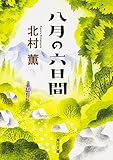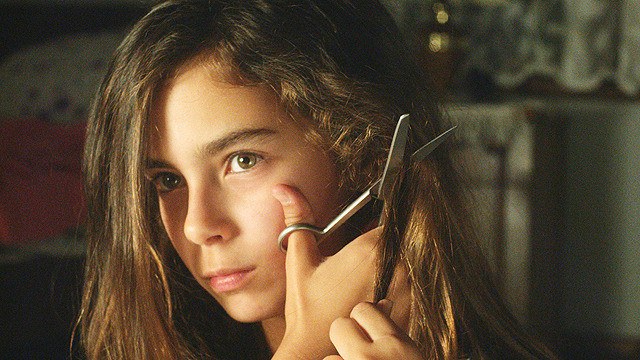タフで、不運。かっこわるくてカッコイイ。
* * * * * * * * * *
ひき逃げで息子に重傷を負わせた男の素行調査。
疎遠になっている従妹の消息。
依頼が順調に解決する真夏の日。
晶はある疑問を抱く(「静かな炎天」)。
イブのイベントの目玉である初版サイン本を入手するため、翻弄される晶の過酷な一日(「聖夜プラス1」)。
タフで不運な女探偵・葉村晶の魅力満載の短編集。
* * * * * * * * * *
若竹七海さんの女探偵葉村晶シリーズ、大好きです。
短編集で当文庫オリジナルとのこと。
ウレシイですねえ。
タフでクール、しかしいつも満身創痍のイメージがありますが、
本作、まずはゆっくりとスタート。
一ヶ月に一作ずつというテンポで話は進みます。
 「青い影」では彼女が大きな交通事故の現場に遭遇するのですが、彼女は無事。
「青い影」では彼女が大きな交通事故の現場に遭遇するのですが、彼女は無事。
ふー、やれやれ、良かった・・・。
その混乱した現場で、葉村は小型車からバッグを取り出して走りだす女性を目撃しますが・・・。
 表題の「静かな炎天」
表題の「静かな炎天」
珍しく葉村のもとに次々に仕事の依頼が入るのですが、
それがまたどれも拍子抜けするくらいに、簡単に片付いてしまいます。
楽勝の物語?
いえいえ、ここで彼女を襲う災難はなんと「四十肩」。
腕が上がらずひどい痛み・・・。
うーむ、葉村さんも、もう若くはありませんねえ。
しかし本作、そもそもこんなに次々と依頼が舞い込むのもちゃんと理由があり、
結局葉村はたったひとつのヒントから、依頼されていない事件まで解き明かしてしまう。
たくらみに満ちた物語。
う~ん、面白い。
 「副島さんは言っている」
「副島さんは言っている」
以前葉村と同僚だった村木が、
何故か入院先の病院で人質に取られた(?!)という事件が発生。
葉村はその犯人・副島と村木からの電話を受け、
副島が巻き起こしたと思われる事件を推理します・・・。
なんともユニークな舞台設定。
とにかく副島が納得できるストーリーを葉村はでっち上げたわけですが、
しかし実はそれはあながちでっち上げではなく・・・?
 ラスト「聖夜プラス1」
ラスト「聖夜プラス1」
クリスマスイブの日。
葉村はある作家の元へ一冊の本をうけ取りに行きます。
その日はその仕事一つだけで終了、のはずでした。
ところが行く先々で用事をことづかり、一日中アチラコチラへと移動して歩くはめになります。
おまけに風邪気味で体調がひどく悪い。
これだ、これでこそ葉村晶。頑張れ葉村晶!
しかし彼女はこんな中でも、けしからん強盗の裏をかいてみせたりする。
四十肩でも、くたびれてヘロヘロでも、
やっぱりカッコイイ、葉村晶なのでした。
コンパクトにまとまっていて、タフだけれど不運続きというユーモラスな展開、
などと思っているうちに、葉村さんの一歩先をゆく推理に驚かされる。
葉村シリーズ入門にも最適、おススメの一冊です。
巻末で、葉村晶のバイト先であるミステリ専門の古書店、店長富山氏が
作中に登場するミステリの解説をしていますが、
多くは海外ミステリで、そちらはほとんど読んでいない私、ちょっと残念でした。
「静かな炎天」若竹七海 文春文庫
満足度★★★★★
 | 静かな炎天 (文春文庫) |
| 若竹 七海 | |
| 文藝春秋 |
* * * * * * * * * *
ひき逃げで息子に重傷を負わせた男の素行調査。
疎遠になっている従妹の消息。
依頼が順調に解決する真夏の日。
晶はある疑問を抱く(「静かな炎天」)。
イブのイベントの目玉である初版サイン本を入手するため、翻弄される晶の過酷な一日(「聖夜プラス1」)。
タフで不運な女探偵・葉村晶の魅力満載の短編集。
* * * * * * * * * *
若竹七海さんの女探偵葉村晶シリーズ、大好きです。
短編集で当文庫オリジナルとのこと。
ウレシイですねえ。
タフでクール、しかしいつも満身創痍のイメージがありますが、
本作、まずはゆっくりとスタート。
一ヶ月に一作ずつというテンポで話は進みます。
 「青い影」では彼女が大きな交通事故の現場に遭遇するのですが、彼女は無事。
「青い影」では彼女が大きな交通事故の現場に遭遇するのですが、彼女は無事。ふー、やれやれ、良かった・・・。
その混乱した現場で、葉村は小型車からバッグを取り出して走りだす女性を目撃しますが・・・。
 表題の「静かな炎天」
表題の「静かな炎天」珍しく葉村のもとに次々に仕事の依頼が入るのですが、
それがまたどれも拍子抜けするくらいに、簡単に片付いてしまいます。
楽勝の物語?
いえいえ、ここで彼女を襲う災難はなんと「四十肩」。
腕が上がらずひどい痛み・・・。
うーむ、葉村さんも、もう若くはありませんねえ。
しかし本作、そもそもこんなに次々と依頼が舞い込むのもちゃんと理由があり、
結局葉村はたったひとつのヒントから、依頼されていない事件まで解き明かしてしまう。
たくらみに満ちた物語。
う~ん、面白い。
 「副島さんは言っている」
「副島さんは言っている」以前葉村と同僚だった村木が、
何故か入院先の病院で人質に取られた(?!)という事件が発生。
葉村はその犯人・副島と村木からの電話を受け、
副島が巻き起こしたと思われる事件を推理します・・・。
なんともユニークな舞台設定。
とにかく副島が納得できるストーリーを葉村はでっち上げたわけですが、
しかし実はそれはあながちでっち上げではなく・・・?
 ラスト「聖夜プラス1」
ラスト「聖夜プラス1」クリスマスイブの日。
葉村はある作家の元へ一冊の本をうけ取りに行きます。
その日はその仕事一つだけで終了、のはずでした。
ところが行く先々で用事をことづかり、一日中アチラコチラへと移動して歩くはめになります。
おまけに風邪気味で体調がひどく悪い。
これだ、これでこそ葉村晶。頑張れ葉村晶!
しかし彼女はこんな中でも、けしからん強盗の裏をかいてみせたりする。
四十肩でも、くたびれてヘロヘロでも、
やっぱりカッコイイ、葉村晶なのでした。
コンパクトにまとまっていて、タフだけれど不運続きというユーモラスな展開、
などと思っているうちに、葉村さんの一歩先をゆく推理に驚かされる。
葉村シリーズ入門にも最適、おススメの一冊です。
巻末で、葉村晶のバイト先であるミステリ専門の古書店、店長富山氏が
作中に登場するミステリの解説をしていますが、
多くは海外ミステリで、そちらはほとんど読んでいない私、ちょっと残念でした。
「静かな炎天」若竹七海 文春文庫
満足度★★★★★