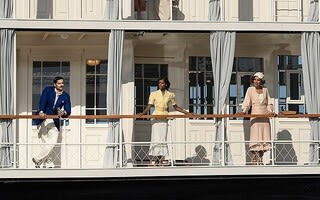文明や歴史を飲み込もうとする自然の力と向き合うこと

* * * * * * * * * * * *
J・R・R・トールキンが現代語訳したことで知られる
14世紀の叙事詩「サー・ガウェインと緑の騎士」を映画化したもの。

アーサー王の甥であるサー・ガウェイン(デブ・パテル)は
酒浸りで自堕落な日々を送っていました。
「騎士」にもなれていません。
そんなクリスマスの日、円卓の騎士が集う王の宴に異様な風貌をした“緑の騎士”が現れ、
恐ろしい首切りゲームを持ちかけます。
「この中の誰か、我こそと思う者は、今ここで私の首を切り落とせ。
そしてその代わりに一年後のクリスマスに、私の屋敷に来るように。
その時に、私がそのものの首を切り落とす。」
というのです。
ガウェインは挑発に乗り、緑の騎士の首を切り落としますが、
騎士は転がった首を拾い上げて去ってしまいます。
さて、一年後。
約束を果たすためにガウェインは緑の騎士の居所を訪ねて、
未知の世界へ踏み出します・・・。

さてさて、なんとも不思議な物語です。
これってゲーム!?と、まず首をかしげたくなりますが、
つまりはガウェインの勇気を試そうという話なのでしょう。

一年後、自らの死を覚悟しながら、ガウェインは旅立つのか。
本当に緑の騎士の元まで行こうとするのか・・・?
ちょっと、走れメロスのようでもあると思ってしまいました。
ただし、身代わりの友が待っているわけでもない。
ただひたすらに、自分の「名誉」のためだけに命をかけることができるのか。
・・・つまり、それが「騎士」であることの資格なのかも知れません。

さてそれはそれとして、とある解説で、
本作にて<緑>は「自然」を、<赤>は「文明」を表わしているというのがありました。
すなわち緑の騎士とは、人の前に立ちはだかる大自然の象徴。
それと対峙する人間、そしてその代表であるガウェインが文明の象徴。
人によって自然は簡単になぎ倒されてしまうけれども、
しかしじきに復元していく。
そしてその勢いは時には人を押しつぶす。
大自然の力に抗おうとするからには、自らの生命が脅かされることも覚悟しなければならない・・・と、
そんなことを言っているようにも思えます。

でも物語の舞台の14世紀、人が自然に抗おうとするといってもたかが知れています。
せいぜいが、少しの森を切り開くくらい。
だから、この物語は現代でこそ意義があるのでは?
あらゆる開発や、二酸化炭素の放出、あふれるプラスチックゴミ・・・
大自然にさからう人の営みがいま、強烈なしっぺ返しを受けていると、
常々感じるところではありますので。

幻想的で不思議な物語。
独特の雰囲気があります。
<シアターキノにて>
「グリーン・ナイト」
2021年/アメリカ・カナダ・アイルランド/130分
監督・脚本:デビッド・ロウリー
出演:デブ・パテル、アリシア・ビカンダー、ジョエル・エドガートン、サリタ・チョウドリー、
ケイト・ディッキー、ラルフ・アイネソン、ショーン・ハリス
幻想度★★★★☆
満足度★★★☆☆