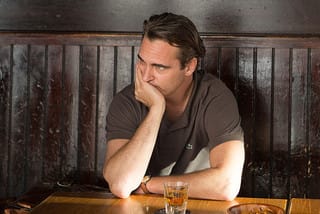自由で孤独な魂

* * * * * * * * * *
マギー・スミスが16年間主演してきた舞台劇の映画化。
・・・ということで、道理でマギー・スミスがこの役にハマっているはずですよね。
汚れ役でありながら、なんだか凄くリアルな人間像を感じます。
まあ、実際、この舞台劇の作家が実体験した話でもあるわけですから・・・。
北ロンドンのカムデンの町に、
オンボロの車に暮らしている老婦人、ミス・シェパード(マギー・スミス)がいます。
劇作家ベネット(アレックス・ジェニングス)は、
路上駐車をとがめられている彼女に声をかけ、
親切心から彼女を自宅の駐車場に招き入れます。
ほんの少しのあいだ・・・と思っていたのが、なんとも計算違い。
なんと彼女はそれから15年もそこに居着いてしまったのでした!

つまりは浮浪者で、悪臭をはなつミス・シェパードですが、態度は高飛車。
もと修道女であったらしいとか、ピアノが得意らしいとか・・・。
そしてなぜかフランス語が堪能。
自分のことなど決して語らないミス・シェパードなのですが、
ふとした言葉の端々とか、昔の彼女を知る人の話などから垣間見える彼女の人生がなんとも興味深く、
ベネットは、迷惑に思いながらも、彼女を観察することに楽しみを覚えてもいたわけでした。
彼女をネタに作品を書いてしまおうという下心もあったりして・・・。

ミス・シェパードが承諾さえすれば、彼女を迎え入れてくれる施設はあるのです。
けれども彼女はそれを断固拒否。
ボロを着て悪臭を放ちながらも、どこか強い意志を感じさせる彼女が、
次第に高潔にさえ思えてきます。

一体何が彼女をこの生活に追い込んだのか、なぜ彼女はこの生活に固執するのか。
それは彼女の若い頃のつらい体験であり、事故であり・・・、
多分一言で言えるようなことではないのでしょう。
でもときには、車椅子で坂を下る爽快さに、子どものように喜んだりもする。
自由で孤独な魂に、どこか惹かれてしまうのです。

人生の不思議、人の気持ちの不思議を感じます。
・・・良い物語でした。

「ミス・シェパードをお手本に」
2015年/イギリス/103分
監督:ニコラス・ハイトナー
出演:マギー・スミス、アレックス・ジェニングス、ジム・ブロードベント、フランシス・デ・ラ・トゥーア、ロジャー・アラム
人生の不可思議度★★★★★
満足度★★★★☆

* * * * * * * * * *
マギー・スミスが16年間主演してきた舞台劇の映画化。
・・・ということで、道理でマギー・スミスがこの役にハマっているはずですよね。
汚れ役でありながら、なんだか凄くリアルな人間像を感じます。
まあ、実際、この舞台劇の作家が実体験した話でもあるわけですから・・・。
北ロンドンのカムデンの町に、
オンボロの車に暮らしている老婦人、ミス・シェパード(マギー・スミス)がいます。
劇作家ベネット(アレックス・ジェニングス)は、
路上駐車をとがめられている彼女に声をかけ、
親切心から彼女を自宅の駐車場に招き入れます。
ほんの少しのあいだ・・・と思っていたのが、なんとも計算違い。
なんと彼女はそれから15年もそこに居着いてしまったのでした!

つまりは浮浪者で、悪臭をはなつミス・シェパードですが、態度は高飛車。
もと修道女であったらしいとか、ピアノが得意らしいとか・・・。
そしてなぜかフランス語が堪能。
自分のことなど決して語らないミス・シェパードなのですが、
ふとした言葉の端々とか、昔の彼女を知る人の話などから垣間見える彼女の人生がなんとも興味深く、
ベネットは、迷惑に思いながらも、彼女を観察することに楽しみを覚えてもいたわけでした。
彼女をネタに作品を書いてしまおうという下心もあったりして・・・。

ミス・シェパードが承諾さえすれば、彼女を迎え入れてくれる施設はあるのです。
けれども彼女はそれを断固拒否。
ボロを着て悪臭を放ちながらも、どこか強い意志を感じさせる彼女が、
次第に高潔にさえ思えてきます。

一体何が彼女をこの生活に追い込んだのか、なぜ彼女はこの生活に固執するのか。
それは彼女の若い頃のつらい体験であり、事故であり・・・、
多分一言で言えるようなことではないのでしょう。
でもときには、車椅子で坂を下る爽快さに、子どものように喜んだりもする。
自由で孤独な魂に、どこか惹かれてしまうのです。

人生の不思議、人の気持ちの不思議を感じます。
・・・良い物語でした。

「ミス・シェパードをお手本に」
2015年/イギリス/103分
監督:ニコラス・ハイトナー
出演:マギー・スミス、アレックス・ジェニングス、ジム・ブロードベント、フランシス・デ・ラ・トゥーア、ロジャー・アラム
人生の不可思議度★★★★★
満足度★★★★☆