「村田エフェンディ滞土録」 梨木香歩 角川文庫
さて、まず、この題名の解説からはじめなければならないでしょう。
そもそも、時代は100年前。明治時代です。
日本からトルコへ留学した青年の物語。
彼は、トルコではエフェンディと呼ばれましたが、それは尊称で、「先生」くらいの意味。
それでつまり、「村田先生のトルコ滞在記録」というわけです。
私自身、これまであまりこの作家の作品は読んでいないのですが、ファンタジーの作家ですよね。
この題名からすると歴史物?と思えるのですが、やはりこれはファンタジーと分類すべきかも知れません。
ただし、荒唐無稽な想像の産物というものではありません。
まず、1899年。
明治政府のもと、多くの面で世界に立ち遅れた日本を何とかヨーロッパレベルまで引き上げようと必死になっていた時代。
時代設定も特異ながら、その時代のトルコとなると、これまで小説の題材としてもほとんどなかったのではないでしょうか。
トルコは西洋、東洋の交わる場所。
トルコ人・ユダヤ人・アルメニア人・ギリシャ人、人種もさまざまなら、宗教もさまざま。
そんな中で、帝国主義の欧州から自国を守らねばならないという複雑で大変な状況下にある。
村田は、このトルコに考古学の勉強をしにきているという設定です。
このようなきちんとした時代考証の中で、想像を自由に膨らませ、登場人物たちが個性豊かに活き活きと生活しているのは、魅力的です。
同じ宿舎に住むギリシャ人のディミトリスは言います。
「(日本の)善き貧しさを保つことだな。
西の豊かで懶惰な退廃の種を、君たちが持ち帰らないようにすることだ。」
それに対する、村田の思い。
「---豊かな退廃など、私は今の日本に想像すらできなかった。
祖国が少しでも豊かになってほしいとの思いで必死、いつくるか分からぬ危険な豊かさへの懸念など、まるで寄せ付けなかった・・・。」
このあたりは、今、まさに「豊かな退廃」に埋もれている日本からすると、ぐっと来ますね。
確かに、当時の日本人はこのような思いで必死だったのだろうと、なんとなく時代の空気が分かる気がしました。
それから、この悠久の歴史を持つ地で、村田はさまざまな不思議な出来事を体験します。
夜彼の部屋の壁にに不思議な映像が浮かび上がったり、
部屋にお稲荷さんの狐の根付を持ち込むと、もともとそこの主であった牡牛の神と追いかけあっている音が聞こえたり、
そこへエジプトのアヌビス像が加わるともっとひどい騒ぎになったり・・・、
それが恐ろしいことではなく、よくあることのように淡々と語られるのが、また、魅力。
単なる物体でも、長年人の想いがこめられて行くと、それもまた、意識を持つようになる・・・、それが神の正体。
これはとても日本的な解釈かも知れないのですが、これは村田の専門である考古学とも非常につながりのあることなのです。
彼は言います。
「消えていった者の声は、遺跡から発掘される壷や皿のかけらにわずかに残存し、誰もいないとき資料室の倉庫で耳を傾ければ、ざわざわとした囁きで部屋中が震えるように緊張して行くのを、過去私は何度体験したことだろう。」
ストーリーと共に想いが100年前へ、さらには果てない過去へとめぐらされる、余韻の深い作品でした。














 え~、疲れました。
え~、疲れました。 2時間50分あったんですね。まあ、退屈はしないけれども、すごいシーンの連続で、さすがに疲れるという。
2時間50分あったんですね。まあ、退屈はしないけれども、すごいシーンの連続で、さすがに疲れるという。



















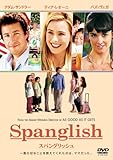


 そうですよ、こういうのは四の五の言わずに楽しむほかないでしょう。
そうですよ、こういうのは四の五の言わずに楽しむほかないでしょう。