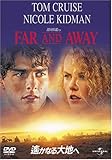裏社会の事情がヒリヒリと伝わる

* * * * * * * *
ベン・アフレックの監督及び主演作品、ということで期待が高まります。
原作はチャック・ホーガン「強盗こそ、我らが宿命(さだめ)」。
ボストンのチャールズタウンが舞台ですが、
ここは全米一銀行強盗発生率の高い街だとか。
・・・何とも物騒ですね。
そこで育ったダグは、やはり父と同じく銀行強盗の道を歩む・・・。
あるとき、強盗に入った先で、支店長クレアを人質に連れ出すことになってしまった。
元々ダグはお金は奪うけれども、人は傷つけない主義。
けれど仲間はそうではなく、そこでまた軋轢が起こったりするのです。
この時は何とかクレアを傷つけることなく、海岸で解放することが出来ました。
ダグたちは覆面をしていたため、クレアにも顔は見られていません。
しかしその後、クレアがFBIに不都合な情報を流したりしないかどうか探るため、
ダグは彼女に接近します。
むろん彼女はダグの正体を知るよしもない。
そしてダグは次第にクレアに強く惹かれていく・・・。

破綻は目に見えていますよね。
けれども、ストーリーに惹きつけられ、目が離せない感じです。
暴力、ドラッグ、売春・・・そういうものが日常茶飯事のダグの生活。
彼は何とかまっとうな生活をしたい、こんな街から抜け出したい、
と強く思っているのです。
そういう彼の目指す夢の象徴がクレア。
嫌ならさっさと抜け出せばいい。
単純にはそう思うのですけれど。
しかしそう簡単には行かない裏の事情というものが、やはりあるんですね・・・。
う~ん、確かにこれではどうしようもないのか。
見ている方も切なくなってきます。
もがけばもがくほど泥沼にはまり込む。

収入の格差が教育の格差を生むといいます。
そういうことがさらに進と、
こんなふうに裏社会のものは裏社会にしか住めないような状況を生み出していくのかなあ、
と思ったりします。
ともあれ、そういう裏社会の切ない事情がひりひりと伝わってくる力作でした。
ベン・アフレックは、結構こういう悪人役もはまりますね。
俳優兼監督として、この先も期待していいのではないでしょうか。
とはいえ、百戦錬磨、酸いも甘いも噛み分けたイーストウッド監督には及びません。
それはもう、経験の差なのでしかたありません。
40年、50年先の彼がさらに楽しみ。
って、考えてみたら、そんなには私は生きられないです・・・。残念。
「ザ・タウン」
2010年/アメリカ/123分
監督:ベン・アフレック
出演:ベン・アフレック、レベッカ・ホール、ジョン・ハム、クリス・クーパー、ブレイク・ライブリー

* * * * * * * *
ベン・アフレックの監督及び主演作品、ということで期待が高まります。
原作はチャック・ホーガン「強盗こそ、我らが宿命(さだめ)」。
ボストンのチャールズタウンが舞台ですが、
ここは全米一銀行強盗発生率の高い街だとか。
・・・何とも物騒ですね。
そこで育ったダグは、やはり父と同じく銀行強盗の道を歩む・・・。
あるとき、強盗に入った先で、支店長クレアを人質に連れ出すことになってしまった。
元々ダグはお金は奪うけれども、人は傷つけない主義。
けれど仲間はそうではなく、そこでまた軋轢が起こったりするのです。
この時は何とかクレアを傷つけることなく、海岸で解放することが出来ました。
ダグたちは覆面をしていたため、クレアにも顔は見られていません。
しかしその後、クレアがFBIに不都合な情報を流したりしないかどうか探るため、
ダグは彼女に接近します。
むろん彼女はダグの正体を知るよしもない。
そしてダグは次第にクレアに強く惹かれていく・・・。

破綻は目に見えていますよね。
けれども、ストーリーに惹きつけられ、目が離せない感じです。
暴力、ドラッグ、売春・・・そういうものが日常茶飯事のダグの生活。
彼は何とかまっとうな生活をしたい、こんな街から抜け出したい、
と強く思っているのです。
そういう彼の目指す夢の象徴がクレア。
嫌ならさっさと抜け出せばいい。
単純にはそう思うのですけれど。
しかしそう簡単には行かない裏の事情というものが、やはりあるんですね・・・。
う~ん、確かにこれではどうしようもないのか。
見ている方も切なくなってきます。
もがけばもがくほど泥沼にはまり込む。

収入の格差が教育の格差を生むといいます。
そういうことがさらに進と、
こんなふうに裏社会のものは裏社会にしか住めないような状況を生み出していくのかなあ、
と思ったりします。
ともあれ、そういう裏社会の切ない事情がひりひりと伝わってくる力作でした。
ベン・アフレックは、結構こういう悪人役もはまりますね。
俳優兼監督として、この先も期待していいのではないでしょうか。
とはいえ、百戦錬磨、酸いも甘いも噛み分けたイーストウッド監督には及びません。
それはもう、経験の差なのでしかたありません。
40年、50年先の彼がさらに楽しみ。
って、考えてみたら、そんなには私は生きられないです・・・。残念。
「ザ・タウン」
2010年/アメリカ/123分
監督:ベン・アフレック
出演:ベン・アフレック、レベッカ・ホール、ジョン・ハム、クリス・クーパー、ブレイク・ライブリー


















 さて、お待ちかねクリント・イーストウッド監督の新作です!
さて、お待ちかねクリント・イーストウッド監督の新作です! ヒアアフターというのはつまり、死後の世界、来世のことなんですね?
ヒアアフターというのはつまり、死後の世界、来世のことなんですね? さて、この冒頭からいきなりスペクタクルシーンで度肝を抜かれました。
さて、この冒頭からいきなりスペクタクルシーンで度肝を抜かれました。

 うーん、これぞドラマですよ。
うーん、これぞドラマですよ。 私は少年が心の癒やしを得るシーンなんか、泣けて泣けて・・・。
私は少年が心の癒やしを得るシーンなんか、泣けて泣けて・・・。 いつも傍らにいた人が亡くなってしまったときの喪失感。
いつも傍らにいた人が亡くなってしまったときの喪失感。