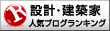そろそろ「寒暖の差」が気になる頃ではないですか・・・・・。
日中の移動時は流石にまだ車中では「暑い時間帯」もあるのですが、
夕方になると・・・・「暖かさ」が恋しくなります。
移動途中の「上着」にも困る時期です・・・・・皆さんはどうですか。
さて、現在・・・奈良・高取町内で工事進行中の
(仮称)借景を楽しむ和モダンの玄関共有二世帯住宅新築工事の現場・・・・・。
工事担当は㈱南工務店さん。
来年で創業50年を迎える・・・吉野の老舗工務店さんで、
口頭だけではなくて、
本当に「住まい手目線」に寄り添っていただける工務店です。
イロイロな意味で今回ご縁があり、工事をお願いすることになりました・・・・・。
現場では建物の基礎工事を行うための準備工事の最中。
イロイロと指示が飛びながら・・・・作業も進みます。
設計図書の「配置図」に沿って・・・・土地の中で「建物の位置」を確定させる作業・・・・・・。
「やりかた」の作業。
「やりかた」とは、敷地のどこに建物を配置するか、位置や高さを決める仮設工事。
隣地境界線や道路境界線からの離れや道路と敷地の高さを決める重要な作業。
設計図書の「配置図」に従って、
現状敷地を確認して・・・・基準となる境界線からの離れを確認。
そこから建築する建物より1m程度外側に木杭を打ち込んで、
「ヌキ」とよばれる板を木杭に基準のレベル(高さ)を合わせて釘などで止めます。
斜め材で固定して・・・・倒れないように設置。
基準となる隣地や道路からの離れを確認して、
直角の墨「印となる目印の墨」を出し、
建物の基準線となる「通り芯」を設置されたヌキに書き込んで・・・・・・・・・・。
最後に道路からの高さや「計画地盤面」からの高さ・・・基礎の高さを決め、
ヌキからの基礎の高さを書き込んで終了・・・・・・。
基礎工事開始時には、「ヌキ」に書かれた芯墨に釘を打ち水糸を張って高さと通り芯を確認しながら
基礎工事のための作業を進めていくわけです・・・・・。
準備段階の工事・・・・カタチとしては「見えてこない部分」ですが、
何度も確認して「チェック」を繰り返して・・・・・「住まい手さんの暮らし」を
カタチにしていく「基礎」・・・そして建物の「基礎」をつくる大切な仕事・・・・・。
対角やその他の部分も「異なる位置」からも何度もチェック。
こういう地道な仕事の繰り返しが「質」をよくするんです・・・・・・・。
朝から奈良県橿原市役所にきて来ています…。
相談をいただきました住まい手さんの家の計画が可能な地域なのかどうなのかを調査中。
計画にはルールがあり、住まい手さんや、
地主さんも知らない法律の壁がイロイロとありますからね。
まずは情報収集。
その情報の量と質により、今後の「計画内容」が変わりますからね・・・・・。
建物の大きさやレイアウト・・・そもそもの「土地」の使い方・・・etc。
イロイロな法律上の制限+ロケーションや住まい手さんの想いなど、
建築をカタチにするための要素は隠れている部分、見えている部分・・・・があるんです。
そこを整理しておかないと「進むべき方向」は決まりませんからね。
同時にイロイロな事を並行して考えておくことが「情報のみえる化」をさせることが出来る
方法ですよ・・・・。