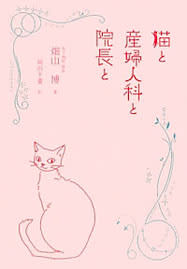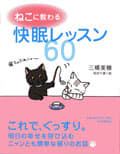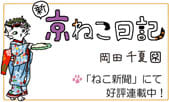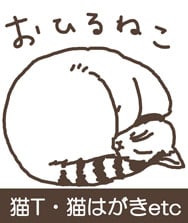ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ
猫と千夏とエトセトラ
カレンダー
| 2006年10月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||
本が出ました
| イラスト(426) |
| 猫マンガ(118) |
| 猫じゃないマンガ(2) |
| 猫(512) |
| 虫(49) |
| 魚(11) |
| works(75) |
| 鳥(20) |
| その他の動物(18) |
| Weblog(389) |
| 猫が訪ねる京都(5) |
| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |
| GIFアニメーション(4) |
最新の投稿
| 節分 |
| 沖縄・三線猫ちゃん |
| 猫又のキミと |
| アダンの浜 |
| サンタさんを待っているうちに寝落ちしてしまった子猫たち |
| 「白い猫塔(にゃとう)」 |
| 新嘗祭 |
| いい猫の日 |
| 「ハロウィンの大収穫」 |
| 銀閣寺~椿の回廊2024 |
最新のコメント
| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| 千夏/残暑 |
| タマちゃん/残暑 |
| 千夏/「豊穣」 |
| タマちゃん/「豊穣」 |
| 千夏/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |
| 与作/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |
| 千夏/家族が増えました |
| 与作/家族が増えました |
最新のトラックバック
ブックマーク
|
アトリエおひるねこ
岡田千夏のWEBサイト |
| それでも愛シテ |
| 手作り雑貨みみずく |
| くろうめこうめ |
| 忘れられぬテリトリー |
| 猫飯屋の女将 |
| 雲の中の猫町 |
| イカスモン |
| タマちゃんのスケッチブック |
| あなたをみつめて。。 |
| 眠っていることに、起きている。 |
| ノースグリーンの森 |
プロフィール
| goo ID | |
amoryoryo |
|
| 性別 | |
| 都道府県 | |
| 自己紹介 | |
| ねこのまんが、絵を描いています。
ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |
|
検索
gooおすすめリンク
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |

寄生虫あれこれ
2006年10月03日 / 虫
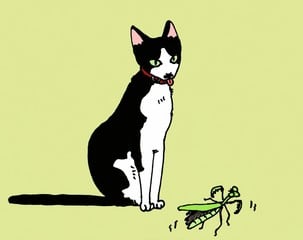
水の中で生まれたハリガネムシの幼虫は、まず水生昆虫に寄生する。そしてその水生昆虫をカマキリが捕食すると、今度はカマキリの体内に寄生し成虫となる。成虫になったハリガネムシはカマキリを水辺に誘導する。カマキリが水辺にたどり着くと、ハリガネムシはカマキリの腹を破って水中に脱出し、そこで交尾・産卵する。
宿主を操って思い通りに誘導するとはまるでホラー映画みたいだが、この誘導のメカニズムは未解明らしい。クラスメイトがやったように、人為的にお尻を水に浸けた場合も、やはり腹を食い破るのだろうか。それとも数十年前のあのハリガネムシは、肛門からするっと出たのだろうか。
猫にも寄生虫がいる。うちの猫は全員がノラ出身なので、なんらかの虫を腹に持っていることが多かった。
まずはネコ回虫。戦後の困窮期を経験した人にとっては懐かしい寄生虫かもしれない。デビンちゃんの便の中に、白く細長い虫がうねうねとのたくっていた。ネコ回虫は、糞便と一緒に出た卵が、毛づくろいの際に再び口に入ってしまったり、生肉を食べることによって感染する。
猫がお尻からゴムひものようなものをぶら下げていたら、それはマンソン裂頭条虫である。条虫とはサナダムシのこと。これは長い。体長が二百五十センチになるという報告もある。外飼い猫のチャプリが、1メートルを超えるサナダムシをお尻に引きずって帰ってきたときには、ぞっとした。虫のからだの上半分はまだ猫の体内にいるので、使い捨てのゴム手袋をはめてつかんで引っ張る。たいていちぎれる。猫を外飼いしている人なら、こういう経験はそれほど珍しいことではない。友人も木の枝で巻き取ったと言っていた。マンソン裂頭条虫は、幼虫の寄生しているヘビやカエルを食べると感染する。
瓜実条虫というのがいる。友人Kは愛猫・太郎と毎晩ひとつの枕で仲むつまじく眠っていた。ある日、枕の周りになにか米粒みたいなものがぱらぱらと落ちているのに気づく。なんだろうこれは。なぜこんなところに。怪訝に思いつつも、たいして気にもとめずにいた…これは瓜実条虫の体の一部がちぎれて猫の体外に排出された片節というものである。瓜実条虫の感染経路はノミである。条虫の卵をノミの幼虫が食べる。ノミが成虫となって猫にとりつき、そのノミを毛づくろいなどで猫が食べてしまい感染する。
実家猫のネロも、やはり両親の枕で寝ていて、この片節をばらまいていた。これが虫の一部だとわかって皆びっくり仰天。猫を飼っているといろんなことがある。猫の寝床に米粒状の物体が散らばっていたら、注意されるのがいいだろう。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )