年末に「第九」が演奏されるのはなぜ?(R25) - goo ニュース
年末の風物詩といえば大掃除や紅白歌合戦、そして“第九”。“第九”とは通称で、『交響曲第9番ニ短調作品125』が本当の作品名。ベートーベンの最後の交響曲として、世界中で愛されている楽曲だ。そんな第九が、年末になると日本各地で演奏されるのには何か意味があるの? 社団法人日本オーケストラ連盟の事務局、加納民夫さんに聞いてみた。
「戦後、貧しかったオーケストラが、いわゆる“もち代稼ぎ”で始めたといわれています。第九には、オーケストラのほかにコーラスも参加するので、出演者の総人数がとても多い。その出演者たちの知人が客として来れば、ふだんより多くの来場者が期待できます。コーラスもプロを雇ってしまうとコストはかさみますが、学生などのアマチュアに頼めば出演料もあまりかからず、オーケストラの収益はアップするのです」
選曲の理由がお金って、なんだか現実的……。とはいえ、マーラーの『交響曲第2番』やホルストの『惑星』などコーラスが入る楽曲は他にもあるのに、なぜ第九が選ばれたのでしょう?
「年末に演奏され始めた1940年代後半、第九はとても人気のある曲でした。当時、第二次世界大戦直後だったために日本はとても貧しく、多くの人が苦労をしていた。そんななかだったので、『歓喜の歌』の名前でも親しまれる前向きなイメージの第九のメロディが、日本人の心をとらえたのでしょう」
(以下略)
 確かに年末になると「第九」の演奏は聞くことが多いような。
確かに年末になると「第九」の演奏は聞くことが多いような。
なるほどですね。
今日のオイラの午前中は買出しに出たのですが、めっちゃ道路が滑りました。
店は混んでいるし、結構ハードな一日。
神棚のしめ縄交換も無事終了することが出来、後は年越しそばを待つだけ。
オイラのブログでは先取り情報を流すことは無いので、つまらない、後付と思われるかも知れませんが、来年もよろしくお願いします。
ニュースで放送されてましたが、今年はフライング福袋なるものが有るそうで、ちょっとビックリ。
カワイイ画がありましたので、強引に話を変えますがこちらの画像はどうでしょう。











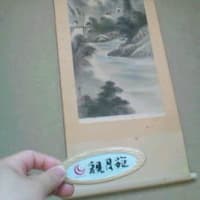









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます