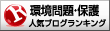一視同仁の愛
1924年、25歳の晃はロンドンにいた。思うところがあって、日々、大英博物館の図書室に通っていた。彼が座って作業をしている席は、かのカール・マルクスが、19世紀中ごろ30年間通って資本論を書いた同じ席であった。そこで晃は、油脂国際取引のための基本条項であるロンドン契約もしくはリバプール契約に関して、調べごとをしていた。これは、欧州へ輸出されるすべての油脂原料がこの契約に基づいて執行されている現状の打破にかかわるものであった。この契約があることで、英国は、いかなる場合でも1%の手数料を手に入れることができた。仮に、積載船が沈没して積み荷がすべて失われても、英国の仲買人は利益を得ていたのである。国際的不平等といえた。
博物館からの帰り道、ロンドン郊外へ向かうバスに乗った。車内はひどく込み合っていたが、とつぜん老齢の英国紳士が立ち上がって、晃に席を譲ろうとした。
「どうぞ、お座りください。」
「ありがとうございます。しかし、私は25歳でまだとても若いので、座らなくても大丈夫です。」
「遠慮なさらないでください、この地はあなたにとっては異国の空です。さぞ不慣れなこともあるでしょう。ただ、その代り、あなたにお願いしたいことがあります。もし我が国の同胞が、あなたの国で困っていたら、ぜひ面倒を見ていただけないでしょうか。」
「もちろんです。」
晃は、かの紳士の暖かい申し出を受け入れることにした。たかがバスの席ひとつ、されどその席が、大きな結果をもたらすこともある。
ロッテルダムに帰って、この話を妻のラウラにした。すると彼女は、興味ある話を聞かせてくれた。
「ロッテルダム港のそばに、子沢山の靴修理屋さんがいるのだけれど、日本人の船員さんを世話しているのですって。なんでも南米に向けて出航した貨物船に乗り遅れた人で、次の航海までここで待っているらしいの。おかみさんの話だと、同じくらいの年の息子さんが南アフリカへ行く貨物船に乗っているらしくて、とても他人事とは思えなくて世話をしているらしいのよ。日本人の船員さんに良くしておけば、きっと神様が息子さんをお守りくださるって言っていたわ。」
一視同仁というのはこのことか、と晃は思った。古くて新しいもの、それは人と人とをつなぐ愛であり、何げない普段の生活の中に生かされてこそ、持続するものなのだろう。
つづく