
毎日のように福島第一原発のトラブルが報告されている。
本当に大丈夫なのだろうか。
こんなに多くの人為的なトラブルが頻発すると、二つのことが考えられる。
作業員が極限的に疲労し、相互にチェックしきれていない。
もしくは、熟練した作業員が枯渇し全くの素人が増えてきている。
いずれにしても、時間との闘いなのだろう。
冗談ではなくて、とても深刻な気がする。
凍土遮水壁は冗談だとして、上策が必要だ。
海外の研究者とやり取りをしながら、いま代案を考えている。
要求として、ふたつの点を満たす手法を探す。
(1)地下水の進入と汚染水の隔離を切り離して考えること。
難しい問題を一つの方法で解決するのは下策だ。
まず地下水を制御し、そして汚染水を隔離すること。
(2)複雑な手法や電気を使わないで、視覚的にわかりやすい手法を考案すること。
システムが複雑になればなるほど、事故の確率が高まる。
可能な限り自然の力を利用することだ。
我々の案はこうだ。
まず、原発施設全体を取り囲むように運河(Canal)を作り、上流から来る地下水を運河に流す。
深さは30mくらだろうか。
この水はやがて海に流れていく。
運河の山側には透水性の壁、施設側には不透水性の壁を作る。
つまり地下水は入りやすく、汚染水は流れ出にくくする。
次に、建屋を取り巻くように内堀(Channel)を作る。
内堀の壁は透水性として、内部の地下水位調整の役割を持たす。
深さは10mもあればよい。
底には不透水性の汚濁防止膜を敷く。
水中に放射性物質を体内に取り込む植物プランクトンを培養する。
定期的に植物プランクトンを捕獲すれば、放射性物質が除去され水中の濃度は減少する。
この水を冷却用に再利用する。
ちょうど、外堀と内堀を備えた城(原発事故記念城)のようなイメージだ。
放射性物質が無毒化する200年後には、ピラミッドのような観光地になっているかもしれない。
次世代の子供たちに役に立つものを残すことは大切なことだ、と思うのだが。











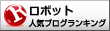

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken




