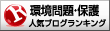記事のタイトルを入力してください(必須) blog.goo.ne.jp/bitex1993/e/14…
損が得になる。
1921年、晃はついにビジネスを開始した。狙いは、三井物産や三菱商事などの大手が取り扱わないもの。満州の大豆粕を仕入れて、南オランダの農業組合に売ることにした。大豆粕というのは、ダイズから油を絞った残りで、よい飼料になる。隙間のビジネスといえる。さっそくオランダ人の飼料取り扱い専門の仲買人と契約を結び、大連の日清製油を通して1トンの大豆粕を購入した。
ところが、荷がロッテルダム着くと、なんと仲買商が雲隠れしてしまったのだ。飼料の急激な値崩れと買い手が見つからなかったことが原因だった。晃は途方にくれてしまったが、契約上、生じた損害をすべてかぶらざるを得なかった。初めてのビジネスが、とんだトラブルを引き起こしたのである。忘れもしない、損失は1800ギルダーにのぼった。今で言えば、1000万円くらいだろうか。
もちろんそんなお金はなかった。支払い先と協議して、借金をすることにした。大豆や油といった利益率の良い物産の荷渡監督をやって手数料から返済をした。毎日懸命に働いて、なんと2年間で負債を完済してしまった。ある日、仕事が終わってホッとしながらロッテルダムの繁華街を歩いていると、逃避していた仲買人とばったり出会った。
「ごめんなさい、アキラさん。ワタシ、ずっとあなたに会いたいと思っていました。まことに申し訳ないことをしました。じつは田舎に逃げ帰っていました。父や母からも、ひどく叱られました。ぜひあなたが蒙った損害を弁償させてください。お願いします。どうぞワタシの不徳を許してください。」
「いや、むしろ、私のほうがお礼を言いたいくらいですよ。この失敗が転機となって私に同情が集まり、逆に大豆や油の差配を任されるようになったのです。今では、ロッテルダムだけでなく、ロンドン、ハル(イギリス)、ハンブルグ、アントワープ、スカンジナビア諸国、オラン(アルジェリア)、カサブランカなど向けの荷渡監督事業を拡大することができました。ずいぶん儲けさせていただきました。あなたには感謝しなければならない。」と晃は切り返した。
この答えに、仲買人は、感極まったように涙ぐんだ。このとき得た心境を、晃は後日、「不二の法門」と呼んでいた。
つづく
オランダ最初の印象
鳥沢晃がジャワからオランダへ移った頃に接触した人物の中に、後藤新平(1857-1929)や大谷光瑞(1876-1948)・松岡静雄(1878-1936)らがいた。いずれも、本業以外に、当時の文化人として特筆すべき活躍をしていた。このような人々から様々な形で支援を得た晃は、まだ二十歳そこそこの若造でありながら稀有な存在だったのかもしれない。意気軒昂として欧州に乗り込んだ当時、かの地も第一次世界大戦が終わり、ようやく復興に向けて歩みだした頃だった。
ロッテルダムは、世界有数の貿易港である。ニューアムステルダム号から下船した晃は、ホテルコーマンに宿をとった。16世紀ころより港として栄えてきたロッテルダムには、日本の名誉領事館があった。早速、ヨング名誉領事に会いに出かけた。彼は世界有数の船会社Van Ommeren社で働いてから、引退後は日本の名誉領事としてオランダと日本の架け橋となっていた。というのも、ヨング氏は、1855年に来日し、長崎出島の海軍伝習所で日本人に蒸気船の運航指導していたからである。この時の一期生として勝麟太郎、二期生として榎本武揚などがいた。また、1866年にドルドレヒトで行われた開陽丸の進水式にも立ち会っていた。この時の日本人留学生には、榎本武陽(釜次郎)、沢太郎左衛門、赤松則良(大三郎)、内田正雄(恒次郎)、田口俊平、津田真道(真一郎)、西周(周助)、伊東玄伯、林研海などそうそうたるメンバーがいた。そんな歴史の生き証人のようなヨング氏も、すでに齢85歳を超えていたが、依然かくしゃくとしていた。
「君は、あの運転手にいくら払ったのかね。」
会社の玄関で晃を迎えたヨング氏は、何か気になったかのように尋ねた。
「運転手に要求された通り、5ギルダー払いました。」
緊張した面持ちで答えた晃に、ヨング氏はこう続けた。
「なんということだ。何も知らない異国人から暴利をむさぼるとは。同じオランダ人として恥ずかしい。申し訳ないことだ。これからは切符を買って電車に乗ってきなさい。」
といって、ポケットから11枚つづりの回数券を取り出して見せた。
晃には、その親切が身に染みてありがたかった。それは、ヨング氏が単に倹約家だったからではない。彼は、ビジネスを立ち上げたばかりの若い晃に対して、心からの忠告をしてくれたのである。
ああ、オランダに来てよかった。この地に悪者はいない。そう、晃はつぶやいた。1920年、年の瀬12月のことだった。
つづく
悪者どもを運んだ船会社
1920年11月30日、ついに晃は、ニューヨークからロッテルダムへ向かうオランダ船籍「ニューアムステルダム号」に乗船した。
2万トンを越える大型客船には400人ほどの乗客がいたが、日本人は晃だけだった。
2年前の1918年に第一次世界大戦が終了し、のんびりとした船旅だった。
十数日かかる航海の慰みに、腕相撲をやろうと提案した。
「おまえのようなチビが勝てるわけがない。」
みながそう言って馬鹿にするのだが、どっこい晃は勝ち続けた。
大きな白人がそろって負けるので、だんだん船中の話題になってきた。
「なぜ、そんなに勝てるのだ。」との質問に、「サンスクリットにいう阿吽の呼吸だよ。」と煙に巻いた。
実際、東洋の神秘的な勝ち方だった。
ちょうどその時、デッキで遊んでいた子供がかけて来た。
一時帰国するチェコスロバキアの家族の一員だった。
「おかあさん、チョコレートちょうだい。」
腕相撲を観戦していた母親が、救命ブイに書かれたNASMという文字を指差して、子供を諭した。
「みてごらん。Never Ask Some Moreって、書いてあるでしょう。もうおねだりしちゃだめです。」
それは、まったくのジョークで、本当は船会社「Netherlands-American Steam Navigation Company」の略称だった。
晃は、思わずオランダ語で口を挟んだ。
「坊や、それは違う。NASMの本当の意味は、Neem Alles Smeerlap Meeだよ。」
どさくさにまぎれて、「悪者を運んだ船会社」と言ったのだ。
とたんに、オランダ人に船長や乗組員が驚愕して騒ぎ出した。彼らは、晃がそれまで英語で会話していたので、てっきりオランダ語を知らないと思っていたのだ。しかも、言った内容に腹を立てていた。
「悪者とは何だ。」船長が怒鳴った。
「その昔、NASMは、オランダからならず者たちを積んで、ジャワやアメリカに運んだ船会社の一つではないか。おかげで植民地では今ひどい目にあっている。もちろん中には日本に蘭学を伝えたように優れた人たちもいて、私はとても尊敬しているのだが。」
そう言い訳をすると、なるほどもっともだと納得をしてくれた。このことは事実だからしかたない。
これには後日談がある。
アムステルダム号がロッテルダムにつくと、どこで聞きつけたのか、当地の新聞記者がやってきた。
取材を受けると、翌日の新聞に「他山の石」と題した晃の記事が載った。
このように、彼が行くところ、決まって楽しい話題が生まれてきた。
得な性分の男である。
つづく
コスモポリタンの恋
「さて、ここまでは、先生の貴重な人生遍歴の序章でした。」
俊一は、そう前置きをして、しばらく沈黙した。
「先生の名前は、鳥沢晃。私の人生の師と言っても良いと思います。彼が歩んだ波乱万丈の人生は、明治・大正・昭和をつなぐ、日本史いや世界史の裏側ともいえるものです。その当時、権威に屈せず、自己を磨き、冷静な分析力を信じ、国際的に生きた日本人の生き様を、今の人々に思い出して欲しいのです。だからこそ、この文章をまとめる決心をしました。日本にも、こんな人がいたことを多くの人に知って欲しいのです。」
いよいよ、先生こと、鳥澤晃の波乱万丈の人生譚のはじまりです。
*****
「ラウラ、会社は認めてくれそうにない。」
晃は、宣教師の娘、ラウラに言った。彼らは、しばらく前に婚約していた。堅物の晃が、なぜラウラと愛し合うことになったのか、自分でも良くわからなかった。オランダ語を学ぶために教会に通っていたら、いつのまにかこうなっていた。それは男と女の、自然の流れだったのかもしれない。女性を避けるようにして歩行していた日本男児の晃からは、想像も出来ないことだった。
「どうする、アキラ。私は絶対に結婚したい。」
18歳になったばかりのラウラは、情熱的な女性だった。その気持ちが、純朴な晃の背中を押していた。
東京の三井物産本社から、実家にも二人が婚約したという連絡がいった。400年間続いた沼津の旧家では、当主である養父が断固反対だった。
「何が悲しくて、日本男性が、インドネシアで会ったオランダ女性と結ばれなければならないのだ。」
そんな強い口調の手紙が来た。
父親は、腹を切ってお詫びするとまで言い出していた。
大変なことになったなと思っていたら、やがて、会社から、東京本社への転勤命令が来た。なんとしてもこの婚約を破棄させようということだった。
逆に、このことが晃の気持ちを決めさせた。
「ラウラ、私は会社を辞めようと思う。やめて、オランダで独立して貿易を行い、その上で結婚したい。」
若い二人の決心は固かった。こうして会社に正式に辞表を提出した。
そして、晃はオランダ語の習得により熱心に取り組むと共に、新しく立ち上げるビジネスの準備にとりかかった。
数ヶ月たってからやっと会社も辞表を受理してくれた。
晃は日本に一時帰国することにした。
必死の説得もあって、父親や伯父もやっと結婚を認めてくれた。
さっそく、ヨーロッパに持っていく品物の見本を買い揃えた。陶器や漆器、アンチモニー製品などであった。
興味深いことだが、アンチモニー製品というのは、江戸時代末期に失職した彫り物師が葛飾区で立ち上げた地場産業で、世界中でここにしかない。日本のオリジナルブランドだ。これに目をつけた晃の商才には、先見の明があったと言える。ヨーロッパに輸出されたアンチモニー技術は、やがて宝石入れやオルゴール・ライターなどに取り入れられ、ベルギーなどで有名になっていくのだった。
さて、とうとう、晃は横浜港をエンプレス・オブ・ロシア(ロシアの女王)号に乗って、カナダへ向けて出航した。1920年大正9年11月初旬のことだった。船は約1週間でバンクーバーへ到着した。それからカナダ横断鉄道で東海岸へ向かい、シカゴを経てニューヨークへたどり着いた。今でも大変な旅程であるのに、この当時はもっとつらかったことだろう。しかし、ニューヨークでヨーロッパへ向かう船待ちをする間に、ジャワに輸出する米国硫安の買取り交渉も行っている。
当時、まさに、怖いものなしの若き貿易商であった。
つづく
修身よりの感化
当時は民間旅客機がなかったので、日本郵船の船でシンガポールへ行き、そこからオランダの船でタンジョンプリオク港に上陸した。この港は、インドネシア第一の都市バタビア(現在のジャカルタ)の表玄関だ。ジャカルタは、もともとヒンズー教徒が4世紀ころに居住地として開いた港町だ。バタビアの名称は、1619年のオランダ東インド会社の設立までさかのぼる。オランダ人の祖先であるドイツの部族Bataviにちなんでこの名称がつけられたという。1942年に日本軍が占領するまで、約300年間、バタビアと呼ばれ続けた。バタビアから汽車に乗り、ジョグジャカルタ、ソロー(スラカルタ)を経て3日かけてスラバヤに着いた。
「あなたは、バイテンゾルグ植物園という名前を知っていますか。」と先生が聞いた。
「いえ、知りません。何ですか、それは」俊一は尋ねた。
「バイテンゾルグ植物園は、1817年に設立された世界最大の熱帯植物園だ。今は、ボゴール植物園と呼ばれている。ジャワに赴任した時、私は最初にここを見学した。実は、現地における私の主な仕事は、オランダ語で書かれた東印度植物栽培書の翻訳だったのだ。そのために、オランダ語とマレー語を習熟する必要があった。」
こうした語学の習得は、先生にいろいろな仕事をもたらした。スマランという港では、日本に砂糖を輸出し、満州や日本から硫安をまたオーストラリアから小麦粉を輸入していた。三井商船を使っていたが、船長を含めて乗組員は言葉が十分に通じなかった。病気や検疫、証明書の発行など問題が起こるたびごとに先生は呼び出されたという。
第一次世界大戦中に、オランダ領インドネシアは中立を保っていたので戦争特需に沸いていた。
「ゴムとか砂糖の農園や工場ではよく儲かっていたのだね。どんどんボーナスを出すので、いろいろな種類の人間が集まってきた。中には悪いやつもいて、特にオランダ人の道徳の乱れはひどいものだった。博打、酒、女、暴力、汚職、薬物なんでもありの感があった。あまりひどいので、高校のオランダ人教師に文句を言った。」
「なんと言ったのですか。」
「ハールレムの英雄という話を聞いたことあるかい。オランダは、土地を増やすために堤防を作って干拓した土地が多い。ある日の夕方、ハンス・ブリンカーという少年が堤防に穴が開いていることを見つけた。周りに誰もいなかったので、少年は穴に手を突っ込んで堤防の決壊を防ごうとした。彼は一晩がんばって国を救ったのだ。この話は日本でも修身(道徳)の教科書に『オランダ魂』という題で載っている有名な話だ。そんな英雄がいるオランダ人が、ジャワで横暴のやり放題をしているのはなぜなのだ、と聞いたのだ。」
「どういう答えが返ってきたのですか。」
「それが傑作でね。あの話は、アメリカの作家メアリ・メイブス・ドッジという人が1865年に書いた『銀のスプーン』という本の中に載っている作り話なのだ。実話ではないのだ。メアリは、オランダに行ったこともなかったらしい。オランダ人の教師は苦笑いしながらこういったよ。『植民地にいるオランダ人を見て、本国のオランダ人を批判しないで欲しい。』と。何事も、よく調べてから判断することが大切だね。」
つづく
ナポレオンと西郷隆盛
「不屈の意志と強い力、それが人生を変えていく。」
先生はそう言って、片目をつぶってみせた。
「私が三井物産に就職したのは、1917年、19歳の時だった。ちょうど第一世界大戦の真っただ中で、世の中は騒然としていた。そんな中、私が最初に派遣されたのが、中国の上海だった。」
当時、中国は袁世凱を大総統とする中華民国の時代だった。列強は、中国に数多くの租借地を得ており、日本も遅れてその争いに参加していた。1914年に、ドイツとの戦いに勝った日本は、青島を奪取するとともに、翌1915年には対華21か条の要求を突き付けた。このことが、中国の対日運動に火をつけた。一方、ロシアでは、1917年に10月革命が起こっていた。
そんな中、先生はフランス租界にある社宅に住んでいたが、半年後には共同租界四川路にあるイギリス人宣教師の家に下宿し、英語と北京語、上海語を懸命に学んだ。
「私は、会計課に勤務していた。知識に貪欲で、暇さえあれば無我夢中でいろいろなことを学んだ。一日3時間しか眠らなかったボナパルト・ナポレオンを気取って、ひと月に何日も徹夜をして勉強したのだ。特に、銀本位制の上海租界地では、両(中国銀貨)とメキシコ銀貨を併用していたので、イギリス人の為替ブローカーに強い興味を持っていた。」
そういう時、小柄な先生の体躯からは想像できないくらいの熱いエネルギーが感じられた。
「商業高校しか出ていない私の初任給は、月5円だった。大卒の初任給は出身大学によって異なるが、月に25円から40円だった。いくらいい仕事をしても、私の給料が上がることはなかった。悔しかったので、西郷隆盛の『天を相手にせよ』という言葉を思い出して自分を慰めていた。」
「何ですか、西郷隆盛の言葉というのは。」
「はは、少し古い表現かな。西郷隆盛の遺訓だよ。『人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし』というのだよ。まあ、三井物産を相手にせず、天に貸しておく程確かなことはない、という気分かな。」
「含蓄がありますね。私も、人を信じないわけではないのですが、あてにしないようにしています。あてが外れたときに悲しいですから。」
「なるほど。とにかく、自分のエネルギーを吐き出すために、朝は新公園までジョギングをし、夜は上海同文書院で剣道をしていた。それでも、会計事務ではうだつが上がらないと思ったので、商事の実務をさせて欲しいという嘆願書をだした。」
「それで、どうなりました。」
「中国奥地の出張員になってもいいと思っていたのだが、インドネシアへ行けと言われた。ちょうど三井物産が熱帯地産業に投資をしようとしていて、インドネシア第二の都市であるスラバヤというところに支店を作ったばかりだった。そこで、私は、オランダ語、マライ語、スンダ語を勉強することになった。このことが、私の運命の転機となったのだよ。『六根清浄大祓(ろっこんしょうじょうおおはらえ)に曰く、為すところの願いとして成就せずということなし』と言ったところかな。」
だんだんわけがわからなくなってきた。
つづく
数奇な運命
83年間の長い人生を振り返るように、先生はゆっくりと切り出した。
「私はね、4歳まで静岡県沼津市にある我入道という漁村で育ったのだよ。父は沼津の旧士族の次男坊だったが、当時は東京で気ままに暮らしていた。その時、たまたま浅草で知り合った女性との間に生まれたのが私だった。1898年、明治31年のことだよ。1895年に日清戦争が終わって、官民ともに浮かれていた時代でね。当時は身分が違うということで、私は生まれてすぐに母親から引き離され、この地の漁師の家に里子に出された。小さかったから乳母が必要だったのだ。」
明治という言葉は、俊一にある種の感慨をもたらした。明治維新が1868年だった。それから富国強兵に努め、日本はひたすら欧米に追い付こうともがいてきた。それは、江戸時代という、鎖国であったがゆえに太平であり、太平であったがゆえに箱庭であった世界から、突然、列強という嵐の中に放りだされ、文明開化という新しい価値観の中で翻弄されていた時代でもあった。ことの是非はさておき、日清戦争の勝利は、箱庭から大陸へと、多くの若者の血をわきたてるには十分なできごとだったのだろう。先生の話には、そんな時代の重みと不思議な明るさがあった。
「5歳になると、私は、沼津の伯父の家に移された。本家を継いでいた伯父はとても厳格でね、質実剛健を絵にかいたような人だった。おかげで、学業もスポーツも人後に落ちることはなかった。母親はいなかったが、祖母がとても優しくしてくれた。両親の愛情を受けなくても、特にぐれずにそれなりに育ったのも、叔父と祖母のおかげだったと思っている。」
「淋しいということはなかったのですか。」と俊一は尋ねた。
「小さい時からそういう境遇だったから、あまり気にならなかったね。ただ、早く自立して、沼津の家を出なきゃ、とずっと思っていた。それが、自分の運命のような気がしていたのだよ。」
こうして先生は、沼津で幼稚園、尋常高等小学校と進み、沼津商業学校に入学した。現在は静岡県立沼津商業高等学校となっているが、当時の沼津商業学校は、先生が生まれた1898年(明治31年)に創立されていた。予科3年、本科2年というのが標準だった。中学校と高等学校が一緒になった専門学校のような位置づけだったと思う。予科で全科目の平均点が95点以上という優秀な成績を収めた先生は、授業料が免除される特待生となって本科に進んだ。そして、加地という校長先生の推薦を得て、三井物産に就職が決まった。三井物産は、1876年に井上馨が創業した総合商社として、三菱商事や住友商事と並んで日本の貿易を牽引していた。やっと沼津から抜け出せる。先生の自立への夢は大きく膨らんでいった。
先生は、小さく目を瞬かせ、遠くを見るようにして言った。「不思議なのだよね。それまで音信不通だった父親が突然やってきて、浅草へ行けと言うのだ。そこで母親が待っていると。」
「初めて会った母親は、小柄だけどとても美しい人だった。ずっとこの時を待っていてくれたのだろうね。私の手を握って離さないのだよ。時はまさに、浅草オペラの流行の頃でね。大正浪漫というか日本のオペラの幕開けの時代だった。二人でオペラを楽しんだ後、駒形『どぜう』を食べに行った。何を話したかあまり覚えていないが、一日中付き合ってくれたね。運命とはいえ、母親っていいなと思ったよ。」
ちょうど、関東大震災の少し前で、
女房もらって うれしかったが
いつも出てくる おかずはコロッケ
今日もコロッケ 明日もコロッケ
というオペレッタ「カフェーの夜」の劇中歌「小唄コロッケー」が大ヒットしていた時代でもあった。
つづく
物語のはじまり
晴れた秋の空に薄い白雲がたなびき、湖面の照り返しがさわやかなきらめきを窓辺に届けていた。
先生は、デッキチェアーに腰掛けながら、おもむろに語りはじめた。
「そうだね。この世の中は不思議なもので、楽しいこともあれば苦しいこともある。私はね、子供のころ両親の愛を知らなかったのだよ。でも、今はとても幸せに感じている。どうしてだかわかるかい。」
問われて、俊一は首をかしげた。
「それは、いつも何とかなるさ、と思ってきたからだよ。行き詰ったら、初めて打開の道が開かれるのさ。それを繰り返していくうちにだんだん成功するようになって、この年になるまで何とか生きてくることができたのだよ。」
先生が語る言葉は、なぜだか俊一の心には新鮮に響いた。その語り口には、気負いが全く感じられなかった。
「成住壊空(じょうじゅうえくう)という仏教の教えを知っているかい。」
無言で首をかしげる俊一に、先生は言葉をついだ。
「とても不思議な話なのだが、仏教では、と言っても元はヒンズー教の考えなのだけど、宇宙を四つの期間に分けているのだ。これを四劫(しこう)といって、一劫はおよそ43億年にあたるのだよ。」
「ずいぶん長い期間ですね。一劫というのは、ちょうど今の地球の年齢と同じくらいですか。」と俊一が合いの手を入れた。
「そうだね。成劫(じょうごう)というのが最初の期間で、宇宙のすべての物質がこの時期に作り出されたと言われている。」
「ということは、そのあとに住劫(じゅうごう)や壊劫(えごう)、空劫(くうごう)などという期間が続くのですね。」
「そのとおりだよ。作られ、保たれ、壊され、空になる。宇宙はそれを繰り返しているのだと、古代のインド人は考えたわけだ。」
面白そうな話だ、と俊一は思った。
「人の一生も同じだよ。生まれ、育ち、老い、死を迎える。君はまだ若いから、住劫かもしれないね。」
先生は、そう言いながら、ふと俊一に顔を向けた。
「もしよかったら、私の波乱万丈な遍歴の話を聞いてくれるかな。」
もちろん、という顔をして俊一はうなずいた。










 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken