 取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。
取材意欲を感じた。その後、4年間の能登での取材と考察をまとめたのが、上記の著書である。読み続けると、行間から能登の人たちへの敬愛がにじみ出ていて、引き込まれる。藤井氏が赴任したころ、能登には一つの大きなエポックメイキングが始まろうとしていた。国連食糧農業機関(FAO)による世界農業遺産(GIAHS)に日本で初めて能登と佐渡がエントリーしていて、6月のGIAHS国際フォーラム(中国・北京)で認定の可否が注目されていた。藤井氏と名刺を交換した5月は、世界農業遺産についての勉強会が朝日新聞金沢総局の主催で開かれた日だった。その後、「能登の里山里海」がGIAHSに認定され、人々のさまざまな動きが始まる。それをつぶさに観察して、朝日新聞石川版で「能登の風」とのタイトルで連載記事を連ねた。著書の中で述べている。「能登には『超一級品』がない」のになぜ世界農業遺産に認定されたのか、疑問を持ちつつ、能登の世界農業遺産という時代の風と人々の動きを丹念に追っている。
能登半島の先端・珠洲(すず)市に隣り合わせに狼煙(のろし)と横山という2地区がある。隣接地だが、観光と漁師の狼煙と純農村の横山は気質の上でも折り合いが悪く、原発立地計画をめぐってしこりも残った。2003年に原発計画は凍結され、気が付いてみると両地区は過疎と高齢化に見舞われていた。狼煙は水田の4割が耕作放棄地になっていた。隣の横山は在来種の大浜大豆の栽培に活路を見出し、豆乳や豆腐の加工品の販売に活路を見出した。そこで、狼煙に禄剛崎灯台という「さいはての灯台」が観光地としてあり、両地区の住人が出資して「道の駅狼煙」の運営会社をつくった。大豆の関連商品の売上年間2200万にもなり、観光客も増えてきた。お互いに協働を模索し、観光と農業がうまくマッテイングした。能登にはそんな風が吹いている。藤井氏が発掘した記事だ。
⇒10日(木)午前・金沢の天気 くもり










 和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』
和紙をイメージするのだが、画像変化カードは意外だった。女将の名前は小田真弓さん、その小田さんが日経新聞出版社から本を出した。『加賀屋 笑顔で気働き~女将が育んだ「おもてなし」の神髄~』 現在80歳超えた著者は東京大学や政策研究大学院大学で、日本近現代史を切り開いた研究者である。本の帯にも書かれている通り、若き日の共産党体験や、歴史観をめぐる論争、伊藤博文から佐藤栄作にいたる史料収集と編纂の経緯を回想している。著書の後半では、岸信介や後藤田正晴、竹下登らへのオーラル・ヒストリーの秘話やエピソードが綴られていて興味深い。
現在80歳超えた著者は東京大学や政策研究大学院大学で、日本近現代史を切り開いた研究者である。本の帯にも書かれている通り、若き日の共産党体験や、歴史観をめぐる論争、伊藤博文から佐藤栄作にいたる史料収集と編纂の経緯を回想している。著書の後半では、岸信介や後藤田正晴、竹下登らへのオーラル・ヒストリーの秘話やエピソードが綴られていて興味深い。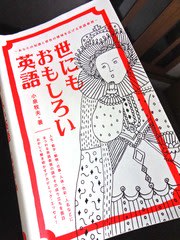 言葉は人間が使うものだから少々の感性のズレはあっても、似たような表現になる、それも英語も日本語でもある。日本語で「鼻差で」「間一髪で」という表現がある。鼻差で、あるいは髪の毛1本の差は、わずかの差でという意味だ。この表現は英語表現でも使われるという。たとえば、win by the nose あるいは win by a hair である。日本語を英訳したのではなく、もともとイギリスやアメリカでも使っている。
言葉は人間が使うものだから少々の感性のズレはあっても、似たような表現になる、それも英語も日本語でもある。日本語で「鼻差で」「間一髪で」という表現がある。鼻差で、あるいは髪の毛1本の差は、わずかの差でという意味だ。この表現は英語表現でも使われるという。たとえば、win by the nose あるいは win by a hair である。日本語を英訳したのではなく、もともとイギリスやアメリカでも使っている。 著者は京都大学東南アジア研究所に所属する文化人類学者。研究者の著書は読み辛いものなのだが、ジャーナリストのルポルタ-ジュを読んでいるような感覚でリズミカルに読めるのである。それは、本人が学術書というより、ルポを意識して書いているからだ。時には少し自らの感情も込めて。それは本人が第9章~「山奥どうし」の国際協力~で述べているように、1991年のフィリピン・ルソン島ピナツボ火山の噴火を目の当たりにして、それまでの文化人類学者の「冷静な観察」から踏み出して、「現場の問題と深くコミットしていくことを選んだ」といい、それを「コミットメントの人類学」「応答する(協働する)人類学」と称している。気が入っているから読みやすい、読ませるのである。ただ本人は「現場に深入りしたら研究ができなくなるかもしれないと恐れつつ」と躊躇したことも吐露している。
著者は京都大学東南アジア研究所に所属する文化人類学者。研究者の著書は読み辛いものなのだが、ジャーナリストのルポルタ-ジュを読んでいるような感覚でリズミカルに読めるのである。それは、本人が学術書というより、ルポを意識して書いているからだ。時には少し自らの感情も込めて。それは本人が第9章~「山奥どうし」の国際協力~で述べているように、1991年のフィリピン・ルソン島ピナツボ火山の噴火を目の当たりにして、それまでの文化人類学者の「冷静な観察」から踏み出して、「現場の問題と深くコミットしていくことを選んだ」といい、それを「コミットメントの人類学」「応答する(協働する)人類学」と称している。気が入っているから読みやすい、読ませるのである。ただ本人は「現場に深入りしたら研究ができなくなるかもしれないと恐れつつ」と躊躇したことも吐露している。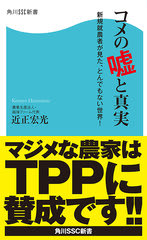 東京の不動産会社の社員(著者)が社長命令で、生まれ故郷の新潟でコメ生産を中心とした食糧事業部門を立ち上げる予定だったが、困難が待ち受ける。農地法に阻まれ個人負担で農業生産法人「越後ファーム」をつくり新規就農を始める。さらにそこから見えた農の世界。消費者のことなど一考もしない、「保護漬け」になり向上心を失った、コメの生産の場だった。農地法、農業委員会、村社会(兼業農家)など、コメを「ダメにした」存在と出会い面食らう。そこから著者が立ち上がる。機械化・大型化が条件の「集約型の米作農業」が不可能な中山間地=里山であえて耕作し、機械化・大型化とは真逆の「手作業農業」を選択するのである。
東京の不動産会社の社員(著者)が社長命令で、生まれ故郷の新潟でコメ生産を中心とした食糧事業部門を立ち上げる予定だったが、困難が待ち受ける。農地法に阻まれ個人負担で農業生産法人「越後ファーム」をつくり新規就農を始める。さらにそこから見えた農の世界。消費者のことなど一考もしない、「保護漬け」になり向上心を失った、コメの生産の場だった。農地法、農業委員会、村社会(兼業農家)など、コメを「ダメにした」存在と出会い面食らう。そこから著者が立ち上がる。機械化・大型化が条件の「集約型の米作農業」が不可能な中山間地=里山であえて耕作し、機械化・大型化とは真逆の「手作業農業」を選択するのである。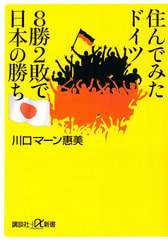 本著での「我々は原爆を持っているが、ドイツはマルクを持っている」と、ドイツを見つめるフランス人の考え方が圧巻だ。これは1989年、「ドイツ統一とユーロ導入の裏事情」という下りで出てくる。ドイツの経済は強く、ミッテラン大統領はドイツが統一を望むならとユーロ導入を強力に勧めた。他国が望まなかったドイツ統一の代償として、ドイツはマルクを手放したという裏情報である。これは腑に落ちる。壮絶な政治的駆け引きがあったのだろう。でもドイツはその後、ユーロ導入で域内の関税はなくなり、為替変動のリスクもなく、輸出大国ドイツの地位を確立する。が、ギリシア財政危機が表面化し、ユーロ圏が一蓮托生となるとのドイツにも焦りが生じる。ドイツもユーロ圏を抜けたがっているのだろうと想像に難くない。それでも、ドイツは近隣から憎まれる。ドイツがギリシアに対して財政規律と緊縮財政を求めれば、求めるほど、ドイツのメルケル首相に「ナチの制服を着せたカリカルチュアがギリシアの雑誌に出回る」ことになる。ドイツも辛い。
本著での「我々は原爆を持っているが、ドイツはマルクを持っている」と、ドイツを見つめるフランス人の考え方が圧巻だ。これは1989年、「ドイツ統一とユーロ導入の裏事情」という下りで出てくる。ドイツの経済は強く、ミッテラン大統領はドイツが統一を望むならとユーロ導入を強力に勧めた。他国が望まなかったドイツ統一の代償として、ドイツはマルクを手放したという裏情報である。これは腑に落ちる。壮絶な政治的駆け引きがあったのだろう。でもドイツはその後、ユーロ導入で域内の関税はなくなり、為替変動のリスクもなく、輸出大国ドイツの地位を確立する。が、ギリシア財政危機が表面化し、ユーロ圏が一蓮托生となるとのドイツにも焦りが生じる。ドイツもユーロ圏を抜けたがっているのだろうと想像に難くない。それでも、ドイツは近隣から憎まれる。ドイツがギリシアに対して財政規律と緊縮財政を求めれば、求めるほど、ドイツのメルケル首相に「ナチの制服を着せたカリカルチュアがギリシアの雑誌に出回る」ことになる。ドイツも辛い。 中でも食品添加物は直接体に入ってくる。食品添加物には合成添加物と天然添加物があるが、合成添加物はいわゆる化学物質、431品目もある。スーパーやコンビニ、自販機、また一部の居酒屋や回転ずしなどで購入したり食する食品に含まれる。長年気にはなっていたが、その数が多すぎて「どれがどう悪いのかよう分からん」とあきらめムードになっていた。たまたま薦められて、『体を壊す10大食品添加物』(渡辺雄二著・幻冬舎新書)を読んだ。10だったら、覚えて判別しやすい、「買わない」の実行に移せる。
中でも食品添加物は直接体に入ってくる。食品添加物には合成添加物と天然添加物があるが、合成添加物はいわゆる化学物質、431品目もある。スーパーやコンビニ、自販機、また一部の居酒屋や回転ずしなどで購入したり食する食品に含まれる。長年気にはなっていたが、その数が多すぎて「どれがどう悪いのかよう分からん」とあきらめムードになっていた。たまたま薦められて、『体を壊す10大食品添加物』(渡辺雄二著・幻冬舎新書)を読んだ。10だったら、覚えて判別しやすい、「買わない」の実行に移せる。 キャロラインさんの話を思い出しながら、『里山資本主義』(著者:藻谷浩介・NHK広島取材班)を読んだ。消費生活と呼ばれる現代の都会の暮らしと対極にあるのが、山林や山菜、農業など身近にある資源を活用して、食糧をなるべく自給し、エネルギーも自ら得て暮らす、地方の自立的な暮らし方である。著者は、前者をマクロ的に表現して「マネー資本主義」と称し、後者を「里山資本主義」と名付けている。後者、たとえばキャロラインが語った「野菜が足りなければ、近所と物々交換するの。お金が少なくても、里山の生活はお金がかからないので暮らしは豊か」な経済的な暮らしは「贈与経済」とも呼ばれてきた。「里山の資本=資源」で暮らすライフスタイルという意味であり、独特の金の流れ(金融)があったり、経済構造を抜本的に変えるというわけではない。
キャロラインさんの話を思い出しながら、『里山資本主義』(著者:藻谷浩介・NHK広島取材班)を読んだ。消費生活と呼ばれる現代の都会の暮らしと対極にあるのが、山林や山菜、農業など身近にある資源を活用して、食糧をなるべく自給し、エネルギーも自ら得て暮らす、地方の自立的な暮らし方である。著者は、前者をマクロ的に表現して「マネー資本主義」と称し、後者を「里山資本主義」と名付けている。後者、たとえばキャロラインが語った「野菜が足りなければ、近所と物々交換するの。お金が少なくても、里山の生活はお金がかからないので暮らしは豊か」な経済的な暮らしは「贈与経済」とも呼ばれてきた。「里山の資本=資源」で暮らすライフスタイルという意味であり、独特の金の流れ(金融)があったり、経済構造を抜本的に変えるというわけではない。 朝日新聞の書評欄に『海女(あま)のいる風景』(大崎映晋著・自由国民社)=写真=を見つけ、本を書店に注文した。大正9年(1934)生まれで、水中撮影家でもある著者は昭和30年代から全国の海女村に取材に出向き、特に石川県輪島市の舳倉島(へぐらじま)に通い、当時は普通だった裸海女の仕事ぶりを撮影した。その写真が多数収録されているというので、価値があると思い、注文した。当時の裸海女の写真はモノクロではいくつか本がある。ただ、カラー写真はお目にかかったことがない。届いた本の写真は予想通りカラーだった。水中を潜る裸海女の写真は、まるで人魚のような美しさである。それはまったく無駄のない、潜水技術の洗練されたフォルムなのである。素潜りで数分のうちに、岩にへばりついたアワビを見つけ、剥ぎ取るのである。採取ではない、海底でへばりついたアワビと格闘する、まさに自らの命をかけた狩猟なのである。英語での表記は female shell diver だ。
朝日新聞の書評欄に『海女(あま)のいる風景』(大崎映晋著・自由国民社)=写真=を見つけ、本を書店に注文した。大正9年(1934)生まれで、水中撮影家でもある著者は昭和30年代から全国の海女村に取材に出向き、特に石川県輪島市の舳倉島(へぐらじま)に通い、当時は普通だった裸海女の仕事ぶりを撮影した。その写真が多数収録されているというので、価値があると思い、注文した。当時の裸海女の写真はモノクロではいくつか本がある。ただ、カラー写真はお目にかかったことがない。届いた本の写真は予想通りカラーだった。水中を潜る裸海女の写真は、まるで人魚のような美しさである。それはまったく無駄のない、潜水技術の洗練されたフォルムなのである。素潜りで数分のうちに、岩にへばりついたアワビを見つけ、剥ぎ取るのである。採取ではない、海底でへばりついたアワビと格闘する、まさに自らの命をかけた狩猟なのである。英語での表記は female shell diver だ。





