 いるとメディア各社が報じている=写真=。実現すれば、現役のアメリカ大統領としては初めてのことだが、それより何より、オバマ大統領が掲げる「核兵器のない世界」に向けた国際的な取り組みを継続的に発展させるためのシンボリックな一歩となる。
いるとメディア各社が報じている=写真=。実現すれば、現役のアメリカ大統領としては初めてのことだが、それより何より、オバマ大統領が掲げる「核兵器のない世界」に向けた国際的な取り組みを継続的に発展させるためのシンボリックな一歩となる。オバマ大統領がまだ訪問を鮮明にしていないのは、アメリカ国内の退役軍人らを中心に「原爆投下によって終戦が早まった」とする意見が根強いからだろう。オバマ氏が広島を訪問する目的を「謝罪」ではなく、「不戦の誓い」の献花でよいのではないか。オバマ大統領の広島での献花の後、安倍総理が機会をつくって、今度はハワイのパールハーバーで献花すれば、日米相互の信頼関係を新構築する外交のチャンスだと考える。
日本政府がアメリカをはじめとする連合軍の占領から統治権を回復するまで、原爆問題はタブーだった。連合国軍総司令部(GHQ)の指令によって、日本のメディア(主に新聞、ラジオ)は情報統制(プレスコード)下に置かれたからだ。プレスコードの内容は、1)報道は絶対に真実に即すること、2)公安を害するようなものを掲載してはならない、3)連合国に関し虚偽的または破壊的批評を加えてはならない、4)連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、または軍に対し不信または憤激を招くような記事は一切掲載してはならない、5)連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載しまたは論議してはならない、といったものだった。つまり、原爆の問題性を議論することそのものがこうしたプレスコードにひっかかった。
1952年4月のサンフランシスコ講和条約以降になって、日本国内で自由に原爆問題が議論された。また、広島に平和記念公園が開設された1954年から現在の平和記念式典が開催されるようになった。戦争の恐ろしさと参戦という悲惨な過ちを繰り返さないという趣旨の行事であり、アメリカ側に原爆投下の責任を求める集会とはなっていない。
むしろ、アメリカに原爆投下の責任を問うたのはストックホルム・アピール(1950年3月)だろう。1949年、ソビエトによる原爆保有声明が発せられ、アメリカのトルーマン大統領が水爆製造命令を出すなど、米ソの核軍備競争が過熱し出した。国際緊張が高まり、1950年3月にスウェーデンのストックホルムで開催された平和擁護世界大会で、「原子兵器の絶対禁止」「原子兵器禁止のための厳格な国際管理の実現」「最初に原子兵器を使用した政府(アメリカ)を人類に対する犯罪者として扱われるべき」とのアピールを採択された。世界中で署名運動が繰り広げられ、2億7347万の署名が集まったとされる。
日本では署名が639万の署名が集まった。しかし、1950年の平和擁護世界大会に日本代表として作家の川端康成ら3人が派遣される計画だったが、GHQの渡航許可が得られず、出席は果たされなかった。
同年(1950年)6月に朝鮮戦争が始まり、国連軍総司令官のダグラス・マッカーサーが核兵器使用を主張したが、トルーマン大統領はマッカーサーの司令官を罷免し、核兵器使用は見送られた。この核兵器使用の見送りはストックホルム・アピールや署名活動など国際的な反核運動の高まりが背景にあったとされる。
北朝鮮は、アメリカと韓国の両軍による合同軍事演習を非難し、遂行するならば米韓両国に「無差別の」核攻撃を実施するとの談話を発表している(2016年3月7日付・BBCウエッブ版)。核兵器の使用を「正義の核先制攻撃」とする北朝鮮の挑発する事態の中でこそ、オバマ大統領のヒロシマ・アピールが期待される、と考えている。
⇒23日(土)午前、金沢の天気 はれ










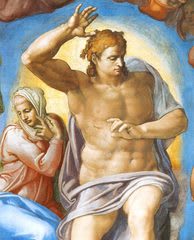 は65%が「正しかった」と回答した、という。
は65%が「正しかった」と回答した、という。 がすがしい感じがした。
がすがしい感じがした。 公園の桜は春の嵐で桜吹雪の状態になっていた。そして、自宅の庭に出て、観察するとタイツリソウやイワヤツデといった花が咲き始めている。このタイツリソウは、面白い花だ。ネットで調べてみると、タイツリソウは別名で正式にはケマンソウ(ケシ科)。中国や朝鮮半島に分布していて多年草です。日本には15世紀の初めの室町時代にに入ってきらしい。ケマンソウの名前は花を寺院のお堂を飾る装飾品「華鬘(けまん)」に見立てて付けられたとか。
公園の桜は春の嵐で桜吹雪の状態になっていた。そして、自宅の庭に出て、観察するとタイツリソウやイワヤツデといった花が咲き始めている。このタイツリソウは、面白い花だ。ネットで調べてみると、タイツリソウは別名で正式にはケマンソウ(ケシ科)。中国や朝鮮半島に分布していて多年草です。日本には15世紀の初めの室町時代にに入ってきらしい。ケマンソウの名前は花を寺院のお堂を飾る装飾品「華鬘(けまん)」に見立てて付けられたとか。 じだ」と。田原氏らは「テレビ局の上層部が萎縮してしまう」と指摘した。しかし特派員から質疑応答が始まると、逆に鋭い質問が会見者側に向けられた、という。
じだ」と。田原氏らは「テレビ局の上層部が萎縮してしまう」と指摘した。しかし特派員から質疑応答が始まると、逆に鋭い質問が会見者側に向けられた、という。




