 新聞社のウエッブニュースを検索すると、盛んに取り上げられている。被告は、イタリアを代表する国立地球物理学火山学研究所の所長(当時)や、記者会見で事実上の「安全宣言」をした政府防災局の副長官(同)で、マグニチュード6.3の地震が発生する直前の「高リスク検討会」に出席した7人。求刑の禁錮4年を上回る重い判決で、執行猶予はついていない。被告側は控訴するという。
新聞社のウエッブニュースを検索すると、盛んに取り上げられている。被告は、イタリアを代表する国立地球物理学火山学研究所の所長(当時)や、記者会見で事実上の「安全宣言」をした政府防災局の副長官(同)で、マグニチュード6.3の地震が発生する直前の「高リスク検討会」に出席した7人。求刑の禁錮4年を上回る重い判決で、執行猶予はついていない。被告側は控訴するという。記事を総合すると話をラクイラ一帯では当時、弱いながらも群発地震が続きており、「大地震」を警告する学者もいた。高リスク検討会の学者らは「大地震がないとは断定できない」としながらも、「群発地震を大地震の予兆とする根拠はない」と議事録に残していた。裁判では、学者側は「行政に科学的な知見を伝えただけだ」と主張、行政当局は「根拠のない『予知』をとめるためだった」などと無罪を訴えた。これに対し、検察は情報提供のあり方を問題視した。政府の防災局は市民の動揺を静めようと3月31日、高リスク検討会の後の記者会見で事実上の「安全宣言」をした。この発表を受けて、屋外避難を取りやめて犠牲になった人もいたという。
学者が「地震が来るかわからない」と言い、行政当局は数ヵ月前から続いていた群発地震による住民の動揺を鎮めるために、それを「安全だ」と発表した。言葉の誤謬が生んだ悲劇か、学者と行政のミスなのか。このニュースを読んで、カトリック教会の異端審問を連想した。ローマなどでは、中世以降のカトリック教会で正統信仰に反する教えを持つ「異端」という疑いを受けた者を裁判するために設けられたシステムだ。地震学者として、行政担当者としてその言葉がふさわしかったか、どうか。科学者を入れた検討会で、その発した言葉が罪になるとすれば、科学者は口をつぐむだろう。こうなると「言葉狩り」になってしまう。
⇒23日(火)朝・金沢の天気 あめ










 キノコ狩りのマニアは、クマとの遭遇を嫌って加賀地方の山々を敬遠する。そこで、クマの出没情報が少ない能登地方の山々へとキノコ狩りの人々の流れが変わってきている。本来、能登地方の人々にとっては迷惑な話なのだが。
キノコ狩りのマニアは、クマとの遭遇を嫌って加賀地方の山々を敬遠する。そこで、クマの出没情報が少ない能登地方の山々へとキノコ狩りの人々の流れが変わってきている。本来、能登地方の人々にとっては迷惑な話なのだが。 ドイツで9月25日から28日にかけて、東部のブランデンブルグ州やザクセン州計5州の学校や幼稚園で園児や小学生1万1千人以上が給食の食材からノロウィルスに感染し、下痢や吐き気などの症状を訴え32人が入院する過去最大規模の食中毒事件が起きた。ドイツ政府がロベルト・コッホ研究所などに委託した調査で、給食に使われた中国産の冷凍イチゴからノロウィルスが検出された。
ドイツで9月25日から28日にかけて、東部のブランデンブルグ州やザクセン州計5州の学校や幼稚園で園児や小学生1万1千人以上が給食の食材からノロウィルスに感染し、下痢や吐き気などの症状を訴え32人が入院する過去最大規模の食中毒事件が起きた。ドイツ政府がロベルト・コッホ研究所などに委託した調査で、給食に使われた中国産の冷凍イチゴからノロウィルスが検出された。 人口1300人ほどの村が一丸となって取り組んだ美しい村づくりとはこんなふうだった。クリ、カシ、ブナなどを利用した「緑のフェンス」(生け垣)が家々にある=写真=。高いもので8mほどにもなる。コンクリートや高層住宅はなく、切妻屋根の伝統的な家屋がほどよい距離を置いて並ぶ。村長のギュンター・シャイドさんが語った。昔は周辺の村でも風除けの生け垣があったが、戦後、人工のフェンスなどに取り替わった。ところが、アイシャーシャイドの村人は先祖から受け継いだその生け垣を律儀に守った。そして、人工フェンスにした家には説得を重ね、苗木を無料で配布して生け垣にしてもらった。景観保全の取り組みは生け垣だけでなく、一度アスファルト舗装にした道路を剥がして、石畳にする工事を進めていた。こうした地道な村ぐるみの運動が実って、見事グランプリに輝いたのだった。
人口1300人ほどの村が一丸となって取り組んだ美しい村づくりとはこんなふうだった。クリ、カシ、ブナなどを利用した「緑のフェンス」(生け垣)が家々にある=写真=。高いもので8mほどにもなる。コンクリートや高層住宅はなく、切妻屋根の伝統的な家屋がほどよい距離を置いて並ぶ。村長のギュンター・シャイドさんが語った。昔は周辺の村でも風除けの生け垣があったが、戦後、人工のフェンスなどに取り替わった。ところが、アイシャーシャイドの村人は先祖から受け継いだその生け垣を律儀に守った。そして、人工フェンスにした家には説得を重ね、苗木を無料で配布して生け垣にしてもらった。景観保全の取り組みは生け垣だけでなく、一度アスファルト舗装にした道路を剥がして、石畳にする工事を進めていた。こうした地道な村ぐるみの運動が実って、見事グランプリに輝いたのだった。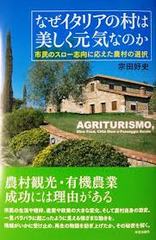 最近読んだ『なぜイタリアの村は美しく元気なのか~市民のスロー志向に応えた農村の選択~』(宗田好史著・学芸出版社)にかかれている状況は、現在の日本のそれと同じだ。イタリアの農業生産はGDPの2.3%、農家は全世帯の3.8%に減った(2009年)。日本は、GDPに占める農業の割合は0.9%だが、農家の全世帯に占める割合は4.5%だ。ただし、農家一戸当たりの耕作面積は日本1.6㌶、イタリア7.9㌶と比較にならないほどイタリアの農家は土地持ちだ。土地面積は少なくとも農業人口の比率はイタリアより多いのでうまく農業経営をやっているとのだと思ってしまうが、日本の場合は農業補助金が現在でも5.5兆円あるので、補助金でなんとか農業人口を支えていると表現した方が良さそうだ。
最近読んだ『なぜイタリアの村は美しく元気なのか~市民のスロー志向に応えた農村の選択~』(宗田好史著・学芸出版社)にかかれている状況は、現在の日本のそれと同じだ。イタリアの農業生産はGDPの2.3%、農家は全世帯の3.8%に減った(2009年)。日本は、GDPに占める農業の割合は0.9%だが、農家の全世帯に占める割合は4.5%だ。ただし、農家一戸当たりの耕作面積は日本1.6㌶、イタリア7.9㌶と比較にならないほどイタリアの農家は土地持ちだ。土地面積は少なくとも農業人口の比率はイタリアより多いのでうまく農業経営をやっているとのだと思ってしまうが、日本の場合は農業補助金が現在でも5.5兆円あるので、補助金でなんとか農業人口を支えていると表現した方が良さそうだ。




