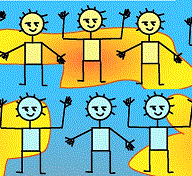
本を探していて、読んだことも忘れていた本が、本棚の奥から出てきた。村上重良の『新宗教 その行動と思想』(岩波現代文庫)である。
読むと、新宗教の開祖、多くは女性だが、すごく不幸な人生を送っていて、そして、ある日、神がかりになって、みんなの病気をなおそうとし、世直しを訴えだしたと、村上は書いている。不幸への怒りが爆発したのだ。そして、字が読め理屈を求める信者が、ほとんど男だが、開祖を助け教義体系を整えていくと、書いている。最後に、その教義を、マルクス主義の立場から、村上は批判していく。
この本には、また、宗教学者の島薗進の解説が載っている。その解説の最後に彼はいう。
〈しかし、村上が新宗教の歴史や教義についてのべた著作を読むと、そうした価値観と新宗教についての叙述がどこか食い違っているように思えることが少なくない。なぜ、新宗教がこれほど人々を魅了したのか、この革新的な問いへの答えが村上の叙述からは見えにくいのもそのためだろう。〉
村上重良の本は、最初、評論社から1980年に出版された。本人は1991年に死んでいる。
この後、オウムによる地下鉄サリン事件が1995年に起きた。
そして、2001年に、島薗進は『ポストモダンの新宗教 現代日本の精神状況の底流』(東京堂出版)を出版している。
島薗は、オウムの事件で、自分の見落としていたものに気づいたのだろう。彼は、「新新宗教」という言葉を作り、幕末から戦前までの新興宗教を「新宗教」とし、戦後の新興宗教を「新新宗教」と便宜的に呼んでいる。オウムで気づいたのは宗教のもつ凶暴性だろう。
ふりかえって、「新宗教がこれほど人々を魅了したのか」の答えは、不幸な人に寄り添う優しさであると私は思う。上からではなく、不幸を体験したものどうしが、たがいに寄り添う優しさである。それは、弱者からなる「共同体」といっても良いかもしれない。
村上は、この不幸な人たちが政治に目覚めず、神がかりになるほどの怒りをもちながら、社会変革の力とならなかったことに、いらだっていたと思う。そして、新宗教の教義の批判に向かった。
オウムの事件で島薗進が見出した凶暴性は、呪術的なものにのめりこむことが、「世なおし」が無理なら、「呪術」が無理なら、「終末が来ない」なら、「世界を破滅させるしかない」となる可能性であろう。
現在なお、病気や貧乏などの不幸をおっている人々が厳然と存在しており、いっぽう、勝ち組が「近代合理主義」者と自称し、格差を正当化している。その勝ち組でさえ、負け組に陥ることを心の奥で心配している。このような状況下では、ちょっとしたきっかけで、「世なおし」が無理なら「世界が破滅すれば良い」となる可能性がある。
「世なおし」は、幸福になることへの願いだが、「世界の破滅」は、みんなが不幸になればよいという怒りである。
私は、呪術的なものに頼る宗教には賛同できない。私の母は日蓮宗で、生前に頼まれたとおり、身延山の寺に分骨した。その寺のパンフレットに、お祈りをしてもらうと病気が治るなどの「ご利益」が書かれていた。母はこのことを知っていたのだろうか。
旧来の宗教も新宗教も新新宗教も、非合理的な力に頼ることには、賛同できない。
しかし、教義をいくら批判しても、しかたがない。宗教にはまる人は、不幸に疲れ果てて、慰めを求めているのだ。決して、教義に賛同してでない。
政治的な社会変革運動は、上からではなく、対等なものどうしの、寄り添う優しさをもたないといけない。誰かが不幸なままに放置されることがあってはならない。弱いものは集まって、助け合わないといけない。
[補遺]
書いた後で気づいたのだが、宗教の疑似共同体がもつ排他性についての論点が落ちていた。島薗進の本が手元にないので、この点についての彼の議論がわからない。共同体は一般に内側に優しい顔を向けるが、その外に対しては攻撃的になる。









