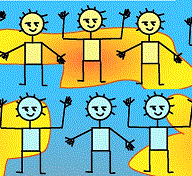ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の第5編に「大審問官」という章がある。
「大審問官」とは、異端者を裁き、火焙(ひあぶ)りの刑に処するカトリックの枢機卿のことである。
この章で、末の弟アリョーシャに、兄のイワンが、自分の作った物語詩、人間の姿で再び現れたイエスと大審問官との物語を語る。
イワンの物語詩はこうである。
またやってくると約束してから1500年後、人々の願いをあわれに思って、異端者を火焙りにしたばかりのセヴィリアの石畳の広場に、人間の姿で、彼がふたたびあらわれた。
奇跡を求め、多数の群衆が、取り囲む中を、彼は無言で石畳を歩く。
通りかかった90歳の大審問官は、彼が、めくらをなおし、死んだ娘を生き返らすのを見て、顔を曇らせ、捕らえるよう、部下に命ずる。
おとなしくするよう仕込まれた群衆は、恐れおののき、道を開ける。
牢に閉じ込め、その夜、大審問官は、ひとりで彼を訪れる。
「で、おまえがあれなのか?あれなのか?」
「なぜ、われわれの邪魔をしにきた?」
「最悪の異端者として、火焙りにしてやる」
大審問官はひとり長々とののしる。
突然、大審問官は、その男に口づけされ、牢の扉を開き、夜の街の闇に彼を解き放つ。
この自分の物語詩の合間に、23歳の兄のイワンは、修道院から戻った19歳のアリョーシャに執拗に議論を吹きかける。
何年か前に読んだときは、この章がわかったような気がしたが、いま、もう一度読むと、まったくわからない。
年のせいだろうか。
もともと意味のないことをドストエフキーは書いているだけなのか。
あるいは、
シベリア送りを経験しているドストエフスキーは、わざと意図がわからないように書いているのだろうか。
それとも、人間の思いは、もともと、複雑で錯綜したものだからか、わかるはずがないのか。
とにかく、いま、自分がわかっていないということが、わかった。
もうひとつ、いま、わかったことがある。
イワンには、アリョーシャが、可愛くて、可愛くて、たまらないのだ。
アリョーシャが人間のこころの複雑で錯綜していることに気づかないから、イワンには可愛いのだ。
ゾシマ長老がアリョーシャにいだいた思いと同じだ。
この可愛さは、はかなく消えゆくものを前にした哀れみなのか。
ゾシマ長老は死んで腐臭を発した。
それは単に現実にすぎない。別にあたりまえのことだ。
現実に気づいても、精神的なものは、変わらぬものでなければ、意味がない。