
とはいえ、もし母が「生きる気満々」ならば私も頑張るしかないし、よその施設で見放された母を受け入れてくれた我が職場にも恩返しをしたい。
つまり自分の老後なんかよりも「いま、自分が倒れない為に」どうすべきかを考えるのが何より大事。
というワケで先日から読んでるのが工藤孝文監修&ホームライフ取材班編による新書『“ストレスに負けない人”の習慣、ぜんぶ集めました。』
最近の私がズタボロになってるのは、母に関する心配事もさることながら、人一倍ストレスに弱いくせにストレスフルな仕事をしてるのも大きな原因で、それが持病の腎臓結石を悪化させたのも間違いない。食習慣はかなり改めたけど、ストレスに対する耐性をもっと上げなきゃ再発は免れない。
かと言って自己啓発とかスピリチュアル系の訓示に従う気にはなれず、もっと現実的なデータに基づくストレス軽減(あるいは回避)法を、具体的に知りたい。今こそ知らなきゃいけない!
……って、ハリソン君という名の神(潜在意識下の私)が導いたんでしょう。たまたま書店でこの本を見つけ、即買いしました。要するに「直感」で足を運んでた。そういうのこそ「スピリチュアル」と呼ぶのかも知れないけど。
第一章である「ストレスに負けない人の“考え方の習慣”」の主な項目をザッと挙げていくと、「心配ごとの97%は起こらない」「自分では変えられないことを考えても無駄」「無理なことは“できない”ではなく“やらない”と言う」「“もうダメだ”ではなく“なんとかなる”と思う人は打たれ強い」「ストレスに強い人は、みんなから好かれなくても平気」「“想定内”を大きくかまえる人は、突発的な出来事に右往左往しない」等々……
どれもこれも「いつぞや誰かが言ってたこと」のような気がするし「それくらい分かってるけどさ」と言いたくもなるけど、この本はそれらのストレス軽減法がなぜ有効なのかを、具体的な実験・研究結果を示しつつ簡潔に(各項目1ページか2ページで)教えてくれます。
この「ストレスに負けない“考え方”」の章で私が一番ハッとさせられたのが、「“〜すべき”という考え方を変えると、それだけでストレスが軽くなっていく」という項目と「“まあ、いいか”と声に出して、気持ちをさっと切り替える人を見習う」という項目。
“〜すべき”っていうポリシーを強く持つ人はストレスを溜めやすい上、周りの人にもそれを求める傾向があり、面倒くさいヤツだと煙たがられて結局またストレスを増やしていく。関係者でもないのに誹謗中傷をネットに書き込む連中はその典型でしょう。
他人が自分のポリシーに反する言動をしても、自分は自分、他人は他人と割り切れる人は確かにストレスを溜めないだろうと思います。
私は最近、職場で同僚どうしの挨拶をおざなりにする人、最悪の場合は無視する人が何人もいて、「こんな職場は初めてだ!💢」と主任の前でぶちギレるという、かなり恥ずかしいことをやらかしました。
みんな疲れてるのはよく解るけど、だからこそ挨拶ぐらいは気持ちよくやろうよって、ずっと前から溜めてたマグマがふとした拍子に爆発したワケです。
そのポリシー自体は今でも正しいと思うけど、挨拶するのがニガテな人や、私という人間を好ましく思ってない人に挨拶を強要したところでストレス解消には繋がらない。
だったら最初から「まあ、いいか」って、「他人は他人で変えようが無いし」って割り切った方が絶対ラク。それぐらい分かってた筈なのに、普段から意識しないと忘れてしまう。
ちなみに記事タイトルの「オーウェル思考」を日本語に訳したのが「まあ、いいか」で、その逆にあたる「〜すべき」が「マスト思考」。そりゃストレス溜まるわと反省しました。
上に書いた事案はほんの一例で、分かってた筈なのに忘れてるストレスの素は、他にも多々ありそう。
第ニ章以降は「ストレスに負けない人の“溜めない習慣”」「逃れる習慣」「脳をだます習慣」「仕事の習慣」「心と体を休める習慣」「毎日を楽しむ習慣」「食べ方の習慣」「体を動かす習慣」「心と体をじわじわ蝕むストレスな習慣」と続いていきます。
私と同じように「分かってたけど忘れてる」人は読者さんの中にもきっと沢山おられるでしょうから、またハッとさせられる項目があれば記事にしたいと思ってます。










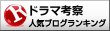







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます