まず、良い音で録音するには、LPの掃除から始めます。
きちんと保存してある方は必要ないと思いますが、私のように長期にわたって押入れに放り込んであった人は、カビが発生していることもあり得ます。一寸吹いた程度ではとても落とせず、かといって市販のカビ取りではレコードを傷めてしまう危険性もあります。
そこで私のやり方を紹介します。かなり過激なやり方のようにも見えますが、効果はかなり有りますし、レコードを傷つけるリスクもほとんど無いと思います。但しあくまで自己責任でお願いします。
<準備するもの>
以下の写真に示す木工用ボンドだけです。(もちろん、きれいにしたいレコードも)
ここでのポイントは、買ってきた木工用ボンド(写真のサイズで200円くらい)を水で二倍に希釈しておくことです。

<掃除の手順>
1.きれいにしたいレコード面に木工用ボンドを塗ります。量は以下の写真を参照
(量はあまり気にしなくても良いですが、少な過ぎると全体に塗れず追加しなければならなくなるので、多すぎるくらいの方が良いでしょう)

2.指先でレコードの溝にボンドを摺りこみながら、全体にボンドを広げて行きます。特にカビ等の発生している部位はしつこく刷り込みます。レコードを傷付けないようにあくまで指の腹でこすり付けましょう。ボンドそのものは水溶性なので、後で簡単に洗えますので心配無用です。

3.この後は乾燥を待ちます。ボンドは乾燥すると透明になるので全体白い色が完全になくなるまで、待ちます。今の季節であれば2~3時間程度でしょうか。以下の写真は1時間ほど経過した状態です。6割くらい乾いた状態です。

4.乾いたボンドをはがしますが、間違っても爪とか針・カッターとか、そういうものは一切使いません。指や爪ではまずはがせませんし、カッターなど使ったら貴重なレコードがパアです。
コツは以下の写真に示すように、セロハンテープを使うことです。しかも内側から外側に向かって真上ではなく、外周に向かって寝かすように引っ張ります。(内側の方がボンドが薄くなっており、はがれやすい)

5.一箇所はがれれば、あとは簡単に剥がせると思います。万一剥がし残りが出た場合はセロハンテープで丁寧に取ってください。(慣れると一発で完璧に剥がせるようになります)

<デジタル化の方法>
最近はUSBから入力するツール等、色々と市販されてますが、私の場合は普通のPC音源とフリーソフトを用いて、金を掛けずにデジタル化してます。
もちろん絶対必要なのはLPレコードプレイヤーです。私も20年前のLPプレイヤーを捨てずに取って置いたのですが、ベルトドライブのタイプだったため、ベルトのゴムが溶けてしまって全く使いものになりませんでした。
今でもテクニクスのSL1200という超ロングセラーのダイレクトドライブプレイヤーが市販されてますが、4万円以上もするのであきらめました。
また普通のレコードプレイヤーには、イコイライザーアンプ(Phono入力のあるアンプ)も必要になります。そんなとき(今から5年ほど前)、以下の写真にあるLPプレイヤーを発見しました。KENWOOD製のプレイヤーで、イコイライザーアンプ内臓、サイズも30cmLPより小さくコンパクト、価格も5000円程度でした。但し、カートリッジは専用タイプ、アームもプラスチックの貧弱なもので、まともな音が出るのか心配でしたが、以外に音質は良いと思ってます。
以下、そのプレイヤーの写真です。



このプレイヤーの出力コード(赤と白のピンプラグ)をPCの音源ボードの入力端子に接続すれば準備完了です。
次にPC側の準備です。市販のソフトも色々ありますが、私はフリーソフトで有名なSoundEngine Free ver.2.945を使用してます。

このソフトは録音ピーク音量を自動で設定(揃える)できる等、使い勝手が良く考えられており、気に入ってます。
SoundEngine
もう一つ便利なソフトを紹介します。上記のSoundEngineで取り込むと、LPの片面全部が一つの曲となり、なんとも間が抜けた形になってしまいます。クラッシック曲等はこれで問題ないのですが、ポップス等、1曲毎に曲名を付け、切り離したくなりますが、そんな時便利なのが WaveZ というソフトです。一定のレベル(閾値)を設定すると、そのレベル以下を無音と判定し、そこを曲の切れ目として全自動で分離してくれるソフトです。WaveZ
きちんと保存してある方は必要ないと思いますが、私のように長期にわたって押入れに放り込んであった人は、カビが発生していることもあり得ます。一寸吹いた程度ではとても落とせず、かといって市販のカビ取りではレコードを傷めてしまう危険性もあります。
そこで私のやり方を紹介します。かなり過激なやり方のようにも見えますが、効果はかなり有りますし、レコードを傷つけるリスクもほとんど無いと思います。但しあくまで自己責任でお願いします。
<準備するもの>
以下の写真に示す木工用ボンドだけです。(もちろん、きれいにしたいレコードも)
ここでのポイントは、買ってきた木工用ボンド(写真のサイズで200円くらい)を水で二倍に希釈しておくことです。

<掃除の手順>
1.きれいにしたいレコード面に木工用ボンドを塗ります。量は以下の写真を参照
(量はあまり気にしなくても良いですが、少な過ぎると全体に塗れず追加しなければならなくなるので、多すぎるくらいの方が良いでしょう)

2.指先でレコードの溝にボンドを摺りこみながら、全体にボンドを広げて行きます。特にカビ等の発生している部位はしつこく刷り込みます。レコードを傷付けないようにあくまで指の腹でこすり付けましょう。ボンドそのものは水溶性なので、後で簡単に洗えますので心配無用です。

3.この後は乾燥を待ちます。ボンドは乾燥すると透明になるので全体白い色が完全になくなるまで、待ちます。今の季節であれば2~3時間程度でしょうか。以下の写真は1時間ほど経過した状態です。6割くらい乾いた状態です。

4.乾いたボンドをはがしますが、間違っても爪とか針・カッターとか、そういうものは一切使いません。指や爪ではまずはがせませんし、カッターなど使ったら貴重なレコードがパアです。
コツは以下の写真に示すように、セロハンテープを使うことです。しかも内側から外側に向かって真上ではなく、外周に向かって寝かすように引っ張ります。(内側の方がボンドが薄くなっており、はがれやすい)

5.一箇所はがれれば、あとは簡単に剥がせると思います。万一剥がし残りが出た場合はセロハンテープで丁寧に取ってください。(慣れると一発で完璧に剥がせるようになります)

<デジタル化の方法>
最近はUSBから入力するツール等、色々と市販されてますが、私の場合は普通のPC音源とフリーソフトを用いて、金を掛けずにデジタル化してます。
もちろん絶対必要なのはLPレコードプレイヤーです。私も20年前のLPプレイヤーを捨てずに取って置いたのですが、ベルトドライブのタイプだったため、ベルトのゴムが溶けてしまって全く使いものになりませんでした。
今でもテクニクスのSL1200という超ロングセラーのダイレクトドライブプレイヤーが市販されてますが、4万円以上もするのであきらめました。
また普通のレコードプレイヤーには、イコイライザーアンプ(Phono入力のあるアンプ)も必要になります。そんなとき(今から5年ほど前)、以下の写真にあるLPプレイヤーを発見しました。KENWOOD製のプレイヤーで、イコイライザーアンプ内臓、サイズも30cmLPより小さくコンパクト、価格も5000円程度でした。但し、カートリッジは専用タイプ、アームもプラスチックの貧弱なもので、まともな音が出るのか心配でしたが、以外に音質は良いと思ってます。
以下、そのプレイヤーの写真です。



このプレイヤーの出力コード(赤と白のピンプラグ)をPCの音源ボードの入力端子に接続すれば準備完了です。
次にPC側の準備です。市販のソフトも色々ありますが、私はフリーソフトで有名なSoundEngine Free ver.2.945を使用してます。

このソフトは録音ピーク音量を自動で設定(揃える)できる等、使い勝手が良く考えられており、気に入ってます。
SoundEngine
もう一つ便利なソフトを紹介します。上記のSoundEngineで取り込むと、LPの片面全部が一つの曲となり、なんとも間が抜けた形になってしまいます。クラッシック曲等はこれで問題ないのですが、ポップス等、1曲毎に曲名を付け、切り離したくなりますが、そんな時便利なのが WaveZ というソフトです。一定のレベル(閾値)を設定すると、そのレベル以下を無音と判定し、そこを曲の切れ目として全自動で分離してくれるソフトです。WaveZ










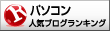

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます