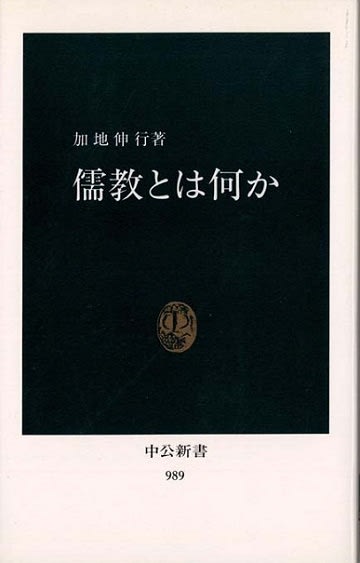
2011-12-20 12:27:41
儒教とは何か? 『儒教とは何か』(中公新書・1990年10月)の著者の加地伸行・大阪大学名誉教授(同志社大学フェロー)はこう述べられる。「儒は、招魂儀礼という古今東西に存在する呪術を生命論に構成し、死の恐怖や不安を解消する説明を行うことに成功した」(同書p.21)、「世界共通のこの招魂儀礼を基礎にして、一大理論体系を作っていったのである」(同書p.19)、「生命論としての孝を基礎として、後の儒教はその上に家族倫理(家族理論)を作り、さらにその上に、社会倫理(政治理論)を作ったのである。後世になり十二世紀の新儒教になると、さらにその上に宇宙論・形而上学まで作るようになった」(同書pp.21-22)、と。
儒教は日本人に執拗につきまとってくる問題である。なぜか? 恐らくそれは、長い歴史の中で、さらに、加地先生の言葉を借りれば同じ「東北アジア人」たる日本人の世界観や感性と共鳴することによって、儒教は言わば<レトロウィルス的>に作用して、最早、日本人の精神構造の一部になっているからだと私は考える。
而して、日本的な世界観とこの後天的に獲得された儒教的な世界観の間の軋轢は(それはいわば、儒教の更なる日本化のプロセスに他ならないけれど)、現在も続いており;明治維新や大東亜戦争後の占領期等の変革期には社会思想の主要なテーマとして意識されてきたのではないか。蓋し、21世紀初頭の日本でも社会の構造改革と戦後を支配した空想的平和論からの脱却の動きの中で儒教は再び思想のメインテーマになりつつある。私にはそう思われる。

◆本書の概要
本書の中核は「儒教は宗教である」という主張に尽きると思う。「はじめに――葬式と儒教と」から「序章 儒教における死」「第一章 儒教の宗教性」「第二章 儒教文化圏」および「第三章 儒教の成立」の第5節にいたるまで(更には、終章「儒教と現代」をも含めて、それは本書の三分の一を占めている)、これすべてこの主張の敷衍であると言っても過言ではない。私なりに著者の主張をパラフレーズすれば、儒教は宗教であり;宗教という最も人間精神の根源的な部面にコミットしているからこそ儒教は東北アジア人に対して広く深く、かつ、長きに渡って影響を及ぼしてきた、と。
著者は「儒教の宗教性」を基底に据えた上で、儒教を「宗教性」と「礼教性」の重層的な思想の統一体として理解する(同書p.21, p.76, p.214の図版参照)。私なりに要約すれば;現在、大なり小なり東北アジアの儒教文化圏でも社会規範や国家の制度の基盤としての「儒教の礼教性」は崩壊しつつある:けれども、「儒教の宗教性」はしたたかに生き残っている:否、欧米流の思想から自己のアイデンティティを護る防波堤として「儒教の宗教性」は、ある意味、強化され向自化される(自分と関係あるものとして明確に意識される)傾向さえある、と。これが著者の現在の東アジアにおける儒教文化圏認識ではないかと思う。
儒教の原点としての「宗教性」、そして、「宗教性」と「礼教性」の統一体としての儒教理解。この強固なフレームを打ち立てた後、著者は、言わば<思想の増改築のダイナミックス>として儒教思想の発展を捉えられる。而して、その説明が通史的記述を通して読者に与えられる。それは(一)原儒時代、(二)儒教成立時代、(三)経学時代、(四)儒教の内面化時代(同書p.50)による時代区分である。蓋し、本書は<宗教としての儒教>を縦糸に<宗教と礼教の統一体たる儒教の絶えざる発展運動>という歴史的経緯を横糸にして、(もちろん、簡単ではないが)明晰かつ論理的に編み上げられた儒教入門である。
◆本書が書かれた背景と著者の意図
本書は、所謂<儒教文化圏論>がホットイシューであった1990年、当時、経済発展著しいAsia NIES(亜細亜新工業地域・国家)に世界の関心が集まる中で上梓された。日本を除いて、共産主義独裁か開発独裁の形態でしか東アジアの人々は国家を運営できず、まして、マックス・ウェーバーの語る合理的で禁欲的なエートスに基盤を置く資本主義を日本以外の東アジア諸国は実現できないという大方の予想に反して、韓国・台湾・香港・新嘉坡が目覚しい経済発展を達成していることに世界が注目する中で本書は登場したのである。
それから幾星霜。韓国がIMF管理下に置かれるなど1997-1998年に顕在化したアジア経済の失速や日本の失われた90年代を経て、現下の中国のほとんどバブル終末期の様相を呈する経済発展と小泉構造改革による我が日本経済の回復;そして、国際法や確立した国際慣行を真っ向から否定する中韓朝の特定アジア三国の中華思想への嫌悪の高まりの中で中華思想の基盤でもある儒教(≒朱子学)への関心も再び高まっている。けれども、本書はそのような国際政治や経済の有為転変とは関係なく読まれ続けてきた。実際、昨日、地元新百合ヶ丘のある書肆で確認した所、2005年3月15日段階で本書は22版を重ねている。専門書研究書ではないにせよ硬派の書籍としては本書は破格のベストセラーなのである。
加地先生は本書執筆の抱負と意図をこう述べられている。「独自の儒教論を構成しつつ中国哲学史を全体として把握する仕事は絶ちがたい魅力あるものであった。ひとたび学を志した以上、こうした無謀な挑戦を望まない者があるであろうか。私は開き直って猛勉強した。(中略)目的はただ一つ――儒教の単なる事実の歴史を書くのではなくて、なぜそうなったのか、その理由を解析して有機的に体系的に儒教を論ずることであった」(同書p.266)、と。蓋し、この意図は本書『儒教とは何か』に美しく結晶したと私は思う。
畢竟、本書は儒教の全体像を掴みそのエッセンスを理解するためには最高の一書である。私のような素人が言うまでもないが、その評価も定まっていると思う。もちろん、<儒>の原初的な形態やそれを受け継いだ孔子以下の儒家の生活や活動を理解するためには(加地先生ご自身が「日本が世界の学界に誇る成果」(同書p.38)と絶賛されている通り)、白川静先生の研究;一般書としては『孔子伝』(中公文庫・1991年1月、初版は1972年11月)に優るものはないかもしれない。それは、老荘に始まる道教をして、実は、孔子最晩年の思想の嫡出子であることを示された白川先生のアイデアの卓抜さについても言えると思う。しかし、儒教思想を通史の形で提示する一般読者を対象とした書籍を私は本書以外に寡聞にして知らない。
◆本書の守備範囲と私家版覚書
本書にも、しかし、限界はある。それは、孟子から朱子学に至る経学時代の説明(本書第四章と第五章「経学の時代」)が手薄という技術的なポイントだけではなく、もっと現実的なものである。
例えば、特定アジア三国が振りかざす中華思想をどう我々日本人は理解し対処すればよいのか。あるいは、同じく儒教の影響を受けている我が神州の政治思想と社会思想は彼等特定アジアのそれとどう異なるのか/なぜ異なるのか;なぜに、日本では仏教が栄え現在に至っているのに特定アジアでは仏教は衰退したのか:なぜに、日本では欧米の法制度の継受が成功したのに特定アジアでは現在に至るまで「法の何たるか」が理解されないでいるのか。そして、我が神州は日本の独自性をどう理解して、欧米が作り上げてきた政治思想や社会思想または実定国際法や確立した国際慣習といかに折り合いをつけていけばよいのか。これら現実具体的な問題を考える際に本書はそう使い勝手のよいものではない。
しかし、大急ぎで言い足しておくけれど、『儒教とは何か』は上で述べた現実具体的な問題を考えるためにも有効である。少なくとも問題のパースペクティブを獲得するためには本書は秀逸である。この経緯は、カーライルが談じたように「太陽が葉巻に火をつけるのに直接役立たないからと言って、太陽が無用なものだと考える人はそう多くはないだろう」ということに近い。蓋し、これは、一冊の書物や一人の政治家や思想家に余り多くを期待すべきではないという真理の適例でもあろう。
では、本書をベースキャンプとして儒教を考える時、どんな問題が日本人に課されているだろうか。私家版の覚書のつもりで2点記しておく。
(甲)日本の法制度と法意識の柔構造
律令の(その法体系内の例外と追加規定である格式を含む)法体系は明治維新直後まで法的拘束力を持っていた;武家諸法度等の武家法と地域の法と律令とは共存し協働していた。近年明らかになっているこの事実を鑑みる時、日本法のこの柔構造は、コモンローとエクイティの協働によって極めて合理的で合道理的とも言うべき法体系を発展させてきた英米法との共通性を感じさせないだろうか。あるいは、ローマ法を継受しながらも古来のゲルマン法と融合させつつ自生的な秩序を構築したドイツ法との類似性をも見出せるのではないか。ならば、明治維新と大東亜戦争後に欧米の法制度の継受に成功した日本と未だに「法の何たるか」が理解できないでいる特定アジア諸国との彼我の差はこの重層的な法の柔構造に起因するのかもしれない。
(乙)家制度を貫く日本のあの世観
福翁(=福沢諭吉)は「封建制度(門閥制度)は親の仇」と述べたというが、島崎藤村の『夜明け前』を紐解くまでもなく、また、大東亜戦争後の民法の親族・相続編(民法第4編と5編)の改正においても<家>は日本の封建遺制と考えられ儒教と結び付けられてきた。
しかし、夫婦別姓論議を通してこれまた世間の常識になったことであるけれど、本来の儒教の教えに従えば、「氏族本貫を異にする夫婦は別姓であるべき」なのであり、血の連続に価値を置く儒教から見れば、DNAを異にする異姓の養子を向かえ<家>を維持するなどは(実際、江戸期の商家には、DNAのつながる息子は他家に出した上で、代々、一番優秀な使用人を養子に向かえ新当主にする慣行を持つところさえ珍しくなかった)、儒教的にはトンデモな事態である。では、なぜに、このような儒教の日本的変容が(=それは氏族やDNAからの<家>の分離であろうが)起きたのか?
私は、そこに日本人特有の<あの世観>と<現世-来世観>が与して力あったと考えている。梅原猛『日本人の魂 あの世を観る』などの通俗書にも紹介されている日本人特有のあの世観のことである;それは、儒教式の「死者が抽象的な魂魄として、しかも、死後も個性を失わずこの世を浮遊放浪しているイメージ」ではなく、あの世もこの世もほとんど同じ、かつ、双方が相互に関係している具体的な世界であり、また、死者は個性を徐々に失い祖霊集合に吸収されるあの世観である。この日本的なあの世観からは、この世とあの世の繁栄の基軸たる<家組織>の価値が当主のDNAの連続を守ることよりも上に置かれることはそう不思議ではないし、逆に、<家たる神州>の一体性と連続性を皇孫DNAの連続の姿を取りながらも象徴するパラドクスを理解することも可能ではないだろうか。
尚、中華思想、および、支那の国家論、就中、現下の支那の社会思想の変容に関する
私の基本的認識に関しては下記拙稿をご参照いただければ嬉しいです。
また、本書『儒教とは何か』の核心というべきメッセージ、
すなわち、「儒教の宗教性=<死>の取り扱い説明の体系」の点に関しては、
下記の再後者が参考になると思います。
・<中国>という現象☆中華主義とナショナリズム(上)(下)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11153763008.html
・「偏狭なるナショナリズム」なるものの唯一可能な批判根拠(1)~(6)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11146780998.html
・元キャンディーのスーちゃんのメッセージに結晶する<神学>と<哲学>の交点
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/ef7b986c941c707ebf1cf53fd9698da7

木花咲耶姫
・ほしのあきさんの<無罪>確定-あんだけ可愛いんだから当然なのです
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/78478ca7d4aebc00f057beebd43f17a4




















日本人は、「漢文」を学校で習ったので論語が立派な道徳であると刷り込まれている節があるようです。
それにしては、最近の中国や朝鮮の理不尽なふるまいを不審に思っていました。
どうも儒教は、いろいろと問題がある考えのようです。