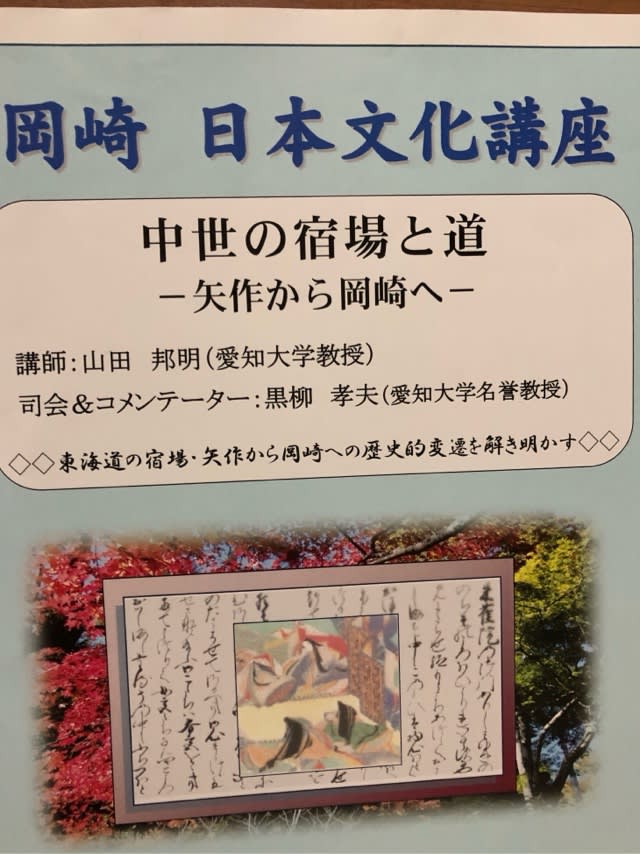
先日、岡崎市図書館りぶらで開かれた岡崎日本文化講座に出席しました。

今回は、愛知大学の山田邦明教授が講師となり、「中世の宿場と道ー矢作から岡崎へー」と題した講義でした。
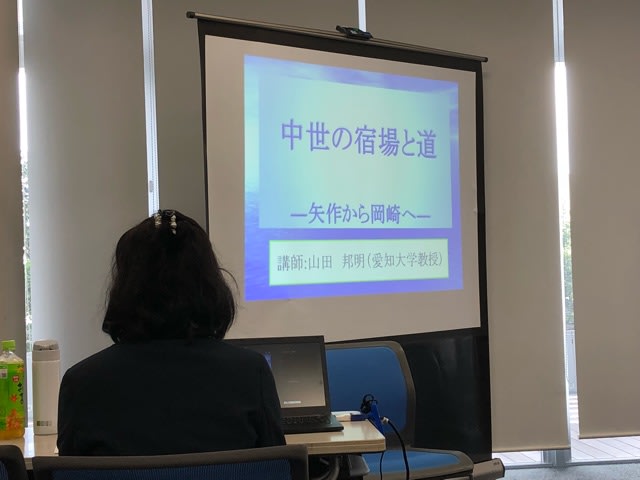
はじめに奈良時代に東海道が整備され、三河国には3つの駅がおかれました。その中に当地にも駅があり、矢作川には渡船が置かれてました。鎌倉時代に入り、東海道を行き来する旅人が、矢作宿に泊まる様子が色々な古文書に登場します。次に、戦国時代に入り松平氏が三河を治める頃から矢作から岡崎に中心が移ります。講義は、この推移について話されました。地元の歴史がよくわかりました。










