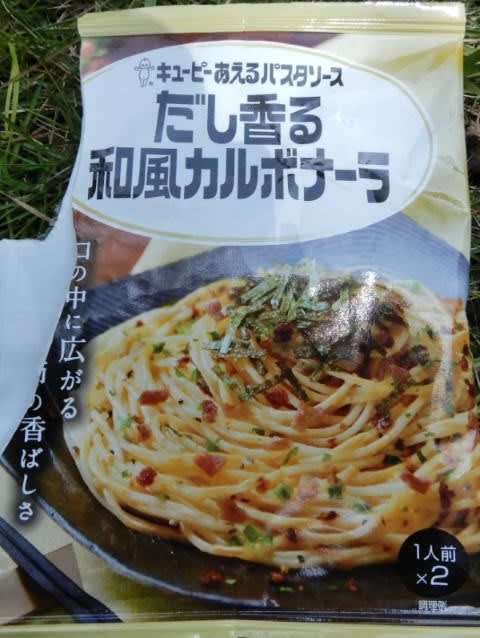田圃脇の水路に居たコシアキトンボ(腰空蜻蛉)。

水辺にはアメンボ(飴坊、水黽、水馬)。
カメムシ目アメンボ科で、飴のような匂いがする事が名前の由来、体長約15mm。
昔は水溜りにも居ましたが、最近あまり見ないような。

カメムシ目アメンボ科で、飴のような匂いがする事が名前の由来、体長約15mm。
昔は水溜りにも居ましたが、最近あまり見ないような。

水田にサギが居ましたが、もしかしてアマサギ?

大、中、小サギの幼鳥かも知れません、なにしろアマサギを見た事が無いので。

こちらは成鳥のダイサギですね、これの幼鳥でしょうか。
ダイサギの幼鳥は、首や頭がオレンジ色になるのかな?

ダイサギの幼鳥は、首や頭がオレンジ色になるのかな?

アマサギは繁殖期に頭、胸、背中が薄いオレンジ色になるようです。
でも↓のボサボサ頭を見ると、幼鳥のような気もします。

でも↓のボサボサ頭を見ると、幼鳥のような気もします。

アマサギなのか、他のサギの幼鳥なのか・・・、アマサギだとしたら初見初撮りになります。


暫く撮っていたら突然飛び立ちました。
辛うじて捉えましたが、ピントは合ってません。(^^;)
田園地帯でサギを撮り、目指すは薄暗い林下に咲く花。

辛うじて捉えましたが、ピントは合ってません。(^^;)
田園地帯でサギを撮り、目指すは薄暗い林下に咲く花。

目的地到着、しかし目当ての花を探すも見付かりません。
例年ここに沢山咲くはずなのですが・・・。
周辺を探し、なんとか二株見付けました、それはタシロラン(田代蘭)です。

例年ここに沢山咲くはずなのですが・・・。
周辺を探し、なんとか二株見付けました、それはタシロラン(田代蘭)です。

ラン科トラキチラン属の多年草で、葉緑素の無い腐生植物、関東以西~沖縄に分布。
花が下を向き、あまり開かないので花の中が撮れません。

花が下を向き、あまり開かないので花の中が撮れません。

環境省の準絶滅危惧指定種、愛知県でも準絶滅危惧指定。

名前の由来は、発見者の田代善太郎の名前からだそうです。
2株しかなかったので、あちこちから撮り方を変えて撮ってます。(^^;)

2株しかなかったので、あちこちから撮り方を変えて撮ってます。(^^;)

一応目的の花が撮れました、帰りがけにアゲハチョウでもと思うも居ませんね。
どうにか見付けたのは、お馴染みのツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)のみ。

どうにか見付けたのは、お馴染みのツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)のみ。

この蝶は割りにとまってくれるので助かります。

翅の縁が黒いので♀です。

とかくする内に7月も中旬に入りましたが、まだ暫く梅雨は明けそうもないですね。