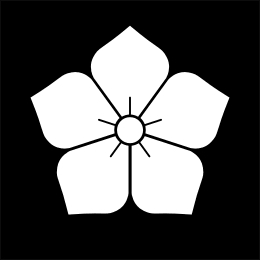心根の腐った人や根性の悪い人のことを「意地が悪い」、
自分の思うことを無理やり押し通すことを「意地を通す」、
物品をむやみにほしがったり、
食べ物にひどく執着する人を「意地汚い」とか「食い意地が張っている」と、
とかく負のイメージがつきまとう「意地」という言葉ですね。
でも、ある一面では、特にスポーツの世界や教育の価値観などには、
がんばる心、とか、強い心、根性、心意気、誇りといった
プラスのイメージで使われたりもします。
「あなたはもう少し意地を見せなさい」、
と、小学生の頃よく先生に言われていたのを想い出します。(^^;)
んで、私は、「僕の辞書には意地という言葉はありません。」と、
心の中でつぶやいておりました。面と向かって言えないところも意気地無し、です。^^;
お話が脱線しました。
「心」をとらえ、そしてそれをコントロールしていくこと、
すなわち心を整えていくという作業は、
これ、仏教のメインテーマですね。
すでに述べました「おこない」と「言葉」も、
心と不可分の関係です。
「身心一如(シンシンイチニョ)」といいますように、
からだと心は別々のものではありません。
だから、これらは全部一セットとしてみるべきです。
具体的には、「身心を静寂にすること」と、
「心の観察」という二種類のとりくみが説かれます。
身心の静寂は、座禅など代表的な方法ですよね。
心の観察は、自分自身を極めて客観的に眺める訓練です。
この心の動揺は何が原因なんだろうか?
どんな手順で今のざわめきに繋がっているんだろうか?
ゆってみれば、動揺そのものに左右されることなく、
その全体像を俯瞰的にみすえ、今の状態にあらためて「気付く」作業です。
なんだか、小難しい話になってしまいましたが、
話すテーマに対して、話し手の力量が小さすぎると、
表現が難しくなったり漢字が増えたりするものだ、
・・・ということを、今まさに、「気付」かされました。
自分の思うことを無理やり押し通すことを「意地を通す」、
物品をむやみにほしがったり、
食べ物にひどく執着する人を「意地汚い」とか「食い意地が張っている」と、
とかく負のイメージがつきまとう「意地」という言葉ですね。
でも、ある一面では、特にスポーツの世界や教育の価値観などには、
がんばる心、とか、強い心、根性、心意気、誇りといった
プラスのイメージで使われたりもします。
「あなたはもう少し意地を見せなさい」、
と、小学生の頃よく先生に言われていたのを想い出します。(^^;)
んで、私は、「僕の辞書には意地という言葉はありません。」と、
心の中でつぶやいておりました。面と向かって言えないところも意気地無し、です。^^;
お話が脱線しました。
「心」をとらえ、そしてそれをコントロールしていくこと、
すなわち心を整えていくという作業は、
これ、仏教のメインテーマですね。
すでに述べました「おこない」と「言葉」も、
心と不可分の関係です。
「身心一如(シンシンイチニョ)」といいますように、
からだと心は別々のものではありません。
だから、これらは全部一セットとしてみるべきです。
具体的には、「身心を静寂にすること」と、
「心の観察」という二種類のとりくみが説かれます。
身心の静寂は、座禅など代表的な方法ですよね。
心の観察は、自分自身を極めて客観的に眺める訓練です。
この心の動揺は何が原因なんだろうか?
どんな手順で今のざわめきに繋がっているんだろうか?
ゆってみれば、動揺そのものに左右されることなく、
その全体像を俯瞰的にみすえ、今の状態にあらためて「気付く」作業です。
なんだか、小難しい話になってしまいましたが、
話すテーマに対して、話し手の力量が小さすぎると、
表現が難しくなったり漢字が増えたりするものだ、
・・・ということを、今まさに、「気付」かされました。