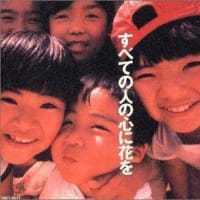今年も日本の研究者がイグノーベル賞を受賞しました。
ノーベル賞ではなく、イグノーベル賞の方の話です。
ご存知の通りイグノーベル賞とはノーベル賞のパロディで、奇抜な研究に対して贈られる賞です。
一種のユーモアとして始められたものでしたが、回を重ねるごとに知名度を上げて今では受賞者も喜んで参列する式典となりました。
研究内容が一見バカげていても、そこには真剣な理由や目的があります。
そうでなければ大学や国が研究費を出すはずがありません。
ただ、見た目の華やかさだけで人は評価をしてしまいがちです。
そこに一石を投じたのがイグノーベル賞でした。
素人からすれば鼻で笑ってしまうような研究であっても、その一石が波紋となり本来の輝きが明らかになったのでした。
私たちが暮らしの中で目にしている当たり前というのは、数々の日蔭が積み重なって結実したものでありました。
世の中に奇想天外な研究がこれほど数多くあったというのは驚きですが、しかしそれこそは、当たり前なことが当たり前になる前の
つぼみ、言いかえれば日蔭そのものであるわけです。
それにしても日本人が10年も連続受賞しているというのは、なんと誇らしいことでしょうか。
どう考えても金目にならない研究、実用性のない研究、馬鹿馬鹿しく思えるような研究ばかりなのにそれを許容できるのは、本当に懐が
深く、成熟した社会だと言えるでしょう。
例えばバナナにすっ転ぶ研究といったものは、スケールは違いますが宇宙観測などと本質的に変わらないものです。
地表観測やロケット開発などの軍事戦略的な意味合いを抜きにすると、純粋な天体観測というのはとにかく莫大な費用がかかるだけで、
日常生活が革新的に便利になったり、あるいは何かの大儲けに繋がることなど決して無い研究です。
その目的はただ、私たち人間やこの天地宇宙が如何にして生じたのか、あるいはどのようにして存在できているのかという知の探究で
しかありません。
そのようなことに途轍もない労力と費用をかけられる社会というのは、成熟以外の何ものでないでしょう。
そして、それはイグノーベル賞のような一見笑ってしまうような研究であっても同じであるわけです。
私たちがただ単に生きるだけなら、明らかに実利のある事柄だけに集中投資した方が効率的です。
しかし、現実というのはそうではありません。
様々な生きものたちが生存することに全力を向けているのに対して、私たちにとっての生存というのは別の目的を叶えるためのもの
でもあります。
すなわち、生きるために生きるのではなく、心を満たすために生きているということです。
だからこそ、心の満たされない状態が続くと絶望してしまい、心を壊したり死を選ぶようなことが起きてしまうわけです。
もとより私たちは生きるためだけに生きているのではありませんので、そうしたことを責めることは出来ません。
ただ、だからこそ、そうなってしまう前に自分にとっての「心が満たされる」ということが何なのか、見誤らないことが重要になって
きます。
自分の身の回りを充実させる、物品に満たされる、飲食に身を投じる、嗜好品に興じる…
あるいは、何かに没頭する、誰かのために何かをする、人の喜ぶことをする、国や社会に貢献する。
一口に「心を満たす」と言っても、それは状況によって、あるいは人によって様々です。
魂の成長の差などという一言で片付けてしまうようなものではなく、ある意味、言葉のアヤでしかないと言えるかもしれません。
どれもこれも「心を満たす」という表現でくくられてしまっていますが、実際はベクトルも土俵も全く異なるものです。
正しく言えば、前者は「自我の衝動に応える」であり、後者は「芯の部分から湧き上がる幸福感を求める」になります。
しかしここでも間違えてはいけないのが、自我というものに対して単なる欲得感情のように捉えてしまうことです。
例えば、戦後日本が高度成長期を経て豊かになる中では、心を壊す人や命を絶つ人が今ほど居ませんでした。
一つには、生きるに必死だったということもあるでしょうが、その一方では目に見えて景色が変わっていったということもあるでしょう。
一つ一つの芽が土中から花開くさまを目の当たりにしていくにつれ、心は満たされていったはずです。
少し前に流行った昭和30年代のノスタルジックというのはその肌感覚の反芻だったのではないかと思います。
日なたの結実を目の当たりにして、生きているという実感を持てた、一歩一歩しっかり山を登っている実感を持てたいうことです。
身の回りの物品に魅力を感じることが未熟だとか幼いということではなく、それぞれ根本から全く異なるものであるわけです。
ただ、生きとし生けるもの、少しずつ魂の照らす範囲が広がっていくに従って、当然のことながら心の満たされかたも変わってきます。
そして、魂の照らす範囲が広がるにつれて、自我というものが明確になっていきます。
動植物から人間へと魂が経験を重ねていくにつれて、個体の中でおさまっていた自我が少しずつ色濃くなっていきました。
そうして魂の照らす範囲が一個体の中にとどまらず、その外へと広がって行く時、その自我もその外へと広がって行くことになります。
それはいま私たちが解釈しているところの「自我」とは異なるものであるわけですが、これまでの魂の進化の延長として考える
ならばそれもまた「自我」で間違いないわけです。
進化の遥か先にある天体や宇宙というものも自我を有していて、ただそれは自他の区別が無くなっている状態にあるということです。
自我が個体の外へと広がっていくというのは、要するに、自他の境を薄めていくことと同意と言えます。
「自我」と聞いた時に固定的な概念をイメージしてしまうと、それを「失くす」とか「薄める」、「昇華させる」「手放す」という
発想になって、それではない何かを追い求めることになってしまいます。
しかし、実際はすべては同じ延長上にあるもので、それは例えば私たちの肉体が成長するにつれて変化していくのと何ら変わりない
ものなわけです。
身体の成長ということに関して、子供の肉体を捨てて大人になるとか、子供の肉体を手放して成長するという考え方がいかに的外れで
あるか。
それらは同じ一直線上にあり、内含しながら変化しているだけであるというのは誰もが当たり前に理解していることでしょう。
子供の肉体を手放さなければ大人になれないと思い込むが如く、私たちは自我を手放さなければ真我に近づかないと思い込んでいます。
それがかえって、自我というものを固定化させることになっています。
そうやって一個体の中に自我をとどめてしまっている結果、私たちは魂の照らす範囲との間にギャップを生じさせてしまっています。
いつまでたっても満たされない想いというのは、そのギャップがあるが故に、魂の照らす範囲と、自身のアクションとがズレてしまって
いるということです。
もしも魂の照らす範囲が個体の内にある場合は、自分だけのことでも十分に満たされるでしょうが、照らす範囲が自分自身から
溢れている場合それでは満たされなくなります。
そして人間というのは、その魂が、一個体の範囲を遥かに越えてその周囲までを照らす存在です。
魂が成長していく過程で、太陽の照らすがごとくその光の照らされる範囲は少しずつ大きくなっていきます。
生まれ変わるごとに、照らされる範囲に合わせるように着替えていき、それが一個体の範囲を越えて照らされる時、私ちちは人間という
身体をまとうようになるのです。
私たちは誰もが、本人の自覚、気持ちの有る無しに関係なく、その魂は一個体の範囲を越えて周囲を照らしているということです。
ですから、優等生的な発想からではなく、私たちは、自己保身や自我の欲に応えるだけでは芯から満たされることはないのです。
この話を進めていくと、例えば、自分の心と向き合って生きてきた人や、信心深い人、前世において心を磨いてきた人は、それが顕著に
なるということになります。
端的に言ってしまえば、自分のためだけに生きていると虚しくなっていくということです。
魂の照らす範囲が広ければ広いほどそうなってしまう。
平凡な人生だろうが、派手な人生だろうが、そこのところはあまり関係がない。
自分という個体の範囲を越えて、溢れ出すようにして他者へと心を向けることが、満たされぬ想いを解決する糸口になっていくのです。
といって、他人の顔色を窺いながら生きて行くということではありません。
それは、嫌われたくない、波風立てず平穏に暮らしたいということですから、結局のところ自分のためだけに生きていることに他なら
ないからです。
(つづく)

にほんブログ村
ノーベル賞ではなく、イグノーベル賞の方の話です。
ご存知の通りイグノーベル賞とはノーベル賞のパロディで、奇抜な研究に対して贈られる賞です。
一種のユーモアとして始められたものでしたが、回を重ねるごとに知名度を上げて今では受賞者も喜んで参列する式典となりました。
研究内容が一見バカげていても、そこには真剣な理由や目的があります。
そうでなければ大学や国が研究費を出すはずがありません。
ただ、見た目の華やかさだけで人は評価をしてしまいがちです。
そこに一石を投じたのがイグノーベル賞でした。
素人からすれば鼻で笑ってしまうような研究であっても、その一石が波紋となり本来の輝きが明らかになったのでした。
私たちが暮らしの中で目にしている当たり前というのは、数々の日蔭が積み重なって結実したものでありました。
世の中に奇想天外な研究がこれほど数多くあったというのは驚きですが、しかしそれこそは、当たり前なことが当たり前になる前の
つぼみ、言いかえれば日蔭そのものであるわけです。
それにしても日本人が10年も連続受賞しているというのは、なんと誇らしいことでしょうか。
どう考えても金目にならない研究、実用性のない研究、馬鹿馬鹿しく思えるような研究ばかりなのにそれを許容できるのは、本当に懐が
深く、成熟した社会だと言えるでしょう。
例えばバナナにすっ転ぶ研究といったものは、スケールは違いますが宇宙観測などと本質的に変わらないものです。
地表観測やロケット開発などの軍事戦略的な意味合いを抜きにすると、純粋な天体観測というのはとにかく莫大な費用がかかるだけで、
日常生活が革新的に便利になったり、あるいは何かの大儲けに繋がることなど決して無い研究です。
その目的はただ、私たち人間やこの天地宇宙が如何にして生じたのか、あるいはどのようにして存在できているのかという知の探究で
しかありません。
そのようなことに途轍もない労力と費用をかけられる社会というのは、成熟以外の何ものでないでしょう。
そして、それはイグノーベル賞のような一見笑ってしまうような研究であっても同じであるわけです。
私たちがただ単に生きるだけなら、明らかに実利のある事柄だけに集中投資した方が効率的です。
しかし、現実というのはそうではありません。
様々な生きものたちが生存することに全力を向けているのに対して、私たちにとっての生存というのは別の目的を叶えるためのもの
でもあります。
すなわち、生きるために生きるのではなく、心を満たすために生きているということです。
だからこそ、心の満たされない状態が続くと絶望してしまい、心を壊したり死を選ぶようなことが起きてしまうわけです。
もとより私たちは生きるためだけに生きているのではありませんので、そうしたことを責めることは出来ません。
ただ、だからこそ、そうなってしまう前に自分にとっての「心が満たされる」ということが何なのか、見誤らないことが重要になって
きます。
自分の身の回りを充実させる、物品に満たされる、飲食に身を投じる、嗜好品に興じる…
あるいは、何かに没頭する、誰かのために何かをする、人の喜ぶことをする、国や社会に貢献する。
一口に「心を満たす」と言っても、それは状況によって、あるいは人によって様々です。
魂の成長の差などという一言で片付けてしまうようなものではなく、ある意味、言葉のアヤでしかないと言えるかもしれません。
どれもこれも「心を満たす」という表現でくくられてしまっていますが、実際はベクトルも土俵も全く異なるものです。
正しく言えば、前者は「自我の衝動に応える」であり、後者は「芯の部分から湧き上がる幸福感を求める」になります。
しかしここでも間違えてはいけないのが、自我というものに対して単なる欲得感情のように捉えてしまうことです。
例えば、戦後日本が高度成長期を経て豊かになる中では、心を壊す人や命を絶つ人が今ほど居ませんでした。
一つには、生きるに必死だったということもあるでしょうが、その一方では目に見えて景色が変わっていったということもあるでしょう。
一つ一つの芽が土中から花開くさまを目の当たりにしていくにつれ、心は満たされていったはずです。
少し前に流行った昭和30年代のノスタルジックというのはその肌感覚の反芻だったのではないかと思います。
日なたの結実を目の当たりにして、生きているという実感を持てた、一歩一歩しっかり山を登っている実感を持てたいうことです。
身の回りの物品に魅力を感じることが未熟だとか幼いということではなく、それぞれ根本から全く異なるものであるわけです。
ただ、生きとし生けるもの、少しずつ魂の照らす範囲が広がっていくに従って、当然のことながら心の満たされかたも変わってきます。
そして、魂の照らす範囲が広がるにつれて、自我というものが明確になっていきます。
動植物から人間へと魂が経験を重ねていくにつれて、個体の中でおさまっていた自我が少しずつ色濃くなっていきました。
そうして魂の照らす範囲が一個体の中にとどまらず、その外へと広がって行く時、その自我もその外へと広がって行くことになります。
それはいま私たちが解釈しているところの「自我」とは異なるものであるわけですが、これまでの魂の進化の延長として考える
ならばそれもまた「自我」で間違いないわけです。
進化の遥か先にある天体や宇宙というものも自我を有していて、ただそれは自他の区別が無くなっている状態にあるということです。
自我が個体の外へと広がっていくというのは、要するに、自他の境を薄めていくことと同意と言えます。
「自我」と聞いた時に固定的な概念をイメージしてしまうと、それを「失くす」とか「薄める」、「昇華させる」「手放す」という
発想になって、それではない何かを追い求めることになってしまいます。
しかし、実際はすべては同じ延長上にあるもので、それは例えば私たちの肉体が成長するにつれて変化していくのと何ら変わりない
ものなわけです。
身体の成長ということに関して、子供の肉体を捨てて大人になるとか、子供の肉体を手放して成長するという考え方がいかに的外れで
あるか。
それらは同じ一直線上にあり、内含しながら変化しているだけであるというのは誰もが当たり前に理解していることでしょう。
子供の肉体を手放さなければ大人になれないと思い込むが如く、私たちは自我を手放さなければ真我に近づかないと思い込んでいます。
それがかえって、自我というものを固定化させることになっています。
そうやって一個体の中に自我をとどめてしまっている結果、私たちは魂の照らす範囲との間にギャップを生じさせてしまっています。
いつまでたっても満たされない想いというのは、そのギャップがあるが故に、魂の照らす範囲と、自身のアクションとがズレてしまって
いるということです。
もしも魂の照らす範囲が個体の内にある場合は、自分だけのことでも十分に満たされるでしょうが、照らす範囲が自分自身から
溢れている場合それでは満たされなくなります。
そして人間というのは、その魂が、一個体の範囲を遥かに越えてその周囲までを照らす存在です。
魂が成長していく過程で、太陽の照らすがごとくその光の照らされる範囲は少しずつ大きくなっていきます。
生まれ変わるごとに、照らされる範囲に合わせるように着替えていき、それが一個体の範囲を越えて照らされる時、私ちちは人間という
身体をまとうようになるのです。
私たちは誰もが、本人の自覚、気持ちの有る無しに関係なく、その魂は一個体の範囲を越えて周囲を照らしているということです。
ですから、優等生的な発想からではなく、私たちは、自己保身や自我の欲に応えるだけでは芯から満たされることはないのです。
この話を進めていくと、例えば、自分の心と向き合って生きてきた人や、信心深い人、前世において心を磨いてきた人は、それが顕著に
なるということになります。
端的に言ってしまえば、自分のためだけに生きていると虚しくなっていくということです。
魂の照らす範囲が広ければ広いほどそうなってしまう。
平凡な人生だろうが、派手な人生だろうが、そこのところはあまり関係がない。
自分という個体の範囲を越えて、溢れ出すようにして他者へと心を向けることが、満たされぬ想いを解決する糸口になっていくのです。
といって、他人の顔色を窺いながら生きて行くということではありません。
それは、嫌われたくない、波風立てず平穏に暮らしたいということですから、結局のところ自分のためだけに生きていることに他なら
ないからです。
(つづく)
にほんブログ村