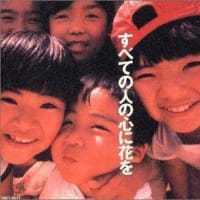人生に面白みを感じられなくなったり、時が経つのを虚しく思ったり、この世に張り合いが無くなった時に、ふと自分にもそろそろ
お迎えが来るのかと思うことが、もしかしたらあるかもしれません。
確かに自分の魂とその思いが一致していればそうなるところですが、実際のところがどうであるのか表層の私たちがそれを知覚する
ことはまずもって無理な話でしょう。
ただ間接的な証明として、実際こうして今も生きているということは、私たちの魂は「この世でやることはやり尽くした」とは思って
居ないということが言えます。
それとは逆のケースとして、表層意識で「まだやり残したことがある」と思っても、魂が「今回やることはやった」と判断すれば
アッサリと旅立つことになるのですから、それをもってしても先ほどの証明は明らかであるわけです。
あの世に旅立たつことなくこうして生かされているということは、魂が「まだまだ味わえることがある」のを知っている状態だと
いうことです。
ですから、虚しい、つまらない、張り合いがないと感じている表層意識の方こそ事実誤認ということになります。
そのような思いが全身を覆い尽くしている時、あたかもそれが世界の真実であるように感じますが、その水面下で私たちの魂は全く
涼しい顔で、まだまだ味わっていない喜びを今か今かと楽しみにしているわけです。
こうしたギャップは、心の向け先が魂の照らす範囲とズレてしまっていることによって生じています。
ただ理屈はそうであるのですが、それならば魂が照らしているのが何処なのか探そうじゃないか、となると、それは逆に解決を遠ざける
ことになってしまいます。
そもそも心が向いたところにしか私たちのサーチライトは当たりません。
しかし、心の向いていないところ、いま光の当たらないところにそれはあります。
私たちのヘッドライトがおでこに固定されているうちは、いくらキョロキョロしても絶対に見つかりません。
まるでそれを避けるかのように、常にその光が当たらないところに在り続けるのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
むしろ、光を当てようとしない、見ようとしないことがそれらを感じ取る近道になります。
見ようとしないといっても、その存在を無視したり、気にしまいとするのではありません。
それは、普通に確信している状態です。
「それは在る。ただ、今は見えていない。」
ひとたび腹に落とせば、あとは放っとくだけです。
私たちの魂は、私たち自身だけにとどまらずこの周囲を大きく照らしています。
その照らすものとは、人であり、物ごとであり、事象の流れといったマトリックスの世界であるわけです。
ですから、今は見えていない水面下の日蔭にも魂の光は届いていますし、同じようにまわりの人や物事へも広がっているということです。
魂が楽しみに待っているという景色、私たちにはまだ見えぬ世界が目に映るようになるのは、私たちの心がそこに向いた時です。
つまりは、魂が照らす範囲へと心が広がった時ということです。
そしてその照らす先がどこなのか分からない、あるいはボンヤリ見えはしても逃げ水のようにそこへ近づくことができないのならば、
まずは自分の身のまわりへと心を向けていけばいい。
魂は全方位に広がっていますので、そのうち一つにでも心が一致すれば、自ずと他の方位にも心は広がっていくということです。
そしてそれというのは「心を満たす」ことの解決にもなっていきます。
水面下の方向というのが何なのか分からなくとも、別の方向で1つだけ明らかなことがあります。
つまり、他人へ心を向けて他人のために何かをすることです。
それこそが、心の不足感を埋めることになり、また、目に映って居なかった景色を水面上に浮かび上がらせることにもなっていく
わけです。
こうしたことは打算や損得勘定、交換条件では成立しないのは明らかです。
たとえ見た目には世のため人のためであったとしても、もしそこに打算や損得勘定があったならば、その心は自分に向いたものであり、
自分のためにしていることに他ないからです。
これは、陰徳というものが、誰にも気づかれない方がいいとする理由でもあります。
景色にせよ、不足感にせよ、心が外へと広がることで初めて変わっていくものであって、自分に心が向いてしまっているのでは何も変わら
ないどころか、むしろその傾向をさらに強めることにしかならないわけです。
いま、目の前に大道が広がっていたとしても、それが私たちの全てではありません。
世間で言われるところの正道、燦々と日が照らす本道だけでなく、誰の目も向いていない脇の道がこの世には無数に存在しています。
それは仕事かもしれませんし、趣味かもしれません。
あるいはそんなジャンルを越えたものかもしれません。
そしてそれは今の私たちには想像もつかないことであるということでした。
しかし、それは確実に存在しています。
何故かと言えば、私たちは何かを味わいたくてこの世に生まれて来たからです。
そして、それがまだ見ぬ何処かに存在しているのは、今こうして生きていることこそが一番の証拠です。
生きることが虚しくなったのならば、その味わい求めた何かが今の景色には映っていないというだけなのです。
私たちは、見たいものしか見えていません。
見ようとしたものしか見えません。
それは無意識に行われているため、そもそも見ていないことにすら気づけていないというのが真実です。
ですから、魂が味わい求める景色というのは、すでに目の前にあるのに単に見えていないだけかもしれません。
もちろん、そもそも目の前には無いということもあります。
どちらのケースであっても共通しているのは、今の私たちには想像もつかないところにそれは在るということです。
だからこそ、その存在を確信することが、自然のうちにそれを浮かび上がらせるための解決法でありました。
そしてそれを邪魔しているものこそ、私たちの頭に固定されたヘッドライトであるわけです。
つまり、目の前に広がる大道が唯一の正道だという思い込み、固定観念をリセットすることが真っ先に必要となってくるということです。
私たちが個々に生きる人生というのは、目に映っている景色が全てではない、と。
とはいえ固定観念というのは固定されてどうにもならないものだから固定観念と呼ばれていますので、それを否定したり無くそうとしても
どうにかなるものではありません。
ですから今ここでは、ただ「これ以外のものも在るのだ」という気持ちを持つだけです。
目に映るもの以外、心に映るもの以外の価値観を受け入れるということであるわけです。
・・・
あるときフト、誰も見向かないような脇道の存在に気づきました。
そこは道と言うにはあまりに荒れ果てて、誰もそれとは思わないような、道なき道でした。
しかし、ただ気になるというその一点だけでその人は突き進む。
たとえ笑われようと、理解されまいと。
それがいつしかトンデモないオアシスへと繋がる道となりました。
それは自分だけ心地よいものかもしれませんし、誰にとっても心地よいものかもしれません。
しかし、そのどちらであろうと、その道が正道となり、大道となったことに違いはありませんでした。
自分自身にとっての晴れやかな道であれば、すでにそれは日蔭の道でなく天下の大道と成っているわけです。

日蔭の脇道も必ず日なたに成ります。
だからこそ、脇道を許容する社会、それを受け入れる心というのが大事になります。
この脇道というのは、現実的な世界を指すだけでなく、心の道も指します。
たとえ現実が変わらなくとも、目の前に映る大道だけに心を縛らず、目には見えない蔭へと
目を向けた時、脇道はその脇道のまま爽やかな風が吹き抜ける大道へ成っていきます。
それは理屈や打算、常識や価値観によって支えられるものではありません。
そもそも、脇道とは常に想定を逸脱するものです。
脱線すればこその脇道であるわけです。
そうでなければ新世界に成ることなど理屈からしても不可能です。
つまりそれは理屈から一番遠いところにあるということです。
理想論や真面目さとは対極にある。
打算や逆算で心を押さえつけるのは苦しみにしかなりません。
景色に映らないものを否定しない心というのは、異なるものを拒絶しない心、むしろそうした突拍子もない事柄を笑い飛ばせる心が
大前提となります。
許容する心、受け入れる心というのは、結局のところ自分自身に向ける心となり、つまりは進んで脇道へと身を投じる心にもなって
いきます。
冒頭のイグノーベル賞を受賞した研究者はもちろん、ノーベル賞を受賞した研究者たちにしても、誰も通らない脇道を進みました。
ここになんか気になる道があるぞ?と思って、目の前にある道を進んで行ったのでした。
結果がどうなるかよりも、目の前の一つ一つに正直になったのでした。
そしてそのノーベル賞を受賞した大隅先生はこう仰っています。
「人と違うことをおそれずに、自分の道を見極めて突き進んで欲しい」
これを聞いて、また特別な花道のようなものを想像してしまうとおかしなことになってしまいます。
別にみんながノーベル賞なんかを取る必要など全く無いのですから。
私たちは誰一人として同じ人間は居ません。
他人とは違うに決まっています。
そんな当たり前のことなのに、私たちはそのことをすぐに忘れてしまいます。
働くとはこういうもの、サラリーマンとはこういうもの、主婦とはこういうもの、生きるとはこういうもの…
そうした思い込みに縛られ、いつしか世の中の大道だけを歩くようになりました。
そうして、自分なんかがみんなと違うはずがない(特別なはずがない)と信じ込んでしまいました。
もう一度繰り返します。
私たちは、誰一人として同じ人間は居ません。
ですから、そのまま普通に歩けば、それが自分の道となります。
たまたま似たような道になることもあるでしょうが、間違いなくそれぞれ違う道になっています。
わざわざトリッキーな脇道を探そうとか、目の前の道を逸脱しようとかしなくても、普通に歩いていけばイイのです。
いけないことというのは、知らず知らずのうちに「世間の大道」を歩こうとすることです。
決めつけない。
あとは、ただ普通に歩いていくだけです。
それこそが「天地の大道」であるわけです。

にほんブログ村
お迎えが来るのかと思うことが、もしかしたらあるかもしれません。
確かに自分の魂とその思いが一致していればそうなるところですが、実際のところがどうであるのか表層の私たちがそれを知覚する
ことはまずもって無理な話でしょう。
ただ間接的な証明として、実際こうして今も生きているということは、私たちの魂は「この世でやることはやり尽くした」とは思って
居ないということが言えます。
それとは逆のケースとして、表層意識で「まだやり残したことがある」と思っても、魂が「今回やることはやった」と判断すれば
アッサリと旅立つことになるのですから、それをもってしても先ほどの証明は明らかであるわけです。
あの世に旅立たつことなくこうして生かされているということは、魂が「まだまだ味わえることがある」のを知っている状態だと
いうことです。
ですから、虚しい、つまらない、張り合いがないと感じている表層意識の方こそ事実誤認ということになります。
そのような思いが全身を覆い尽くしている時、あたかもそれが世界の真実であるように感じますが、その水面下で私たちの魂は全く
涼しい顔で、まだまだ味わっていない喜びを今か今かと楽しみにしているわけです。
こうしたギャップは、心の向け先が魂の照らす範囲とズレてしまっていることによって生じています。
ただ理屈はそうであるのですが、それならば魂が照らしているのが何処なのか探そうじゃないか、となると、それは逆に解決を遠ざける
ことになってしまいます。
そもそも心が向いたところにしか私たちのサーチライトは当たりません。
しかし、心の向いていないところ、いま光の当たらないところにそれはあります。
私たちのヘッドライトがおでこに固定されているうちは、いくらキョロキョロしても絶対に見つかりません。
まるでそれを避けるかのように、常にその光が当たらないところに在り続けるのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
むしろ、光を当てようとしない、見ようとしないことがそれらを感じ取る近道になります。
見ようとしないといっても、その存在を無視したり、気にしまいとするのではありません。
それは、普通に確信している状態です。
「それは在る。ただ、今は見えていない。」
ひとたび腹に落とせば、あとは放っとくだけです。
私たちの魂は、私たち自身だけにとどまらずこの周囲を大きく照らしています。
その照らすものとは、人であり、物ごとであり、事象の流れといったマトリックスの世界であるわけです。
ですから、今は見えていない水面下の日蔭にも魂の光は届いていますし、同じようにまわりの人や物事へも広がっているということです。
魂が楽しみに待っているという景色、私たちにはまだ見えぬ世界が目に映るようになるのは、私たちの心がそこに向いた時です。
つまりは、魂が照らす範囲へと心が広がった時ということです。
そしてその照らす先がどこなのか分からない、あるいはボンヤリ見えはしても逃げ水のようにそこへ近づくことができないのならば、
まずは自分の身のまわりへと心を向けていけばいい。
魂は全方位に広がっていますので、そのうち一つにでも心が一致すれば、自ずと他の方位にも心は広がっていくということです。
そしてそれというのは「心を満たす」ことの解決にもなっていきます。
水面下の方向というのが何なのか分からなくとも、別の方向で1つだけ明らかなことがあります。
つまり、他人へ心を向けて他人のために何かをすることです。
それこそが、心の不足感を埋めることになり、また、目に映って居なかった景色を水面上に浮かび上がらせることにもなっていく
わけです。
こうしたことは打算や損得勘定、交換条件では成立しないのは明らかです。
たとえ見た目には世のため人のためであったとしても、もしそこに打算や損得勘定があったならば、その心は自分に向いたものであり、
自分のためにしていることに他ないからです。
これは、陰徳というものが、誰にも気づかれない方がいいとする理由でもあります。
景色にせよ、不足感にせよ、心が外へと広がることで初めて変わっていくものであって、自分に心が向いてしまっているのでは何も変わら
ないどころか、むしろその傾向をさらに強めることにしかならないわけです。
いま、目の前に大道が広がっていたとしても、それが私たちの全てではありません。
世間で言われるところの正道、燦々と日が照らす本道だけでなく、誰の目も向いていない脇の道がこの世には無数に存在しています。
それは仕事かもしれませんし、趣味かもしれません。
あるいはそんなジャンルを越えたものかもしれません。
そしてそれは今の私たちには想像もつかないことであるということでした。
しかし、それは確実に存在しています。
何故かと言えば、私たちは何かを味わいたくてこの世に生まれて来たからです。
そして、それがまだ見ぬ何処かに存在しているのは、今こうして生きていることこそが一番の証拠です。
生きることが虚しくなったのならば、その味わい求めた何かが今の景色には映っていないというだけなのです。
私たちは、見たいものしか見えていません。
見ようとしたものしか見えません。
それは無意識に行われているため、そもそも見ていないことにすら気づけていないというのが真実です。
ですから、魂が味わい求める景色というのは、すでに目の前にあるのに単に見えていないだけかもしれません。
もちろん、そもそも目の前には無いということもあります。
どちらのケースであっても共通しているのは、今の私たちには想像もつかないところにそれは在るということです。
だからこそ、その存在を確信することが、自然のうちにそれを浮かび上がらせるための解決法でありました。
そしてそれを邪魔しているものこそ、私たちの頭に固定されたヘッドライトであるわけです。
つまり、目の前に広がる大道が唯一の正道だという思い込み、固定観念をリセットすることが真っ先に必要となってくるということです。
私たちが個々に生きる人生というのは、目に映っている景色が全てではない、と。
とはいえ固定観念というのは固定されてどうにもならないものだから固定観念と呼ばれていますので、それを否定したり無くそうとしても
どうにかなるものではありません。
ですから今ここでは、ただ「これ以外のものも在るのだ」という気持ちを持つだけです。
目に映るもの以外、心に映るもの以外の価値観を受け入れるということであるわけです。
・・・
あるときフト、誰も見向かないような脇道の存在に気づきました。
そこは道と言うにはあまりに荒れ果てて、誰もそれとは思わないような、道なき道でした。
しかし、ただ気になるというその一点だけでその人は突き進む。
たとえ笑われようと、理解されまいと。
それがいつしかトンデモないオアシスへと繋がる道となりました。
それは自分だけ心地よいものかもしれませんし、誰にとっても心地よいものかもしれません。
しかし、そのどちらであろうと、その道が正道となり、大道となったことに違いはありませんでした。
自分自身にとっての晴れやかな道であれば、すでにそれは日蔭の道でなく天下の大道と成っているわけです。

日蔭の脇道も必ず日なたに成ります。
だからこそ、脇道を許容する社会、それを受け入れる心というのが大事になります。
この脇道というのは、現実的な世界を指すだけでなく、心の道も指します。
たとえ現実が変わらなくとも、目の前に映る大道だけに心を縛らず、目には見えない蔭へと
目を向けた時、脇道はその脇道のまま爽やかな風が吹き抜ける大道へ成っていきます。
それは理屈や打算、常識や価値観によって支えられるものではありません。
そもそも、脇道とは常に想定を逸脱するものです。
脱線すればこその脇道であるわけです。
そうでなければ新世界に成ることなど理屈からしても不可能です。
つまりそれは理屈から一番遠いところにあるということです。
理想論や真面目さとは対極にある。
打算や逆算で心を押さえつけるのは苦しみにしかなりません。
景色に映らないものを否定しない心というのは、異なるものを拒絶しない心、むしろそうした突拍子もない事柄を笑い飛ばせる心が
大前提となります。
許容する心、受け入れる心というのは、結局のところ自分自身に向ける心となり、つまりは進んで脇道へと身を投じる心にもなって
いきます。
冒頭のイグノーベル賞を受賞した研究者はもちろん、ノーベル賞を受賞した研究者たちにしても、誰も通らない脇道を進みました。
ここになんか気になる道があるぞ?と思って、目の前にある道を進んで行ったのでした。
結果がどうなるかよりも、目の前の一つ一つに正直になったのでした。
そしてそのノーベル賞を受賞した大隅先生はこう仰っています。
「人と違うことをおそれずに、自分の道を見極めて突き進んで欲しい」
これを聞いて、また特別な花道のようなものを想像してしまうとおかしなことになってしまいます。
別にみんながノーベル賞なんかを取る必要など全く無いのですから。
私たちは誰一人として同じ人間は居ません。
他人とは違うに決まっています。
そんな当たり前のことなのに、私たちはそのことをすぐに忘れてしまいます。
働くとはこういうもの、サラリーマンとはこういうもの、主婦とはこういうもの、生きるとはこういうもの…
そうした思い込みに縛られ、いつしか世の中の大道だけを歩くようになりました。
そうして、自分なんかがみんなと違うはずがない(特別なはずがない)と信じ込んでしまいました。
もう一度繰り返します。
私たちは、誰一人として同じ人間は居ません。
ですから、そのまま普通に歩けば、それが自分の道となります。
たまたま似たような道になることもあるでしょうが、間違いなくそれぞれ違う道になっています。
わざわざトリッキーな脇道を探そうとか、目の前の道を逸脱しようとかしなくても、普通に歩いていけばイイのです。
いけないことというのは、知らず知らずのうちに「世間の大道」を歩こうとすることです。
決めつけない。
あとは、ただ普通に歩いていくだけです。
それこそが「天地の大道」であるわけです。
にほんブログ村