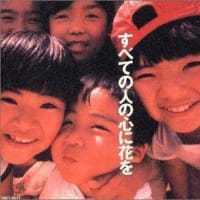世界には偶像崇拝を禁ずる宗教が数多くあります。
原理主義者たちが歴史的遺産を破壊するのも、大義名分としてはそうした原典に基づいた行ない
ということになっています。
さすがにそこまで過激なことは必要ないまでも、方便であるはずの偶像に囚われて内なる執着を
深めてしまうのでは本末転倒と言わざるを得ません。
幸い、私たち日本人は、古くから自然を敬ってきましたので、手を合わせる対象は天地宇宙へと
広がっていました。
風や雲、山や海、草木や動物、身の回りのあらゆるものの中に深淵なる神性を感じてきました。
これはアボリジニやインディアンなど古くからの先住民族にも共通して見られるものです。
即物的な人たちには、そのようなことが物質や現象そのものを崇め奉る姿に見えてしまい、文化的
あるいは文明的な後進性を感じることもあるようです。
しかし私たち日本人は、当たり前に、そうではないことが分かっています。
天地の万物を表層的には捉えず、太陽コロナのように僅かにその背から滲み出す後光を感じ取り
ます。
そこから漂い出る精妙な風を、全身の毛穴を開いて感じ取るわけです。
そのような天地宇宙の真の姿を感じ取ればこそ、恐れおののき、畏れ敬うのです。
仏教伝来とともに仏像を拝む習慣が流入しても、そうした心の姿勢は変わらず、偶像そのものに
すがりつくこともありませんでした。
今でも私たちは仏像を前にした時、ごく自然に、その先の存在に対して手を合わせています。
仏像というのは一つの焦点、目印です。
そこに意識を向けることで、あちこちへと移ろう心が静まり、それとともに自ずと天地へと広がって
いくというわけです。
もし目の前の仏像そのものに意識がとどまってしまうと、心もそこで止まってしまいます。
美術品として鑑賞をしている時はこの状態です。
しかし、それを指月の指として、天に浮かぶ月へと心を向けると、感覚はガラリと変わります。
気づけば、心は外に広がる天地へとフルオープンとなり、無限に溶け合っていきます。
私たちは、目の前の仏像を取っ掛かりとして、知らず知らずその先へと心を向けています。
この場合は決して偶像崇拝にはなりません。
ありがたいという思いは、仏像の向こうの存在(感覚)に対する思いであり、またそれを介して
下さった仏像そのものにもありがたさを感じるわけです。
実際、そのような心が注がれる仏像は、日々祓われていることになります。
そうして仏像そのものも神々しさを放つようになるのです。
実はこれこそが、天地万物に対して私たちが振る舞うべき姿を現しています。
私たちは日々あらゆる現実、モノ、事象に囲まれています。
そうしたモノや事柄は、先ほどの仏像に置き換えることができます。
仏像はそれそのものをジーッと見ている限りは、ただのモノでしかありません。
彩色の剥げ落ちた古い木の塊になってしまいます。
しかし、その先に広がる世界(存在)に心を広げることによって、初めてそれが美しい輝きを
放つようになります。
私たちを取り巻く様々な現実も、それそのものに囚われている限りは、モノとして眺める行為と
変わりありません。
すると、どうしても金箔や極彩色に装飾された美品ばかりに目を奪われてしまいます。
あるいは、そうしたものに魅力を感じなかったとしても、すすけた塊や小汚いものが目の前に
出されたらば、良くてスルー、悪ければ悲しんだり不満を漏らしたりしてしまいます。
見た目の姿形に囚われず、その向こうに広がるものを感じ取ろうと全身の毛穴を開くことで、
初めてそこに天地の姿を垣間見ることが出来るようになります。
この世の物事は、全てが指月の月です。
モノや事象の向こうには満天の月が広がっています。
道元禅師はこれを「山川草木悉有仏性」と言いました。
言い方を変えれば、この世のあらゆるものは、天地宇宙の心が映る依り代であるということです。
何ごとかに相対した時、心を開いてその先を感じ取ろうとした瞬間、たちまちにして清らかな風が
そこを通り抜けていきます。
実際のところ、それ自体が輝いているから清らかな心を向けるというのではなく、私たちが
清らかな心を向けるからそれ自体が輝くようになるのです。
これは非常に深い真理です。
清らかなものから流れる風によって私たちも清められ、またその私たちから流れる清らかな心に
よってその向け先も清らかになっていきます。
逆に、穢れたものに囚われれば私たちも濁ってしまいますし、私たちが濁ることによって目の前の
事象や物事、人物も穢されていきます。
なぜならば、全てのものはそもそもが依り代であるからです。
実体そのものではなく、それを包むものがその本体を決定付けているのです。
現実の出来事や事象、他人様といったものが輝くのも濁るのも、私たちの向ける心次第という
ことです。
私たちは日々、何かの出来事や、誰かの言動に接しています。
そうした時、目の前のものを見て、怒ったり悲しんだりしています。
目の前にある仮初めのものに囚われ縛られてしまっています。
つまり私たち人類は、強烈な偶像崇拝者であるわけです。
埴輪や土偶を奉って、いちいち怖れたり怒ったり悲しんだり喜んだりしている...
その姿は滑稽でもあり、また残念でもありはしないでしょうか。
だからといって、偶像が無意味なものというわけではありません。
何故ならば、それらを通して私たちはその奥に広がる世界を感じることができるからです。
いくらそれに囚われやすいからといって、偶像そのものが不浄なものということにはなりません。
むしろそれらは、清らかなる窓口であるわけです。
この世の現実を忌み嫌ったり、軽んじたりすることは、歴史的遺産を破壊する行為と変わらなく
なります。
天地無限の広がりは、目の前の仮初めの物事の先にあります。
それに触れさせるための取っ掛かり、焦点、例えて言うなら仏像、それがこの世の現実すべてで
あるわけです。
この世というのは現実的なものにしか触れることができません。
そういうルールのもと成り立っています。
しかし、いたるものがその向こうの映し身であるわけです。
つまり、ありとあらゆるものが向こうへの窓口なのです。
部屋に閉じこもらず、窓という窓を開け放して風を通していくことが、爽やか健康生活に繋がります。
そして私たちから漂い溢れる風が、窓を開く鍵となります。
清らかな風が、清らかな風を呼びます。
此方から吹く風に、彼方から吹く風が呼応します。
風漂えばこそ、また風を感じることができるのです。
風は我が身を包み、彼が身を包みます。
神道では「包む身」が「つみ(罪)」の語源と考えられています。
そして、そうした罪・穢れを祓い、天地へ感謝することが、神道の全てであるわけです。
心を清らかに軽やかにすれば、身の回りのありとあらゆる現実が窓となって、彼方の向こうから吹く
爽やかな風が全身を撫でることでしょう。
偶像に心を止めず、その向こうへと心を広げましょう。
この世の現実というのは、まさに紙一重の世界なのです。


原理主義者たちが歴史的遺産を破壊するのも、大義名分としてはそうした原典に基づいた行ない
ということになっています。
さすがにそこまで過激なことは必要ないまでも、方便であるはずの偶像に囚われて内なる執着を
深めてしまうのでは本末転倒と言わざるを得ません。
幸い、私たち日本人は、古くから自然を敬ってきましたので、手を合わせる対象は天地宇宙へと
広がっていました。
風や雲、山や海、草木や動物、身の回りのあらゆるものの中に深淵なる神性を感じてきました。
これはアボリジニやインディアンなど古くからの先住民族にも共通して見られるものです。
即物的な人たちには、そのようなことが物質や現象そのものを崇め奉る姿に見えてしまい、文化的
あるいは文明的な後進性を感じることもあるようです。
しかし私たち日本人は、当たり前に、そうではないことが分かっています。
天地の万物を表層的には捉えず、太陽コロナのように僅かにその背から滲み出す後光を感じ取り
ます。
そこから漂い出る精妙な風を、全身の毛穴を開いて感じ取るわけです。
そのような天地宇宙の真の姿を感じ取ればこそ、恐れおののき、畏れ敬うのです。
仏教伝来とともに仏像を拝む習慣が流入しても、そうした心の姿勢は変わらず、偶像そのものに
すがりつくこともありませんでした。
今でも私たちは仏像を前にした時、ごく自然に、その先の存在に対して手を合わせています。
仏像というのは一つの焦点、目印です。
そこに意識を向けることで、あちこちへと移ろう心が静まり、それとともに自ずと天地へと広がって
いくというわけです。
もし目の前の仏像そのものに意識がとどまってしまうと、心もそこで止まってしまいます。
美術品として鑑賞をしている時はこの状態です。
しかし、それを指月の指として、天に浮かぶ月へと心を向けると、感覚はガラリと変わります。
気づけば、心は外に広がる天地へとフルオープンとなり、無限に溶け合っていきます。
私たちは、目の前の仏像を取っ掛かりとして、知らず知らずその先へと心を向けています。
この場合は決して偶像崇拝にはなりません。
ありがたいという思いは、仏像の向こうの存在(感覚)に対する思いであり、またそれを介して
下さった仏像そのものにもありがたさを感じるわけです。
実際、そのような心が注がれる仏像は、日々祓われていることになります。
そうして仏像そのものも神々しさを放つようになるのです。
実はこれこそが、天地万物に対して私たちが振る舞うべき姿を現しています。
私たちは日々あらゆる現実、モノ、事象に囲まれています。
そうしたモノや事柄は、先ほどの仏像に置き換えることができます。
仏像はそれそのものをジーッと見ている限りは、ただのモノでしかありません。
彩色の剥げ落ちた古い木の塊になってしまいます。
しかし、その先に広がる世界(存在)に心を広げることによって、初めてそれが美しい輝きを
放つようになります。
私たちを取り巻く様々な現実も、それそのものに囚われている限りは、モノとして眺める行為と
変わりありません。
すると、どうしても金箔や極彩色に装飾された美品ばかりに目を奪われてしまいます。
あるいは、そうしたものに魅力を感じなかったとしても、すすけた塊や小汚いものが目の前に
出されたらば、良くてスルー、悪ければ悲しんだり不満を漏らしたりしてしまいます。
見た目の姿形に囚われず、その向こうに広がるものを感じ取ろうと全身の毛穴を開くことで、
初めてそこに天地の姿を垣間見ることが出来るようになります。
この世の物事は、全てが指月の月です。
モノや事象の向こうには満天の月が広がっています。
道元禅師はこれを「山川草木悉有仏性」と言いました。
言い方を変えれば、この世のあらゆるものは、天地宇宙の心が映る依り代であるということです。
何ごとかに相対した時、心を開いてその先を感じ取ろうとした瞬間、たちまちにして清らかな風が
そこを通り抜けていきます。
実際のところ、それ自体が輝いているから清らかな心を向けるというのではなく、私たちが
清らかな心を向けるからそれ自体が輝くようになるのです。
これは非常に深い真理です。
清らかなものから流れる風によって私たちも清められ、またその私たちから流れる清らかな心に
よってその向け先も清らかになっていきます。
逆に、穢れたものに囚われれば私たちも濁ってしまいますし、私たちが濁ることによって目の前の
事象や物事、人物も穢されていきます。
なぜならば、全てのものはそもそもが依り代であるからです。
実体そのものではなく、それを包むものがその本体を決定付けているのです。
現実の出来事や事象、他人様といったものが輝くのも濁るのも、私たちの向ける心次第という
ことです。
私たちは日々、何かの出来事や、誰かの言動に接しています。
そうした時、目の前のものを見て、怒ったり悲しんだりしています。
目の前にある仮初めのものに囚われ縛られてしまっています。
つまり私たち人類は、強烈な偶像崇拝者であるわけです。
埴輪や土偶を奉って、いちいち怖れたり怒ったり悲しんだり喜んだりしている...
その姿は滑稽でもあり、また残念でもありはしないでしょうか。
だからといって、偶像が無意味なものというわけではありません。
何故ならば、それらを通して私たちはその奥に広がる世界を感じることができるからです。
いくらそれに囚われやすいからといって、偶像そのものが不浄なものということにはなりません。
むしろそれらは、清らかなる窓口であるわけです。
この世の現実を忌み嫌ったり、軽んじたりすることは、歴史的遺産を破壊する行為と変わらなく
なります。
天地無限の広がりは、目の前の仮初めの物事の先にあります。
それに触れさせるための取っ掛かり、焦点、例えて言うなら仏像、それがこの世の現実すべてで
あるわけです。
この世というのは現実的なものにしか触れることができません。
そういうルールのもと成り立っています。
しかし、いたるものがその向こうの映し身であるわけです。
つまり、ありとあらゆるものが向こうへの窓口なのです。
部屋に閉じこもらず、窓という窓を開け放して風を通していくことが、爽やか健康生活に繋がります。
そして私たちから漂い溢れる風が、窓を開く鍵となります。
清らかな風が、清らかな風を呼びます。
此方から吹く風に、彼方から吹く風が呼応します。
風漂えばこそ、また風を感じることができるのです。
風は我が身を包み、彼が身を包みます。
神道では「包む身」が「つみ(罪)」の語源と考えられています。
そして、そうした罪・穢れを祓い、天地へ感謝することが、神道の全てであるわけです。
心を清らかに軽やかにすれば、身の回りのありとあらゆる現実が窓となって、彼方の向こうから吹く
爽やかな風が全身を撫でることでしょう。
偶像に心を止めず、その向こうへと心を広げましょう。
この世の現実というのは、まさに紙一重の世界なのです。