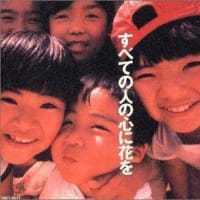草津に長逗留したため、シルバーウィークの最終日は完全に湯あたりしていました(笑)
湯あたりというのは、詰まるところエネルギー過多の状態です。
熱が出たり、頭痛がしたり、頭がクラクラしたり、気持ち悪かったりして食欲もありません。
こうなると半病人ですから、ひたすら寝て自然なチューニングを待つことになります。
それを見越して最終日は自宅に戻ったのですが、目論見ハズれ、急遽茨城に行くことになりました。
まだ大阪に住んでいた頃、今年は東京に戻らないとマズいという感覚とともに、行くべき場所が何ヶ所か
浮かびました。
箱根もその一つだったわけですが、同じように鹿島神宮と香取神宮が来てました。
箱根に行ったあとは流れとして南九州が先に来て、そのあとは湯あたりでシンドイ体調だったりして、
さて少し休んでから次の週末にでも行ければいいかと思っていたのでしたが、そうは問屋が卸さずでした。
こうなると、むしろ草津白根山のエネルギーをマックス帯電したからこそ行くのかと割り切るしかありません。
鹿島神宮と香取神宮は、昔から利根川水系と関東の地を護ってきました。
とても由緒ある神社で、『延喜式』の神名帳には伊勢神宮と並んでこの二社だけが神宮の神号で記されて
いたそうです。
創建は古く、いずれも二千六百年以上前と言われています。
鹿島の御祭神である建御雷神(タケミカヅチノカミ)と、香取の御祭神である経津主神(フツヌシノカミ)
は、天照大御神の命を受けて大国主命に国譲りの交渉に赴いた神様です。
神話にも書かれていますように、最初は話し合いで解決を図り、最後は剣を置いて力くらべで説得を試み
ました。
これを両軍同士のせめぎ合いと見ることも出来ますが、ここでは神話に描写されたその精神性、心の
内面性に着目したいと思います。
力くらべなどと言うと平和な響きに聞こえますが、昔の相撲が殴ったり蹴ったりするのも有りだったように、
恐らくパンクラチオンルールのようなものだったのではないかと想像します。
但し、目や急所を突いたり、背骨や後頭部を折りにかかるような凄惨なものではなく、子供の清らかな心
での喧嘩と同じものだったでしょう。
卑怯なことなど、しようとも思わない。
武器を捨て、素っ裸になって己の身一つだけでぶつかり合う。
喧嘩に限らず戦さもそうですが、己の我欲のために闘う場合と、己の損得に関係なく公や義、あるいは
相手のために闘う場合とでは、自ずと魂の定まり方が違ってきます。
物理的な優劣というのとは明らかに違う、魂の部分での大きさ、言い換えればどれほど濁らずクリアで
在るか、天地と一体になっているか。
そうしたものは、お互いの心に響き合います。
相手を打ち伏せたとか、そのような見た目だけの短絡的な判断ではなく、心にじんわりと感じるものです。
あぁ、到底かなわない、なんて大きな心なんだろう。
そのような気持ちが心の底から湧き上がるわけです。
見た目の結果だけを追おうとする時、その心は私利私欲に染まっています。
姿形としては優勢であろうとも、心は自分だけの世界となっており、そこには天地と断絶した単なる一個体
があるだけとなります。
互いの心に響くものなど、カケラもありません。
力でねじ伏せるという、見た目の結果だけを100%追いかける行為には、人としての崇高さや深淵さなど
皆無で、そこには軽薄さしか残りません。
仮に、形としての勝ちを良しとするならば、人間よりも遥かに力の強い野獣の方が偉いのかという話になって
しまいます。
お互いが私欲を捨てて、透明な心でぶつかり合った時に初めて、人としての深淵な心に触れることが
できるのです。
それこそは、現代の武道にも通じるものです。
スポーツというのは、決められたルールの中での勝ち負けが基本のため、結果を求めがちになってしまい
ます。
しかし、武道では勝ち負けというのはあくまで単なる結果でしかなく、それよりも大事なことはその過程、
その最中であり、その心の清らかさにあるわけです。
つまり、スポーツとは心の向いている方向が根本的に異なるということです。
結果の方などには向いていない。
途中途中の感覚を追っている。
気づいたら勝っていた、あるいは負けていた。それだけです。
だから武道におけるガッツポーズなどというのはあり得ないのです。
それは「結果」という上っ面しか追っていない心の現れであり、私利私欲に囚われた自我の現れであるとして、
そもそもの一歩目から明後日の方向を向いてしまっていることになります。
これは武道が、スポーツとは遥かに遠い異質のもので、むしろ座禅や禅行などに近いものであることを意味
しています。
肉体を使い、自他が対峙するというスタイルを見るとスポーツに近いのではないかと思ってしまいがちですが、
実際は、料理や読書がスポーツとは全く違うのと同じくらいに、別ものであるわけです。
そもそもそこには、勝ち負けという概念がありません。
自分に克つ(かつ)とか、そういうことですらありません。
心の透明性を追い、天地との一体化を目指すだけです。
ですから、ガッツポーズなどという発想自体あり得ません。
ガッツポーズをしてはいけない理由として、対戦相手への礼儀だとか、惻隠だとか、感謝だとか、そういう
優等生的な理屈を並べること自体、すでにピントがズレたものであるわけです。
国譲りを見ますと、そこには同じように心の透明性が感じられます。
だからこそ鹿島神宮と香取神宮の神様は、古来、武道の神様として篤く信奉されてきたのだと思います。
神話では他にも、素戔嗚尊(スサノヲノミコト)が天照大御神のところへ攻めに来たと疑いをかけられた際、
その誤解を解くために互いの持ち物を砕いて吹いて、その清らかさを確認し合う、「誓約(うけひ)」という
ものがありましたが、これもまたの我欲のない濁り無さを確かめ合うものだったと言えます。
「うけひ」にも、国譲りにも、武道にも、日本人が知らず知らずのうちに追い求める天地人合一の清らかな
精神性が、共通して流れているように感じられます。
「うけひ」について、もう少し触れてみたいと思います。
この時に何をもって勝ちとするのか事前に決めていなかったのがミスだと言われますが、古代の清らかな
心の日本人からすれば、それは言わずもがなであったのではないかと思います。
天照大御神が、須佐之男命の刀を噛み砕いて吹いたら三女神が現れました。
素戔嗚尊が、天照大御神の玉を噛み砕いて吹いたら四神が現れました。
つまり、そもそもが勝ち負けという次元のものではなく、いかに互いが濁りなき清らかな心にあるかを確認し
合うものだったということです。
そうなると、そのあとの場面として一人で大はしゃぎする素戔嗚尊の行動が理解に苦しむところですが、それも
後世の人間考えで、「うけひ」を勝ち負けの勝負だと解釈してしまい、無理な話を付け足した結果だと考えれば
辻褄が合います。
さらに、そのあと素戔嗚尊が高天原で乱暴狼藉の限りを尽くす場面に至っては、完全にストーリーが無茶苦茶
だと言わざるを得ません。
私も子供心に、この部分が全く受け入れられずにモヤモヤして気持ち悪かったことを覚えています。
この場面を思うと、今でも心の底がドンヨリとイヤな気持ちになります。
この部分は、悪意をもった改竄を感じずにはいられません。
素戔嗚尊は凄い神様です。
スサまじい神様です。
益荒男(ますらお)の象徴です。
関東というのは、素戔嗚尊系が数多く祀られた土地です。
武蔵国一之宮である氷川神社の系統だけでも200社あると言いますし、大国主命をご祭神としている
神社を入れたらさらに凄い数となります。
出雲族の末裔が、都が栄える前の片田舎に大勢流れて来たとも言われますが、そうした歴史以上に、
結果として素戔嗚尊系統が多く祀られた土地が、この国の中心として栄えているということが、非常に
意味深いことだと思います。
この天地宇宙は、のっぺりした単一のものではなく、陰陽の濃淡に彩られています。
あらゆるエネルギーの循環が、陰陽となって現れています。
天照大御神は女性のエネルギーであり、和魂(にぎみたま)のエネルギーです。
素戔嗚尊は男性のエネルギーであり、荒魂(あらみたま)のエネルギーです。
和魂のエネルギーである天照大御神の中にもさらにまた和魂と荒魂がありますし、荒魂のエネルギーで
ある素戔嗚尊の中にもさらにまた和魂と荒魂があります。
エネルギーの流れるところに陰陽が現れます。
極大から極小に至るまで、この天地宇宙はエネルギーの循環で充ち満ちているということです。
陰と陽がそうであるように、和魂や荒魂もまた、本来一つのものであり裏表です。
どちらがより良いという次元のものではありません。
結果としての現れに過ぎず、互いに互いがなければ元より存在すらしていません。
私たちも、男性は、表の男性性の裏に女性性があり、女性は、表の女性性の裏に男性性があります。
どちらか一方ではなく、その循環とバランスによって、力強く生かされています。
プラス極とマイナス極というのは、磁力線が流れているから存在するわけです。
プラスとマイナスがあるから磁力が流れているのではありません。
流れることによって、プラスとマイナスというものが生じるのです。
流れが無ければ、そもそもプラスもマイナスも存在しないわけです。
私たちだけでなく、天地宇宙そのものも、そこに存在するということは、そこにエネルギーの循環が
あるということです。
循環が発現したものが、存在であるわけです。
言い換えれば、陰陽のエネルギーというのは、私たちが今ここに存在できている証し(あかし)なのです。
(つづく)

湯あたりというのは、詰まるところエネルギー過多の状態です。
熱が出たり、頭痛がしたり、頭がクラクラしたり、気持ち悪かったりして食欲もありません。
こうなると半病人ですから、ひたすら寝て自然なチューニングを待つことになります。
それを見越して最終日は自宅に戻ったのですが、目論見ハズれ、急遽茨城に行くことになりました。
まだ大阪に住んでいた頃、今年は東京に戻らないとマズいという感覚とともに、行くべき場所が何ヶ所か
浮かびました。
箱根もその一つだったわけですが、同じように鹿島神宮と香取神宮が来てました。
箱根に行ったあとは流れとして南九州が先に来て、そのあとは湯あたりでシンドイ体調だったりして、
さて少し休んでから次の週末にでも行ければいいかと思っていたのでしたが、そうは問屋が卸さずでした。
こうなると、むしろ草津白根山のエネルギーをマックス帯電したからこそ行くのかと割り切るしかありません。
鹿島神宮と香取神宮は、昔から利根川水系と関東の地を護ってきました。
とても由緒ある神社で、『延喜式』の神名帳には伊勢神宮と並んでこの二社だけが神宮の神号で記されて
いたそうです。
創建は古く、いずれも二千六百年以上前と言われています。
鹿島の御祭神である建御雷神(タケミカヅチノカミ)と、香取の御祭神である経津主神(フツヌシノカミ)
は、天照大御神の命を受けて大国主命に国譲りの交渉に赴いた神様です。
神話にも書かれていますように、最初は話し合いで解決を図り、最後は剣を置いて力くらべで説得を試み
ました。
これを両軍同士のせめぎ合いと見ることも出来ますが、ここでは神話に描写されたその精神性、心の
内面性に着目したいと思います。
力くらべなどと言うと平和な響きに聞こえますが、昔の相撲が殴ったり蹴ったりするのも有りだったように、
恐らくパンクラチオンルールのようなものだったのではないかと想像します。
但し、目や急所を突いたり、背骨や後頭部を折りにかかるような凄惨なものではなく、子供の清らかな心
での喧嘩と同じものだったでしょう。
卑怯なことなど、しようとも思わない。
武器を捨て、素っ裸になって己の身一つだけでぶつかり合う。
喧嘩に限らず戦さもそうですが、己の我欲のために闘う場合と、己の損得に関係なく公や義、あるいは
相手のために闘う場合とでは、自ずと魂の定まり方が違ってきます。
物理的な優劣というのとは明らかに違う、魂の部分での大きさ、言い換えればどれほど濁らずクリアで
在るか、天地と一体になっているか。
そうしたものは、お互いの心に響き合います。
相手を打ち伏せたとか、そのような見た目だけの短絡的な判断ではなく、心にじんわりと感じるものです。
あぁ、到底かなわない、なんて大きな心なんだろう。
そのような気持ちが心の底から湧き上がるわけです。
見た目の結果だけを追おうとする時、その心は私利私欲に染まっています。
姿形としては優勢であろうとも、心は自分だけの世界となっており、そこには天地と断絶した単なる一個体
があるだけとなります。
互いの心に響くものなど、カケラもありません。
力でねじ伏せるという、見た目の結果だけを100%追いかける行為には、人としての崇高さや深淵さなど
皆無で、そこには軽薄さしか残りません。
仮に、形としての勝ちを良しとするならば、人間よりも遥かに力の強い野獣の方が偉いのかという話になって
しまいます。
お互いが私欲を捨てて、透明な心でぶつかり合った時に初めて、人としての深淵な心に触れることが
できるのです。
それこそは、現代の武道にも通じるものです。
スポーツというのは、決められたルールの中での勝ち負けが基本のため、結果を求めがちになってしまい
ます。
しかし、武道では勝ち負けというのはあくまで単なる結果でしかなく、それよりも大事なことはその過程、
その最中であり、その心の清らかさにあるわけです。
つまり、スポーツとは心の向いている方向が根本的に異なるということです。
結果の方などには向いていない。
途中途中の感覚を追っている。
気づいたら勝っていた、あるいは負けていた。それだけです。
だから武道におけるガッツポーズなどというのはあり得ないのです。
それは「結果」という上っ面しか追っていない心の現れであり、私利私欲に囚われた自我の現れであるとして、
そもそもの一歩目から明後日の方向を向いてしまっていることになります。
これは武道が、スポーツとは遥かに遠い異質のもので、むしろ座禅や禅行などに近いものであることを意味
しています。
肉体を使い、自他が対峙するというスタイルを見るとスポーツに近いのではないかと思ってしまいがちですが、
実際は、料理や読書がスポーツとは全く違うのと同じくらいに、別ものであるわけです。
そもそもそこには、勝ち負けという概念がありません。
自分に克つ(かつ)とか、そういうことですらありません。
心の透明性を追い、天地との一体化を目指すだけです。
ですから、ガッツポーズなどという発想自体あり得ません。
ガッツポーズをしてはいけない理由として、対戦相手への礼儀だとか、惻隠だとか、感謝だとか、そういう
優等生的な理屈を並べること自体、すでにピントがズレたものであるわけです。
国譲りを見ますと、そこには同じように心の透明性が感じられます。
だからこそ鹿島神宮と香取神宮の神様は、古来、武道の神様として篤く信奉されてきたのだと思います。
神話では他にも、素戔嗚尊(スサノヲノミコト)が天照大御神のところへ攻めに来たと疑いをかけられた際、
その誤解を解くために互いの持ち物を砕いて吹いて、その清らかさを確認し合う、「誓約(うけひ)」という
ものがありましたが、これもまたの我欲のない濁り無さを確かめ合うものだったと言えます。
「うけひ」にも、国譲りにも、武道にも、日本人が知らず知らずのうちに追い求める天地人合一の清らかな
精神性が、共通して流れているように感じられます。
「うけひ」について、もう少し触れてみたいと思います。
この時に何をもって勝ちとするのか事前に決めていなかったのがミスだと言われますが、古代の清らかな
心の日本人からすれば、それは言わずもがなであったのではないかと思います。
天照大御神が、須佐之男命の刀を噛み砕いて吹いたら三女神が現れました。
素戔嗚尊が、天照大御神の玉を噛み砕いて吹いたら四神が現れました。
つまり、そもそもが勝ち負けという次元のものではなく、いかに互いが濁りなき清らかな心にあるかを確認し
合うものだったということです。
そうなると、そのあとの場面として一人で大はしゃぎする素戔嗚尊の行動が理解に苦しむところですが、それも
後世の人間考えで、「うけひ」を勝ち負けの勝負だと解釈してしまい、無理な話を付け足した結果だと考えれば
辻褄が合います。
さらに、そのあと素戔嗚尊が高天原で乱暴狼藉の限りを尽くす場面に至っては、完全にストーリーが無茶苦茶
だと言わざるを得ません。
私も子供心に、この部分が全く受け入れられずにモヤモヤして気持ち悪かったことを覚えています。
この場面を思うと、今でも心の底がドンヨリとイヤな気持ちになります。
この部分は、悪意をもった改竄を感じずにはいられません。
素戔嗚尊は凄い神様です。
スサまじい神様です。
益荒男(ますらお)の象徴です。
関東というのは、素戔嗚尊系が数多く祀られた土地です。
武蔵国一之宮である氷川神社の系統だけでも200社あると言いますし、大国主命をご祭神としている
神社を入れたらさらに凄い数となります。
出雲族の末裔が、都が栄える前の片田舎に大勢流れて来たとも言われますが、そうした歴史以上に、
結果として素戔嗚尊系統が多く祀られた土地が、この国の中心として栄えているということが、非常に
意味深いことだと思います。
この天地宇宙は、のっぺりした単一のものではなく、陰陽の濃淡に彩られています。
あらゆるエネルギーの循環が、陰陽となって現れています。
天照大御神は女性のエネルギーであり、和魂(にぎみたま)のエネルギーです。
素戔嗚尊は男性のエネルギーであり、荒魂(あらみたま)のエネルギーです。
和魂のエネルギーである天照大御神の中にもさらにまた和魂と荒魂がありますし、荒魂のエネルギーで
ある素戔嗚尊の中にもさらにまた和魂と荒魂があります。
エネルギーの流れるところに陰陽が現れます。
極大から極小に至るまで、この天地宇宙はエネルギーの循環で充ち満ちているということです。
陰と陽がそうであるように、和魂や荒魂もまた、本来一つのものであり裏表です。
どちらがより良いという次元のものではありません。
結果としての現れに過ぎず、互いに互いがなければ元より存在すらしていません。
私たちも、男性は、表の男性性の裏に女性性があり、女性は、表の女性性の裏に男性性があります。
どちらか一方ではなく、その循環とバランスによって、力強く生かされています。
プラス極とマイナス極というのは、磁力線が流れているから存在するわけです。
プラスとマイナスがあるから磁力が流れているのではありません。
流れることによって、プラスとマイナスというものが生じるのです。
流れが無ければ、そもそもプラスもマイナスも存在しないわけです。
私たちだけでなく、天地宇宙そのものも、そこに存在するということは、そこにエネルギーの循環が
あるということです。
循環が発現したものが、存在であるわけです。
言い換えれば、陰陽のエネルギーというのは、私たちが今ここに存在できている証し(あかし)なのです。
(つづく)