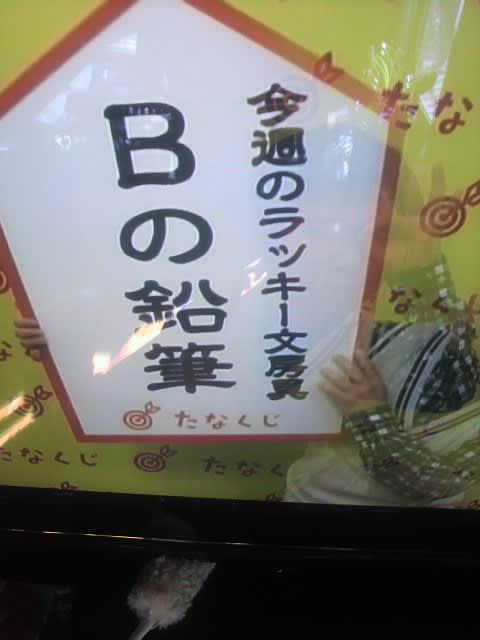なんか最近キャパの名前をまた聞くようになったな、と思ったら、写真展があるらしいですね。学生時代だか「ちょっとピンぼけ」を読んだことがあるようで、写真が凄いというより、文章が何とも面白い人であるという印象は残っている。戦場写真家という職業がどうこうという気は無いが、結局戦場で死んだという事実からして、なんだかやっぱり少し変わった人で無いと務まらないものかもしれないとは思う。
だいぶ後、日本でも戦場カメラマンという有名な人がたくさんいるようだと知ったが、やはり需要があるということでもあるのだろう。批判しているのではなく、そういう世の中だからやっていけるというのはちょっと複雑な気分だ。
キャパが架空というか、二人で一人だったというのは知らなかった。もちろん、もう一人のゲルダ・タロー(岡本太郎から取った名前らしい)も写真家として成り立っている面もあり、しかし名義が混ざったまま人々に知られている写真も多いのだという。さらにその背景も、知られていない事実がいろいろあるらしい。興味のある人は実地に当たって欲しいが、なかなか面白いものである。伝説の人は、やはりいろいろつくられる素地がある訳だ。
そういう職業があって、さらにそういう仕事に憧れて、つづいて伝説になりたいというか、それでもいいからやってみたいというような、いわば名前を残したいとか、いや、写真そのものを残したいというような欲求があるというのが、そのまま人間の面白さということは言えるかもしれない。いわゆる戦争というものを写真で描く事の意味はいろいろあろうが(あえてそういうけど)、なんと言ってもそれは人間の興味がそうさせているということである。さらに名前を売るためであるとか、生活も成り立たせる必要がある訳で、そういう内面も含めて、ロバート・キャパという存在は、伝説以上の存在となっているのかもしれない。
いまだにどこかで内戦をやっているところは絶えない訳だし、将来的に終わりが来るものかは不透明だし、あるいは平和というものを保障するためとして、一定の暴力そのものは、結果的にその担保になっている現実がある訳だ。興味が無くなると却って危ないことになるということも言える訳で、要はそのバランス感覚なのかもしれない。自分が死なないでいられることは、誰かの死によって成り立っているかもしれないのだ。
もちろん、表面的には何の関係も無いお話かもしれない。そのような考え方自体がナンセンスかもしれない。キャパは戦場に行き、死んでしまっただけなのかもしれない。
しかし多くの人々は、その意味をやはり探ろうとする訳だ。ちょっと胡散臭いところもあるが、しかしそれこそが人間としての真実をいちばん伝えているということにもなる。いわゆるキャパ的なものというのは、どこかに持っている必要が、僕らにはあるのだろうという気がする。