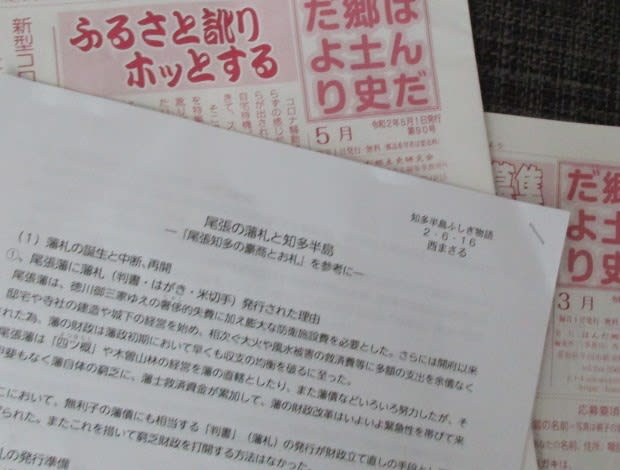講座、3か月のお休みでしたが、6月から再開しました。
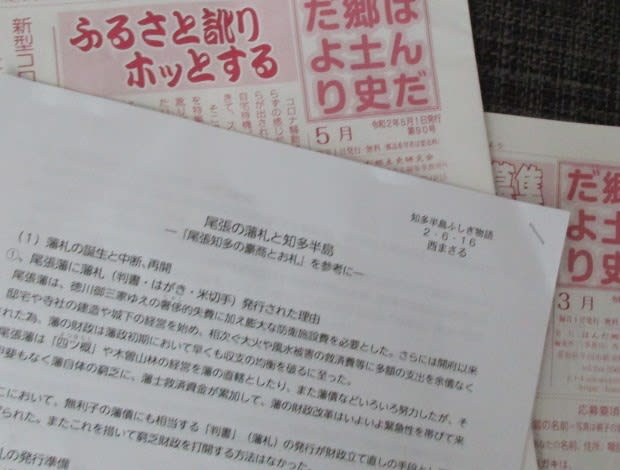
今日のテーマは「尾張藩の藩札と知多半島」
尾張藩は徳川御三家の筆頭、直系ですから権力はありましたが
経済面では他の藩と同じく豊かとは言えずやりくり算段していました
そこで「四つ概」など財政改革で窮乏打開を計りました。
「四つ概」?初めて聞きましたし、先生の説明だけでは理解できませんでした。
藩の知恵者が考え出したのでしょう。
帰宅して今一度ネットで調べたりメモを見て漸く半分理解しました。以下ネット(尾張藩)から拝借。
四つ概の方法は、簡単にいうと従来の村高が一〇〇石であると、
免相は六つ(六〇パーセント)であるから年貢米は六〇石となる。
この六〇石の年貢収入を減らさないで、免相を四つにするには村高を延ばさなければならない。
それには一〇〇石の村高を一五〇石に延して、免相を四つにすると年貢米は六〇石となる。
このように従来の年貢米が、一〇分の四になるように変更したのである。
元の村高一〇〇石を元高といい、一五〇石に延した高を概高という。
年貢米(税金) 公・6 民・4 を → 公・4 民・6 にしました。
?一見民優遇のようにますが、村高100石を150石とし、結果収める税金の額は同じ?
未だに良く理解できていません。
「四つ概」、藩と農民どちらに利が多かったのでしょう?
私が衰えるのは体力だけでなく、理解力もまた甚だしく衰えました。
受講することに意義があることに致しました。















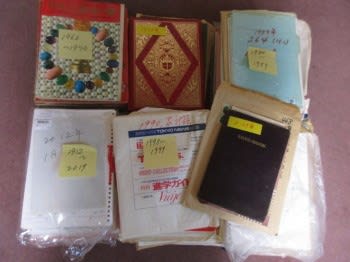









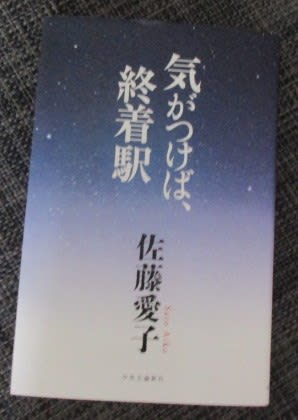 長年にわたり某婦人雑誌に連載された随筆です
長年にわたり某婦人雑誌に連載された随筆です 「山帰来」と言う銘菓、頂きました。
「山帰来」と言う銘菓、頂きました。