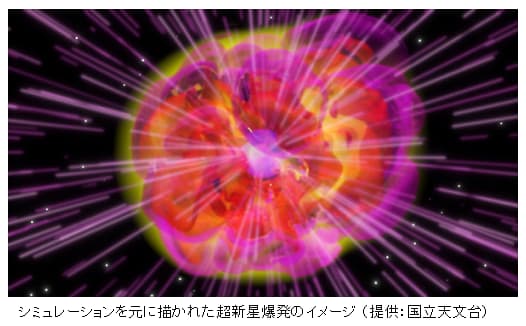ゼロ・グラビティ
連休を利用して、映画「ゼロ・グラビティ」をブルーレイで見ることができた。圧倒的な宇宙の映像美と迫力に感動した。日本でも大ヒットした「ゼロ・グラビティ」。映画関係者でさえ「どうやって撮影したのかわからない」と語るほど驚異的な撮影が行われた。
映画監督のクエンティン・タランティーノは本作を2013年度の映画トップ10に選出した。スティーヴン・スピルバーグは「言葉が出なかったよ。君たち、一体何をやってたんだ?」とジョージ・クルーニーにコメントし、ジェームズ・キャメロンは「これは史上最も優れた宇宙の映像美で創り上げた、史上最高のスペース・エンターテイメント」、「キュアロンとサンドラは、無重力空間で生き延びるため闘う女性の姿を完璧に創り上げた」と語っている。
アポロ11号の乗組員であったバズ・オルドリンは本作の描写が現実の宇宙空間にかなり近いものであることを認めたうえで、称賛している。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/
引用元 Wikipedia: 宇宙服 マイナビニュース: NASAの次世代宇宙服「Z-2」 ピア映画生活:驚異の映像はこうして生まれた「ゼロ・グラビティ」メイキング映像公開
 |
スペースウォーク |
| クリエーター情報なし | |
| 株式会社ブックブライト |
 |
ゼロ・グラビティ ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産)2枚組 [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |