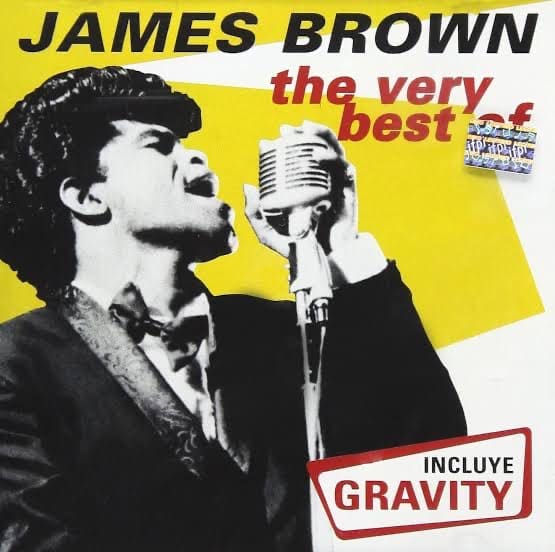2023年1月16日(月)

#425 井上陽水「クラムチャウダー」(フォーライフ 35KD-55)
シンガーソングライター、井上陽水のライブ・アルバム。86年リリース。東京渋谷・NHKホールにて収録。
井上陽水はこれまでに5枚のライブ盤をリリースしているが、これはその4枚目にあたる。
井上陽水については、筆者はあまり語るべき言葉を持っていない。
70年代、彼がデビューしてすぐは注目していたが、ヒットが出て売れっ子になると、たちまち興味を失ってしまった。
もう一度聴く気になったのは、80年代に入り、他アーティストへの楽曲提供や自身のヒット曲によりようやく第一線に復帰したあたりから。それもたまにベスト・アルバムを買う程度の「薄い」ファンだった。
だから、今日はざっくりとした感想のみを語ることにしよう。
オープニングは、スーパー・ベストセラー「氷の世界」所収の「帰れないふたり」。
陽水と忌野清志郎の共作。ふたりの親交はデビューの頃からだそうで、それが実を結んだのがこの曲だ。
あまりにも美しい歌詞とメロディ、幻想的なサウンド。なんの文句のつけようもない。
「ミスコンテスト」は78年のシングル・ヒット。エキゾチックなメロディは、以降「なぜか上海」「ジェラシー」といった曲群に引き継がれていく。
歌詞にも、かつてあったような身辺雑記、私小説的な要素が消え、社会観察、そして少し皮肉めいた視線の作品が増えてくる。
「娘がねじれる時」もそのタイプの一曲。79年のアルバム「スニーカーダンサー」所収。毒のある歌詞で、リスナーをかき回してくれる。
シニカルで、シュールで、時にはナンセンスな歌詞。
それが陽水の個性として認知されるようになる。
「ミスキャスト」もその流れにある。82年、沢田研二のアルバム「ミスキャスト」に、全曲を提供して話題となったが、これはそのタイトル・チューン。
人間の悪意を鋭くえぐる歌詞。ここまで不信感に満ちた言葉を吐くに至ったのは、売れてしまったが故に世間の醜さ、酷薄さと直面した彼の経験がなせる技であろう。
「新しいラプソディー」は、それまでの数曲の毒を洗い流すような、清新なナンバー。ニュー・シングルとして出したばかりで、おそらく初お披露目だったはず。陽水の澄んだ声は、やはりこういう曲に一番合う。
「灰色の指先」は、78年のアルバム「”white”」所収のナンバー。陰キャなプレス工の青年の物語。
物悲しいメロディのジャズ・バラード。陽水が麻薬で逮捕され、執行猶予中に発表された頃の曲だからか、厭世的な色が濃い。聴く者の心にずしりと来る。
「ジャストフィット」は激しいロック・ナンバー。ギターの大村憲司は、このコンサート全編のアレンジも担当しているのだが、この曲ではまるで堰が切れたかのようなパッショネートな演奏でリスナーを圧倒する。
大村は98年に49歳の若さで亡くなっている。日本を代表するギタリストのひとりであったのに、実に惜しい。
そんな彼のハンパない実力が伺えるのが、このコンサートのハイレベルな編曲だ。
高水健司のフレットレスベースのソロから始まるのは「ワインレッドの心」。一時期陽水のバックを務めていた安全地帯のために歌詞を書いた、大ヒット曲(作曲は玉置浩二)。
陽水の歌は、玉置のエモーショナルなそれとは一味違っていて、クールな中にも秘めた熱さを感じさせる。
生み出す曲が優れているだけでなく、単にシンガーとしても底知れない実力を持つことが、この曲だけでもよく分かる。
フォーライフ創設の四人衆の中でも、ずば抜けた歌のうまさで、頭ひとつ抜けた存在であり続けた陽水。
ラストは「結詞」。のちに(92年)シングル化されている隠れた名曲。終幕にふさわしい、ひたすら美しいスローバラードだ。
アレンジの素晴らしさ、そして陽水の歌唱の見事さに、賞賛の言葉が見つからない。
実際のライブはアルバムの2倍の尺があるのだが、残りをどうしても聴きたいかたは、DVD化されていないそうなので、ビデオテープを中古で探して観ていただきたい。
クールと熱狂。いわば相反した要素を包含しながら、見事にひとつにまとまったライブの記録。
スタジオ録音同様、陽水の歌声は一分の曇りもない。感服のひと言だ。
<独断評価>★★★★
シンガーソングライター、井上陽水のライブ・アルバム。86年リリース。東京渋谷・NHKホールにて収録。
井上陽水はこれまでに5枚のライブ盤をリリースしているが、これはその4枚目にあたる。
井上陽水については、筆者はあまり語るべき言葉を持っていない。
70年代、彼がデビューしてすぐは注目していたが、ヒットが出て売れっ子になると、たちまち興味を失ってしまった。
もう一度聴く気になったのは、80年代に入り、他アーティストへの楽曲提供や自身のヒット曲によりようやく第一線に復帰したあたりから。それもたまにベスト・アルバムを買う程度の「薄い」ファンだった。
だから、今日はざっくりとした感想のみを語ることにしよう。
オープニングは、スーパー・ベストセラー「氷の世界」所収の「帰れないふたり」。
陽水と忌野清志郎の共作。ふたりの親交はデビューの頃からだそうで、それが実を結んだのがこの曲だ。
あまりにも美しい歌詞とメロディ、幻想的なサウンド。なんの文句のつけようもない。
「ミスコンテスト」は78年のシングル・ヒット。エキゾチックなメロディは、以降「なぜか上海」「ジェラシー」といった曲群に引き継がれていく。
歌詞にも、かつてあったような身辺雑記、私小説的な要素が消え、社会観察、そして少し皮肉めいた視線の作品が増えてくる。
「娘がねじれる時」もそのタイプの一曲。79年のアルバム「スニーカーダンサー」所収。毒のある歌詞で、リスナーをかき回してくれる。
シニカルで、シュールで、時にはナンセンスな歌詞。
それが陽水の個性として認知されるようになる。
「ミスキャスト」もその流れにある。82年、沢田研二のアルバム「ミスキャスト」に、全曲を提供して話題となったが、これはそのタイトル・チューン。
人間の悪意を鋭くえぐる歌詞。ここまで不信感に満ちた言葉を吐くに至ったのは、売れてしまったが故に世間の醜さ、酷薄さと直面した彼の経験がなせる技であろう。
「新しいラプソディー」は、それまでの数曲の毒を洗い流すような、清新なナンバー。ニュー・シングルとして出したばかりで、おそらく初お披露目だったはず。陽水の澄んだ声は、やはりこういう曲に一番合う。
「灰色の指先」は、78年のアルバム「”white”」所収のナンバー。陰キャなプレス工の青年の物語。
物悲しいメロディのジャズ・バラード。陽水が麻薬で逮捕され、執行猶予中に発表された頃の曲だからか、厭世的な色が濃い。聴く者の心にずしりと来る。
「ジャストフィット」は激しいロック・ナンバー。ギターの大村憲司は、このコンサート全編のアレンジも担当しているのだが、この曲ではまるで堰が切れたかのようなパッショネートな演奏でリスナーを圧倒する。
大村は98年に49歳の若さで亡くなっている。日本を代表するギタリストのひとりであったのに、実に惜しい。
そんな彼のハンパない実力が伺えるのが、このコンサートのハイレベルな編曲だ。
高水健司のフレットレスベースのソロから始まるのは「ワインレッドの心」。一時期陽水のバックを務めていた安全地帯のために歌詞を書いた、大ヒット曲(作曲は玉置浩二)。
陽水の歌は、玉置のエモーショナルなそれとは一味違っていて、クールな中にも秘めた熱さを感じさせる。
生み出す曲が優れているだけでなく、単にシンガーとしても底知れない実力を持つことが、この曲だけでもよく分かる。
フォーライフ創設の四人衆の中でも、ずば抜けた歌のうまさで、頭ひとつ抜けた存在であり続けた陽水。
ラストは「結詞」。のちに(92年)シングル化されている隠れた名曲。終幕にふさわしい、ひたすら美しいスローバラードだ。
アレンジの素晴らしさ、そして陽水の歌唱の見事さに、賞賛の言葉が見つからない。
実際のライブはアルバムの2倍の尺があるのだが、残りをどうしても聴きたいかたは、DVD化されていないそうなので、ビデオテープを中古で探して観ていただきたい。
クールと熱狂。いわば相反した要素を包含しながら、見事にひとつにまとまったライブの記録。
スタジオ録音同様、陽水の歌声は一分の曇りもない。感服のひと言だ。
<独断評価>★★★★