「江戸参府旅行日記」 訳者・斎藤信 東洋文庫 昭和52年発行
第十一章 浜松から江戸までの旅
1691年(元禄4)3月
3月10日
日の出に出発、午前中に吉原まで、午後は三島までの道である。
清見に着いた、奥津という小さな町からさして遠くない200戸の村であって、
海岸の砂にたびたび海水をかけ、それを煮つめて良い塩が作られる。
蒲原までの間の村々では耕地がほとんどない。

(国道1号線、奥津川)

(奥津川川越跡)

(東海道五十三次17・興津宿)
馬に乗っていたわれわれは、奥津からはまた駕籠に乗り換えて、最初に早い流れを渡り、
螺旋階段を登るように苦労して薩埵峠の山地を越えた。

(薩埵峠・・・・この時、富士山が見えるまで2時間待ちました)

(東海道五十三次16・由比宿)

(昭和32年前後の由比ふきん)
由比の村までかつがれて進んだ。
そこからまた馬に乗り換えて大きな蒲原の村に着いた。

(東海道五十三次15・蒲原宿)
1里半で大きくて流れが急な富士川に着いた。
川幅いっぱいに水があるのでなく、二つに分かれて流れており、中洲には露店が立っているのが見えた。
一方は歩いて渡ることができたが、もう一方は歩いて渡るのは危険で、平底の舟でしか割れなかった。
川を渡ってから、再び馬に乗ってたくさんの村々を過ぎた。
昼の1時には吉原という小さな町に着いた。

(東海道五十三次14・吉原宿)
われわれの全行程中で、富士山はこの辺りから一番近いところにあった。
富士山は旅行中、われわれの道標になり、地図を作るにあたって一つの基準として役立った。
その姿は円錐形で左右の形が美しく、堂々としていて、草や木はまったく生えていないが、世界中でいちばん美しい山と言うのは当然である。

(東海道五十三次13・原宿)
人々は登るのに三日かかるが、
下りるにはたった三時間しかかからない。
それは、下る場合にはアシとか藁で作った籠を利用し、腰の下にこれを結び付けて、
夏ならば砂の、冬ならば雪の上を、これで滑り下るためである。
日本の詩人や画家がこの山の美しさをいくらほめたたえ、うまく描いても、それで十分ということはない。
吉原から半里のところにある元吉原で昼食をとったが、
子供たちが群れを成して近づいてきて、前方20~30歩のところでとんぼ返りをしながら、輪を描いて駆け回り、施し物をもらおうとした。
子供たちに小銭をたくさん投げてやった。彼らはぶつかりあってつかもうとして、大変面白かった。
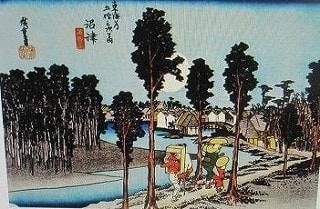
(東海道五十三次12・沼津宿)
沼津という小さな町で夜になってしまい、
残る1時間半の真っ暗な道を、三島まで行かねばならなかった。

(東海道五十三次11・三島宿)
第十一章 浜松から江戸までの旅
1691年(元禄4)3月
3月10日
日の出に出発、午前中に吉原まで、午後は三島までの道である。
清見に着いた、奥津という小さな町からさして遠くない200戸の村であって、
海岸の砂にたびたび海水をかけ、それを煮つめて良い塩が作られる。
蒲原までの間の村々では耕地がほとんどない。

(国道1号線、奥津川)

(奥津川川越跡)

(東海道五十三次17・興津宿)
馬に乗っていたわれわれは、奥津からはまた駕籠に乗り換えて、最初に早い流れを渡り、
螺旋階段を登るように苦労して薩埵峠の山地を越えた。

(薩埵峠・・・・この時、富士山が見えるまで2時間待ちました)

(東海道五十三次16・由比宿)

(昭和32年前後の由比ふきん)
由比の村までかつがれて進んだ。
そこからまた馬に乗り換えて大きな蒲原の村に着いた。

(東海道五十三次15・蒲原宿)
1里半で大きくて流れが急な富士川に着いた。
川幅いっぱいに水があるのでなく、二つに分かれて流れており、中洲には露店が立っているのが見えた。
一方は歩いて渡ることができたが、もう一方は歩いて渡るのは危険で、平底の舟でしか割れなかった。
川を渡ってから、再び馬に乗ってたくさんの村々を過ぎた。
昼の1時には吉原という小さな町に着いた。

(東海道五十三次14・吉原宿)
われわれの全行程中で、富士山はこの辺りから一番近いところにあった。
富士山は旅行中、われわれの道標になり、地図を作るにあたって一つの基準として役立った。
その姿は円錐形で左右の形が美しく、堂々としていて、草や木はまったく生えていないが、世界中でいちばん美しい山と言うのは当然である。

(東海道五十三次13・原宿)
人々は登るのに三日かかるが、
下りるにはたった三時間しかかからない。
それは、下る場合にはアシとか藁で作った籠を利用し、腰の下にこれを結び付けて、
夏ならば砂の、冬ならば雪の上を、これで滑り下るためである。
日本の詩人や画家がこの山の美しさをいくらほめたたえ、うまく描いても、それで十分ということはない。
吉原から半里のところにある元吉原で昼食をとったが、
子供たちが群れを成して近づいてきて、前方20~30歩のところでとんぼ返りをしながら、輪を描いて駆け回り、施し物をもらおうとした。
子供たちに小銭をたくさん投げてやった。彼らはぶつかりあってつかもうとして、大変面白かった。
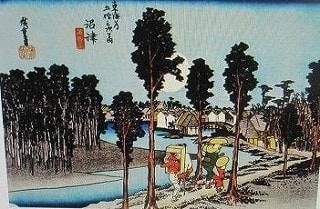
(東海道五十三次12・沼津宿)
沼津という小さな町で夜になってしまい、
残る1時間半の真っ暗な道を、三島まで行かねばならなかった。

(東海道五十三次11・三島宿)

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます