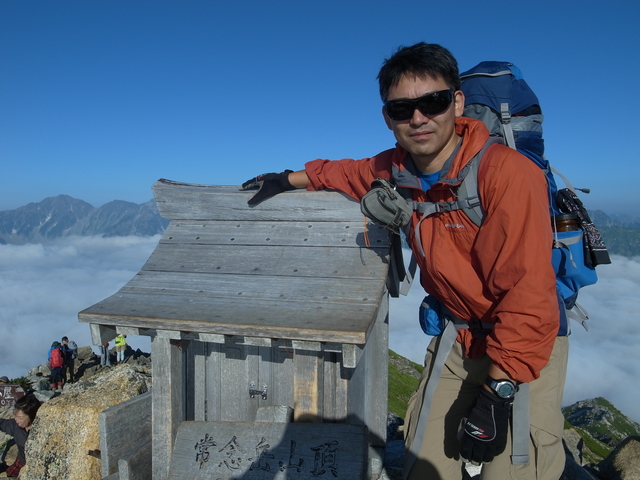古代代エジプトでは減価するお金のシステムがあった。当時のエジプトの農民は穀物を収穫すると大きな倉庫に保管してもらっていた。その際、預り証を発行してもらっていた。その預り証はお金としても使われていた。
倉庫の穀物はねずみが食べたり、カビが生えたりする。その場合、預り証は穀物にあわせて減価する。すなわち、お金としての預り証は減価するのだ。
農民はお金をたくさん貯めておいても損だから、土地の改良や灌漑施設の整備などの長期的な利益をもたらすものに投資する。このようにナイル川流域は豊かな穀物地帯になった。
しかし、ローマ人がエジプトを支配し、利子のつくお金のシステムを採用してからエジプトの繁栄は終わる。
同様に1150年から1350年の中世ヨーロッパにも減価するお金のシステムがあった。
当時、地域の領主たちがお金を発行していた。お金は6ヶ月とか8ヶ月とか、一定の期間がたつと回収し、そして2~3%、減価させて再発行していた。
この仕組みは、富をお金の形で持つのではなく、永久に価値が維持されるであろうと思えるものに投資させることになった。
地域の人々は連帯して、信仰の対象でありながら、経済的な意味でも将来の投資としてカテドラル(大聖堂)を建設していった。この時期に建設された大聖堂は今でも多くの観光客が見に来るくらいの素晴らしいものばかりである。
ここに見られるのは、もしお金がマイナスの利子のシステム(減価する貨幣)におかれるならば、社会が実現した富はなるだけ長期的に価値が維持されるようなものに投資されるということである。これに対し、プラスの利子の場合には、より短期の利益を上げるものへの投資が優勢になる。
例えば、日本の林業はよい例である。なぜ日本の森は死んだのか。それは、今のお金のシステムだと林業が割に合わないからである。木を売り払ったお金で別の短期的な利益を上げるものに投資したほうが有利だからだ。
しかし、オーストリアのヴェルグルで減価する労働証明書が貨幣として使われたとき(減価する貨幣)、町民は自分が手に入れた富を家の修繕に使い、その次には、積極的に木を植え始めたといわれる。
エジプトや欧州に旅行し、古代の遺跡や中世のカテドラルを見物した人は多いと思う。数千年、数百年後の人間が見るに値するものがそこには残っている。20年たったら壊れるような住宅やビル、10年もつかどうかの自動車、すべては、私たちの、利子の存在ゆえの短期的な利益を上げていかねばならない仕組みのなかで成立している。
息の長い価値あるものは作られず、他方で浪費の果てにゴミの山が吐き出されている。
(エンデの遺書 NHK出版)