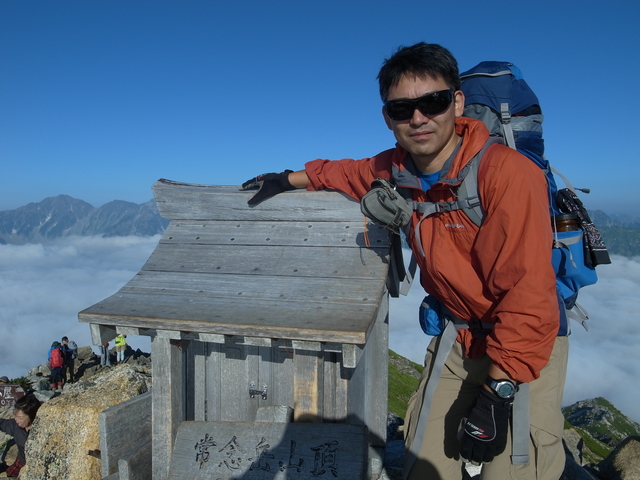重松清の「きよしこ」を読んだ。重松さんの小説を読むのは初めてだった。うーん、どういう感想を書こうか少し迷っている。私みたいなのがくだらない感想を書くより、直接この小説を読んでもらったほうがいいような気もする。しかし、まぁ、私の感想を読んでこの小説を手にとってくれる人が出てくる可能性があるのなら、なんとか頑張って書いてみようと思う。
「きよしこ」の主人公の少年は吃音症である。作者の重松さんも吃音症だったらしい。そうすると、この小説は限りなく私小説に近いのではないかとの推測ができる。重松さんのウェキペディアを読むと、この小説に出てくる少年と重なる部分が多い。もちろん小説に出てくる細かい逸話は創作なのだろうが。
少し前に、「英国王のスピーチ」を観たことをブロクで紹介した。映画のなかで、先生が吃音症になる原因について説明していた。それによると、吃音症になるのは身体的欠陥ではなく、幼児期の精神的な問題により発症するとの事であった。ジョージ6世も幼児期に受けたトラウマが原因で吃音症になったといわれている。「きよしこ」に出てくる少年も、ちょうど言語を覚える3歳くらいの時期に両親と離ればなれになったことが原因のように書かれている。
私は本当に無知でそのような事を全く知らなかった。身近にどもる人がいなくて(昔務めていた会社にひとりいた。営業だったから今考えるとすごいと思う)、そのようなことを考える機会がなかった。ただ、偶然かもしれないが、続けて吃音に関係する作品に触れたということは、なにか考えろと神様が私に告げているに違いない。
この小説を読んで、不覚にも二回くらいポロッと涙がこぼれてしまった(加藤くんとの別れのシーンとおっさんの歌を自転車をこぎながら歌うシーン)。アマゾンのレビューに、「電車の中で読んではいけない本」というのがあった。同感である。
人と人のコミュニケーションの基本は会話である。もちろん、他にもいろんな手段があるが、会話ができなければ自分の言いたいことの半分も相手に伝わらないだろう。主人公の少年は吃音症で、何か言葉を発すると馬鹿にされるのではないかとの恐怖ゆえ、言葉を発することに精神的セーブがかかっている。だから、相手に言いたいことの半分も言えない。しかし、この小説には吃音症ではなくても言いたいことの半分も言えない人たちがたくさん出てくる。なぜなんだろう。
私は結構物事をストレートに言う方で、もし好きな子ができたら、「好きだ」とはっきり言えるタイプだと思う。だけど、それでも、いつもそう言えたわけではない。本当に好きで好きでしょうがなかったときはやっぱり言えなかった。嫌われるのが怖いから。それから、本当に感謝している時だって、きちんと「ありがとう」が言えたか分からない。照れくさかったりして。
度胸があって物事をはっきり言う性格の私ですらこんな感じなのだから、気の小さい人が言いたいことの半分も言えないのは当たり前である。吃音症でなくったって、みんな言いたいことを満足に言えていないのだ。
だけど、人間特有の複雑な感情が邪魔したり、いろいろな障害があったとしても、伝えたい気持ちが強く前面に出てくると、言葉を超えて奇跡的に相手にその想いが伝わることがある。この小説は、その言葉を超えた魂の叫びが相手に伝わる瞬間を、うまく捉えている。その叫びが、ワイングラスを共鳴させるように私たちの心に響くのだ。
この小説を読んだ時、俺はこんな小説が書きたかったんだよなぁと思った。照れくさかったり、恥ずかしかったりして言えないことがたくさんある。だけど、どうにかして自分の中にあるこのポジティブな温かい気持ちを君に伝えたい。どうしても伝えたいんだよと。
この本は本当に素晴らしい。人に気持ちが伝わらない切なさと、それでも本当に伝えたい事は奇跡的に伝わってしまう人間の力強さがうまく表現されている。強くお薦めする。