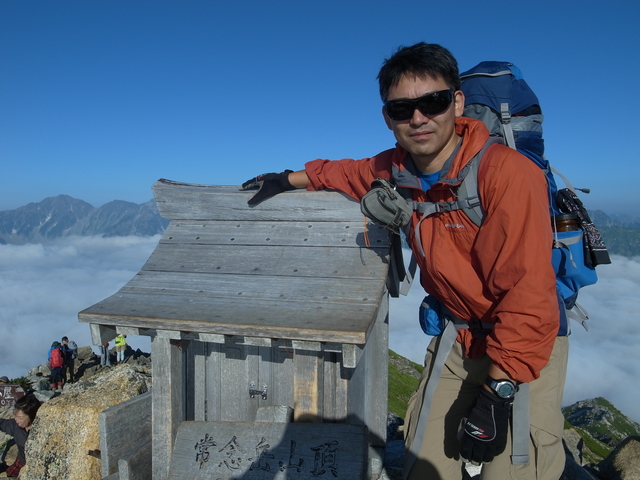「言葉の呪術性」というものを信じるか信じないかはともかく、ポール・オースターの小説は人の何かを微妙に狂わせる麻薬のようなものがある。現実と物語の世界の垣根が曖昧になって、知らない間に物語の中に引きずりこまれている。読むこと自体が奇妙な体験となる。
よく人のことをあれこれ詮索してその人の人生にズカズカと入り込んでくる人がいるが、そのような人を見るといつも軽薄で底の浅い人なんだなぁという感じがする。もし生きることの不可解さと人生の深遠を知っている人なら、簡単に人の人生に踏み込むことはできないはずだ。何かを知るということは一時的な好奇心は満たされるが、何かを傷つけ失うことでもあるからである。
小説家である主人公のシドは妻が精神的に不安定になっていることを感じ取る。そこには、自分には隠された何かがある。日本の昔話に出てくるような秘密をもったきれいな妻。秘密を知れば、妻は自分のもとから去っていってしまうのが、日本の昔話で繰り返されるパターンである。
しかし、彼は小説家らしく手持ちの事実から彼女の過去を推測し一つの物語を作る。そのよくできた最悪ともいえる物語は、彼にとってはそれが真実になる。
言葉の呪術性。
この小説家を主人公にした物語は、彼がポルトガル製の青いノートを手にしたところから始まる。そのノートに様々な物語が書かれることになる。
「わかってます。すべて僕の頭の中の問題だって言うんでしょう。僕だってそうじゃないとは言えませんけど、とにかくあのノートを買って以来、何もかもが無茶苦茶なんです。僕がノートを使っているのか、ノートが僕を使っているのか、それさえわかりません。これって意味を成していますかね?」
早速、ポール・オースターの「幻影の書」を図書館から借りてきて、読み始めている。彼の小説は麻薬のような中毒性がある。だから、近づかない方が身のためかもしれない。