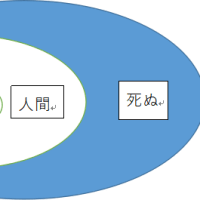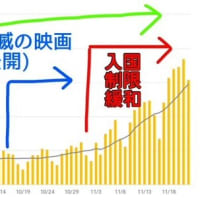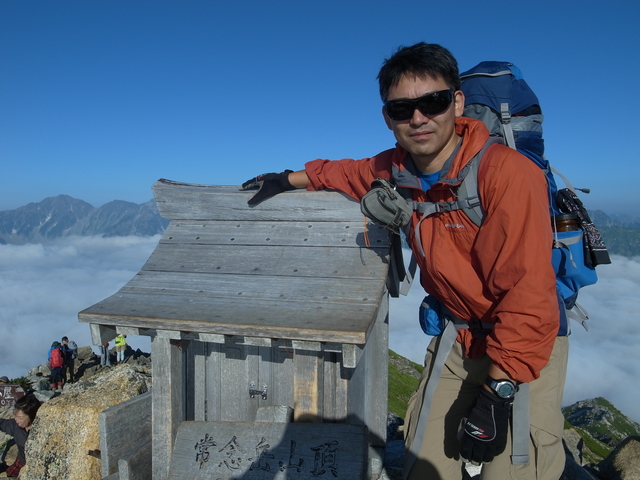「博士の愛した数式」小川洋子著、を読む。
この小説のおかげで、穏やかで心温まる素晴らしい休日が過ごせたと思う。
小川洋子氏は、「物語の役割」という新書の中でフランスの作家を引用してこういっている。
「書くこと、文章に姿をあらわさせること、それは特権的な知識を並べることではない。それは人が知っていながら、誰ひとり言えずにいることを発見しようとする試みだ」と。
なるほど、と深く同意する。自分の周りにある様々な現実を注意深く観察しそれに言葉を与える。それが作家の仕事だというのである。
博士はこのように言う。
「そう、まさに発見だ。発明じゃない。自分が生まれるずっと以前から、誰にも気づかれずそこに存在している定理を、掘り起こすんだ。神の手帳だけに記されている真理を、一行ずつ、書き写してゆくようなものだ。その手帳がどこにあって、いつ開かれているのか、誰にもわからない」
小説を読んでいる間、一切宗教の話は出てこないにも関わらず、何か宗教的なものを感じながら読み進めていた。
それはとても不思議な感覚だった。多分、博士が数というものに対して、純粋な信仰心のようなものを持っているからだと思う。
全く抽象的で偶然の数が、人と人をそれが必然であったかのように結びつける。その瞬間に、超越した何かを感じてしまう。人はそれに魅了されてしまうのだ。
80分で記憶が消滅してしまうということが、この小説を面白くしているわけではあるが、それがまたせつなくもある。
ある種の滑稽さの中には、何か人をせつなくさせるような部分が含まれている。そして不思議なことではあるが、滑稽であればあるほどその滑稽さを深く愛してしまう。