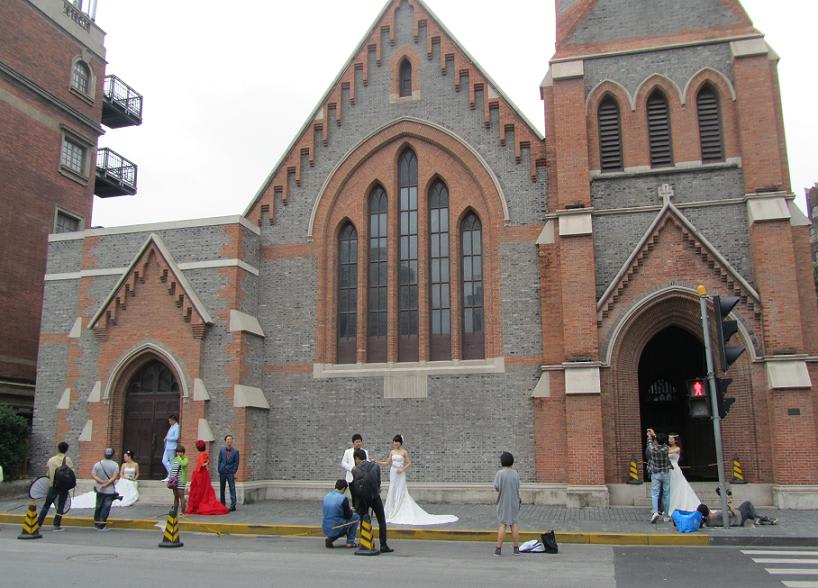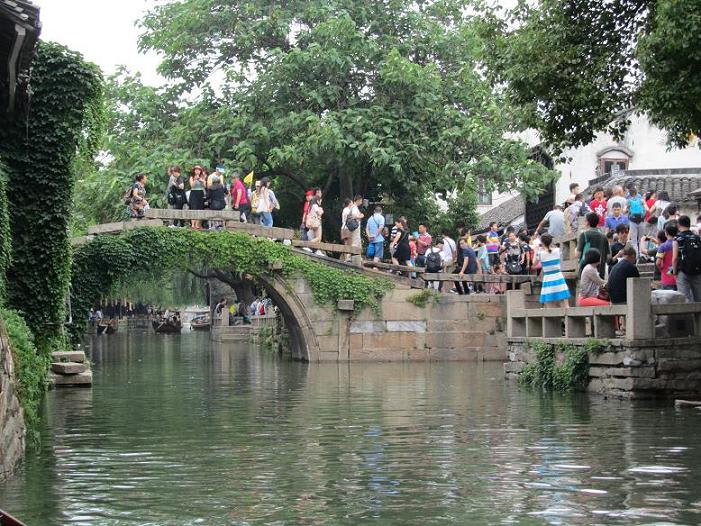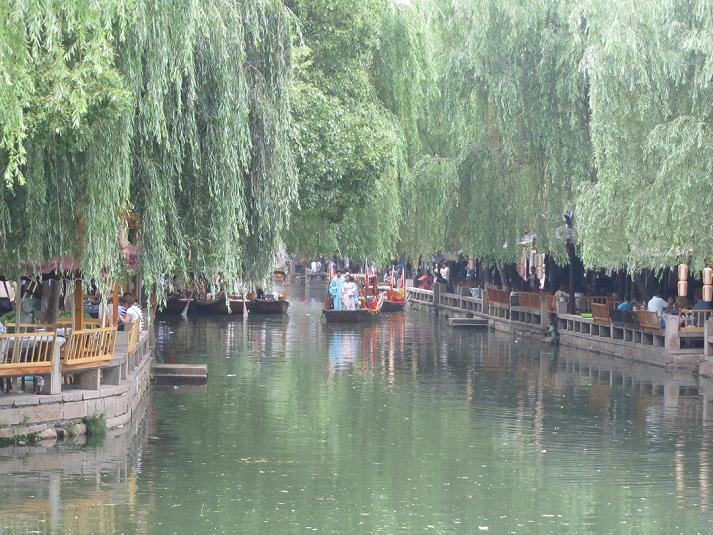お客さんを十人ほど連れて近くのラーメン屋に入った。
「蘭州ラーメン」という名のチェーン店で、中国のイスラム教徒が経営している。注文してから麺を打ってくれるからとてもおいしい。しかも牛肉ラーメンが一杯七元(百円弱)と値段もリーズナブルだ。ラーメンだけではさびしいからチャーハンや炒め物もいっしょに頼んでみんなでつついた。
勘定を払うとき、
「領収書を切ってよ」
と店の若旦那に言うと、
「俺は字が書けないんだ。自分で書いてくれ」
という返事がかえってきた。ちょうど昼時の店がいちばん混む時間帯だったから、若旦那は領収書どころではないという感じでせっせと麺を打つ。
しょうがないなと思いつつ店員に白紙の領収書を出してもらい、ほんとにいいのかなと思いながら客である僕が自分で金額を書き入れた。日本ではあり得ないことだ。
中国の領収書は必ずすべて難しい漢数字で数を記入しなくてはならない。たとえば、「一」は「壹」と書き、「二」は「弐」と書く。日本の領収書や小切手も難しい漢数字で数を書くけど、「四」や「七」といったあとから棒線を書き足して偽造できないような数字はそのまま「四」や「七」を使う。中国の場合は、「四」や「七」もすべて「肆(四)」や「柒(七)」と難しい漢数字で書かなくてはならない。画数の多い漢字ばかりを書かなくてはいけないから、これがけっこう面倒くさい。ようやく書き上げると若旦那は、
「ごめん。百十元じゃなくって、百十七元だった」
などと横から言ってくる。
「早く言ってくれよぉ」
僕はぼやいて、書き上げたばかりの領収書を破って書き直した。
中国ではまれに漢字の書けない人に出くわす。チベット族やウイグル族のように強固な民族文化を持ち、固有の文字を持っている民族は漢字を書けなくてもしかたないとしても、漢民族でも漢字がわからない人がいる。もちろん、漢字を知らないといっても濃淡があって、まったくわからない人もいれば、名前と簡単な漢数字は書けてもそれ以上のことは読み書きできない人もいる。
読み書きできない原因は、昔の日本でもそうだったように、家が貧しくて学校へ行かせてもらえず、農作業の手伝いばかりしていたというのがほとんどだ。ラーメン屋の若旦那の場合は、イスラム教徒の学校へ通って、アラビア文字しか習わなかったのかもしれない。
中国は漢字の国だけど、なかにはいろんな人たちがいる。
(2013年6月22日発表)
この原稿は「小説家なろう」サイトで連載中のエッセイ『ゆっくりゆうやけ』において第242話として投稿しました。 『ゆっくりゆうやけ』のアドレスは以下の通りです。もしよければ、ほかの話もご覧ください。
http://ncode.syosetu.com/n8686m/