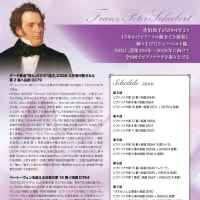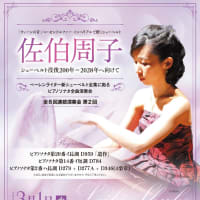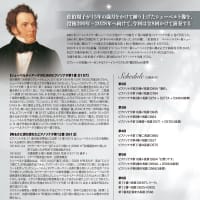昨日号の続き。昨日のペースで書き続けると、10年書くのに10日程度掛かりそうなので、「特急」モードにする(爆
今、聴いているCDは、アルベニス「イベリア」。伊福部昭先生もアルベニスは好きだったことを思い出す。
20世紀は、『1901~2000年』だ。吉松隆のように、2000年 = 21世紀の氣分 とか言う人も多いので、ご注意頂きたい。
旧 Daily Classical Music Critique in Tokyo 時代 の20世紀に、3度「転機」が来た。元々「オーケストラ中心」で批評&評論を重ねる、と宣言していたホームページにもかかわらず、3度ともオーケストラでは無かった。1回はオペラ、次の1回はドイツリート、最後の1回はピアノソロである。う~ん、この辺りの流れはよくわからない(藁
忘れもしない。あれは1997年10月10日だった。産まれた時から「体育の日 = 10月10日」だったのに、この事件が起こった直後の国会で「体育の日」が変えられてしまった。それほど『社会的にインパクトのあった事件』である。もう9年も前のことなので、憶えていない方や知らない方も多いことだろう。振り返ろう。
その現場に立ち会ったのである。「史上初の天覧ブーイング」かも知れない。全部 = 招待 にしてしまうと「非公開演奏会」扱いになる。 シェーンベルク1派が頻繁に行った手法。 シェーンベルク1派が「個人的に非公開演奏会開催」は(個人のフトコロなので)何も問題ないが、クニのゼニをツッ込むとなると、少々違う。『ゲネプロ扱い』されてはダメ。
・・・と言うことで、チケットは売り出された。オペラファンが殺到して発売直後に売り切れた、と記憶している。3&4階だけだったからなぁ。買えなかったら「ふざけるな、新国立劇場!」とかのキャンペーンを張った可能性は極めて大なのだが、なぜか買えた。そして聴いた。ブーイングも聞いた。
をはっきり国内外に示した瞬間だった。
私高本は興奮して、寝ずに批評を書いた。何が何だかわからない内に、いろいろな人が 旧デイリー を引用していた。1円ももらわなかったが、アクセス数がガーンと上がった瞬間だった(藁
1998年12月、新国立劇場「建」の1年2ヶ月後である。新国立劇場のスケジューリングがスカで、「ヘンゼルとグレーテル」公演で日程変更が生じた。昔々から、スカだったのね(藁
・・・で、1日空いた。その日に シューベルト「冬の旅」が、今はほとんど誰も利用しない「音楽の友ホール」で開催された。地下鉄東西線のノイズが ピアニッシモの時にわずかだが聞こえるホールである(爆
岡原慎也は、数年前に同一曲目 = 「冬の旅」 でプライ独唱時に聴いていた。結構クセのある プライ にうまく合わせていた記憶が(強くなく)残っていた。「冬の旅」は私高本が大好きな曲目なので、『あの岡原慎也が伴奏するならば、悪くは無いだろう』くらいの気持ちで『推薦コンサート』にした。
岡原慎也は、1曲目「おやすみ」の前奏から『別人』のように素晴らしかったし、プライ は知っていたが全然しらない ヘンシェル と言うバリトンも(信じられないことに)プライよりも数倍感銘を受けた。
・・・というよりも、F=ディスカウ 以上に感銘を受けた。自分の心の中で「天と地がひっくり返った瞬間」だった、と振り返って今思う。 この演奏会を聴かなかったら、その後の私高本の活動全ては無かったと思う。 川上敦子 & 佐伯周子 を含めて、である。
・・・というよりも「今の私高本秀行」自体が無かったのでは? と思う。岡原慎也 と ヘンシェル には「音楽の本質」を教えて頂いたことについて、言葉が尽くせないほどの感謝がある。
『花火と言えば、ドビュッシー!』 が「ピアノファンの常識」と思うが、非常識な(?)私高本は違う道を歩んだ(爆
その前年に 岡原慎也の真価 を知った私高本は、当時知っていた在京有望アーティストを『夏の花火大会』に招待した。(岡原慎也 は 関西人なので招待していない)酒を呑まないアーティストばかりなのは、今振り返ると不思議。
を中心に花火をツマミに、酒(&貧弱な食い物)で『将来』を語り合った。その中には、柳津みちよ も居たので、おそらく私高本の脳内では「オペレッタ中心」の構想が事前にあったような気がする。その日のために、オペレッタのスコアも購入した形跡とレシートが残っている(レハール「メリー・ウィドゥ」)。
・・・で、この日の結論として「川上敦子のリスト」をプロデュースする方向で私高本の心は決まった。川上敦子の「ダンテを読んで」の演奏が素晴らしかったからだろうか? 上がった花火が「リスト風」だったからだろうか? よくワカラン。 この日から 旧デイリー は「批評よりも、演奏会プロデュース優先」の方針に移った。創刊から 3年も経過していないそんな真夏の日の出来事である(爆
21世紀になってからの6年間の続きはまた明日
今、聴いているCDは、アルベニス「イベリア」。伊福部昭先生もアルベニスは好きだったことを思い出す。
20世紀の転機(私高本の場合)
20世紀は、『1901~2000年』だ。吉松隆のように、2000年 = 21世紀の氣分 とか言う人も多いので、ご注意頂きたい。
旧 Daily Classical Music Critique in Tokyo 時代 の20世紀に、3度「転機」が来た。元々「オーケストラ中心」で批評&評論を重ねる、と宣言していたホームページにもかかわらず、3度ともオーケストラでは無かった。1回はオペラ、次の1回はドイツリート、最後の1回はピアノソロである。う~ん、この辺りの流れはよくわからない(藁
転機1:新国立劇場オープニング=團伊球磨「建(タケル)」に出会い『歴史の証人』となる
忘れもしない。あれは1997年10月10日だった。産まれた時から「体育の日 = 10月10日」だったのに、この事件が起こった直後の国会で「体育の日」が変えられてしまった。それほど『社会的にインパクトのあった事件』である。もう9年も前のことなので、憶えていない方や知らない方も多いことだろう。振り返ろう。
- オペラ関係者悲願の「新国立劇場」が1997年10月10日「体育の日(← 当時)」にオープン
- 日本政府は念には念を入れ、「1階&2階は全部招待(← 今、文部科学省で問題になっている全国各地の『サクラ』と同じと考えて、大体の方向は同じ)」で占有
- 2階席正面は、天皇夫妻&橋本首相が2幕以降来臨
- 「大絶賛のブラヴォーの嵐」で終わるハズだったのに
- 3&4階席の「ごくわずかだけ売り出された一般席の聴衆」が
- 終演までは全く静かにしていたにも関わらず
- 終演と同時に「作曲&演出&指揮」に向かって『ブーイングの嵐』を吹き荒らした
その現場に立ち会ったのである。「史上初の天覧ブーイング」かも知れない。全部 = 招待 にしてしまうと「非公開演奏会」扱いになる。 シェーンベルク1派が頻繁に行った手法。 シェーンベルク1派が「個人的に非公開演奏会開催」は(個人のフトコロなので)何も問題ないが、クニのゼニをツッ込むとなると、少々違う。『ゲネプロ扱い』されてはダメ。
・・・と言うことで、チケットは売り出された。オペラファンが殺到して発売直後に売り切れた、と記憶している。3&4階だけだったからなぁ。買えなかったら「ふざけるな、新国立劇場!」とかのキャンペーンを張った可能性は極めて大なのだが、なぜか買えた。そして聴いた。ブーイングも聞いた。
オペラの中心は聴衆!
をはっきり国内外に示した瞬間だった。
私高本は興奮して、寝ずに批評を書いた。何が何だかわからない内に、いろいろな人が 旧デイリー を引用していた。1円ももらわなかったが、アクセス数がガーンと上がった瞬間だった(藁
転機2:岡原慎也+ヘンシェル「シューベルト:冬の旅」
1998年12月、新国立劇場「建」の1年2ヶ月後である。新国立劇場のスケジューリングがスカで、「ヘンゼルとグレーテル」公演で日程変更が生じた。昔々から、スカだったのね(藁
・・・で、1日空いた。その日に シューベルト「冬の旅」が、今はほとんど誰も利用しない「音楽の友ホール」で開催された。地下鉄東西線のノイズが ピアニッシモの時にわずかだが聞こえるホールである(爆
岡原慎也は、数年前に同一曲目 = 「冬の旅」 でプライ独唱時に聴いていた。結構クセのある プライ にうまく合わせていた記憶が(強くなく)残っていた。「冬の旅」は私高本が大好きな曲目なので、『あの岡原慎也が伴奏するならば、悪くは無いだろう』くらいの気持ちで『推薦コンサート』にした。
岡原慎也は、1曲目「おやすみ」の前奏から『別人』のように素晴らしかったし、プライ は知っていたが全然しらない ヘンシェル と言うバリトンも(信じられないことに)プライよりも数倍感銘を受けた。
・・・というよりも、F=ディスカウ 以上に感銘を受けた。自分の心の中で「天と地がひっくり返った瞬間」だった、と振り返って今思う。 この演奏会を聴かなかったら、その後の私高本の活動全ては無かったと思う。 川上敦子 & 佐伯周子 を含めて、である。
・・・というよりも「今の私高本秀行」自体が無かったのでは? と思う。岡原慎也 と ヘンシェル には「音楽の本質」を教えて頂いたことについて、言葉が尽くせないほどの感謝がある。
転機3:1999年7月の多摩川花火大会の日
『花火と言えば、ドビュッシー!』 が「ピアノファンの常識」と思うが、非常識な(?)私高本は違う道を歩んだ(爆
その前年に 岡原慎也の真価 を知った私高本は、当時知っていた在京有望アーティストを『夏の花火大会』に招待した。(岡原慎也 は 関西人なので招待していない)酒を呑まないアーティストばかりなのは、今振り返ると不思議。
- ソプラノ → 日比野景
- ピアノ → 川上敦子
を中心に花火をツマミに、酒(&貧弱な食い物)で『将来』を語り合った。その中には、柳津みちよ も居たので、おそらく私高本の脳内では「オペレッタ中心」の構想が事前にあったような気がする。その日のために、オペレッタのスコアも購入した形跡とレシートが残っている(レハール「メリー・ウィドゥ」)。
・・・で、この日の結論として「川上敦子のリスト」をプロデュースする方向で私高本の心は決まった。川上敦子の「ダンテを読んで」の演奏が素晴らしかったからだろうか? 上がった花火が「リスト風」だったからだろうか? よくワカラン。 この日から 旧デイリー は「批評よりも、演奏会プロデュース優先」の方針に移った。創刊から 3年も経過していないそんな真夏の日の出来事である(爆
21世紀になってからの6年間の続きはまた明日