経済史のダイアモンドが「中国から消える検索エンジン、バイドゥも窮地に」と言う記事を載せていたが、確かに、検索エンジン、最近は使う頻度が少なくなっている。Webで詳細を見たい場合は、面倒なURLを書かなくてもリンクで跳べる。実際グーグルやYahooの検索エンジンの事業比は低くなっており、検索エンジンだけの中国の百度(バイドウ)の事業が厳しくなっているのは想像に難くない。
以下、ダイアモンドの記事に依る::::::::::::::::::::::::::
バイドゥの足元がふらついたのはこれが初めてではない。昨年8月には、グーグルが中国への再参入を計画しているとの報道を受け、バイドゥの検索エンジンからユーザーが大量に流出すると投資家が懸念。株価は1日で8%急落した。
バイドゥが直面する大きな課題は、中国のインターネットが本質的に変化しつつあることだ。電子商取引大手アリババグループやネットサービス大手のテンセントホールディングスは事実上、それぞれ独自のエコシステムを構築している。それは外界から隔離する壁に囲まれた庭園のようなもので、外部の検索エンジンは必要とせず、また接続することもできない。中国の消費者はオンラインで買い物をする際、例えばアリババのサイトに直接アクセスする。娯楽を求める消費者はテンセントのソーシャルメディア「微信(ウィーチャット)」を使うかもしれない。メッセージアプリのウィーチャットは、ニュースからゲームまで幅広いコンテンツを提供するミニOS(基本ソフト)に進化している。
バイドゥも独自の囲まれた庭園を作り出そうとしている。2016年にはパーソナライズされたニュースフィード機能をアプリに追加し、利用者数と広告収入を押し上げてきた。ただ、その方面では、動画共有アプリを運営するバイトダンス(字節跳動)が強力な競合として立ちはだかる。バイトダンスは人気ニュースアプリの「今日頭条」や動画共有アプリ「ティックトック」でユーザーを取り込んでいる。
バイドゥはアリババ、テンセントと合わせ、頭文字を取って「BAT」と称される三大ネット会社の一つに数えられてきた。最近では、中核事業の成長見通しに対する懐疑的な見方を背景に、時価総額で他の2社に大きく後れを取っている。ファクトセットによると、来年の予想PER(株価収益率)は16.7倍にとどまる。これはグーグルの親会社アルファベットの26倍を大幅に下回る。割安なように見えるかもしれない。だが、バイドゥや中国の検索エンジンを取り囲むあらゆる不確実性を考えれば、今は投資家が再び飛び込むべき時とは言えない。














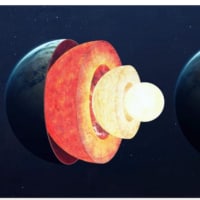

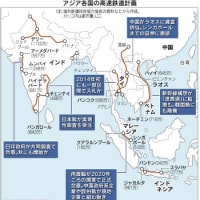
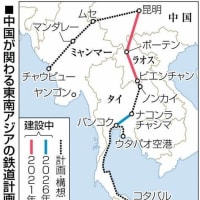

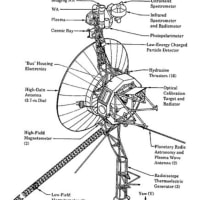
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます