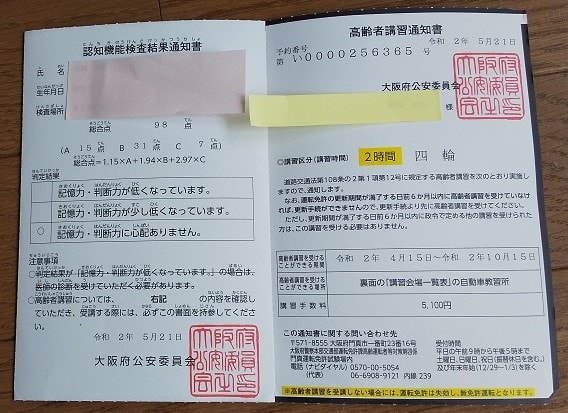先日、特別定額給付金をかたる詐欺について取り上げましたが、今日は給付金の申請方法について総務省のHPからご紹介します。
「特別定額給付金」
「給付対象者と受給権者」
1.給付対象者・・・基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
2.受 給 権 者・・・給付対象者の属する世帯の世帯主
給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になります。
具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
4月28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、4月27日以降に亡くなった人は対象となります。
ホームレスの人などで住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、4月28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となります。
「支給開始日」
支給の開始日は、各市区町村が決めることになっています。
「特別定額給付金の申請方法」
給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。
申請は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送かオンラインの2つの方式のいずれかで行います。
1.郵送で申請する方法
市区町村から世帯主宛に郵送されてくる申請書に、必要事項を記載して返送する方式です。
申請書には、あらかじめ家族全員の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計金額がわかるようになっています。
これらの情報に間違いがないかを確認したうえで、世帯主が氏名、生年月日、それに振り込みを希望する自分名義の金融機関の口座の情報などを記入します。
そして、次の2つの資料を添付して市区町村に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれます。
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
・指定した口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピー
病気などで、世帯主本人が対応することが難しい場合は、代理人が申請したり、給付金を受け取ったりすることができます。
一方で、もし家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給されず、家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ありません。
なお、申請から給付までの流れについては、総務省の「詳しい申請方法」にリンクしておきますので下記をご参照してください。
「総務省・詳しい申請方法」
「申請書を郵送している市区町村」
2.オンラインで申請する方法(マイナンバーカードをお持ちの方)
世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請もできます。
オンラインでの申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから専用のアプリ「マイナポータルAP」を使って申請するか、カードリーダーを接続したパソコンから、「マイナポータル」のサイトを経由して申請する方法があります。
オンラインによる申請を行う場合、口座情報を確認するため通帳やキャッシュカードの写真をアップロードすることが必要ですが、マイナンバーカードの本人確認機能を使うため、本人確認のための書類は必要ありません。
オンライン申請の詳しい申請方法も下記にリンクしておきますのでご参照ください。
「オンライン申請の詳しい申請方法」
「オンライン申請受付開始市区町村」
皆さんのところには申請書類が届きましたか?
そして、申請を済まされましたか?
私が住まいする大阪府熊取町では、先日、申請用紙が送られてきたので、早速、必要事項を記入して返送したところです。
熊取町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送申請するようにとの協力依頼がありました。
なお、受付期間は、5月11日(月)~8月11日(火)(土・日・祝日を除く)となっていました。
申請がまだの方も受付期間には余裕がありますので慌てることはありません。
でも、申請を忘れてしまうと「支給を希望しない」とみなされてしまいます。
ご注意くださいね。
















 幼
幼