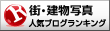鎌倉 円覚寺にて
手前は修行中のブッダ
最近ツイッターにはまっていることはすでに書いたが、そのツイッターで僕がフォローしている発信者の中にブッダの言葉を発信しているものがある。その中で僕が原始仏典に出てくる言葉の中で最も好きな言葉があったので載せていみたい。ツイッターで流れてきたものはもちろんこの中の一部だ。
犀の角
あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩(なや)ますことなく、また子を欲するなかれ。況(いわ)んや朋友(ほうゆう)をや。犀(さい)の角(つの)のようにただ独(ひと)り歩(あゆ)め。
交(まじ)わりをしたならば愛情が生ずる。愛情にしたがってこの苦しみが起る。愛情から禍(わざわ)いの生ずることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
朋友・親友に憐(あわ)れみをかけ、心がほだされると、おのが利を失う。親しみにはこの恐れのあることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
子や妻に対する愛著(あいじゃく)は、たしかに枝の広く茂った竹が互いに相絡(あいから)むようなものである。筍(たけのこ)が他のものにまつわりつくことのないように、犀の角のようにただ独り歩め。
林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところに赴(おもむ)くように、聡明な人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
仲間の中におれば、休むにも、立つにも、行くにも、旅するにも、つねにひとに呼びかけられる。他人に従属しない独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
仲間の中におれば、遊戯と歓楽(かんらく)とがある。また子らに対する情愛は甚だ大である。愛しき者と別れることを厭(いと)いながらも、犀の角のようにただ独り歩め。
四方のどこにでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々(もろもろ)の苦難に堪(た)えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
出家者(しゅっけしゃ)でありながらなお不満の念をいだいている人々がいる。また家に住まう在家者(ざいけしゃ)でも同様である。だから他人の子女にかかわること少く、犀の角のようにただ独り歩め。
葉の落ちたコーヴィラーラ樹のように、在家者のしるしを棄て去って、在家の束縛(そくばく)を断(た)ち切って、健(たけ)き人はただ独り歩め。
もしも汝(なんじ)が、〈賢明で協同し行儀(ぎょうぎ)正しい明敏(めいびん)な同伴者〉を得たならば、あらゆる危難にうち勝ち、こころ喜び、気をおちつかせて、かれとともに歩め。
しかしもしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得ないならば、譬えば王が征服した国を捨て去るようにして、犀の角のようにただ独り歩め。
われらは実に朋友を得る幸(しあわせ)を讃(ほ)め称(たた)える。自分よりも勝(すぐ)れあるいは等(ひと)しい朋友には、親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過(つみとが)のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
金の細工人がみごとに仕上げた二つの輝く黄金(おうごん)の腕輪(うでわ)を、一つの腕にはめれば、ぶつかり合う。それを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
このように二人でいるならば、われに饒舌(じょうぜつ)といさかいとが起るであろう。未来にこの恐れのあることを察して、犀の角のようにただ独り歩め。
実に欲望は色とりどりで甘美(かんび)であり、心に楽しく、種々のかたちで、心を攪乱(かくらん)する。欲望の対象(たいしょう)にはこの患(うれ)いのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
これはわたくしにとって災害であり、腫物(はれもの)であり、禍(わざわい)であり、病(やまい)であり、矢であり、恐怖である。諸々の欲望の対象にはこの恐ろしさのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
寒さと暑さと、飢(う)えと渇(かつ)えと、風と太陽の熱と、虻(あぶ)と蛇と、―これらすべてのものにうち勝って、犀の角のようにただ独り歩め。
肩がしっかりと発育し蓮華のようにみごとな巨大な象は、その群(むれ)を離れて、欲するがままに森の中を遊歩する。そのように、犀の角のようにただ独り歩め。
集会を楽しむ人には、暫時の解脱(げだつ)に至るべきことわりもない。太陽の末裔(まつえい)(ブッダ)のことばをこころがけて、犀の角のようにただ独り歩め。
相争(あいあらそ)う哲学的見解を超え、(さとりに至る)決定に達し、道を得ている人は、「われは智慧が生じた。もはや他の人に指導される要がない」と知って、犀の角のようにただ独り歩め。
貪(むさぼ)ることなく、詐(いつわ)ることなく、渇(かつ)望することなく、(見せかけで)覆(おお)うことなく、濁(にご)りと迷妄(めいもう)とを除(のぞ)き去り、全世界において妄執のないものとなって、犀の角のようにただ独り歩め。
義ならざるものを見て邪曲にとらわれている悪い朋友を避けよ。貪りに耽(ふけ)り怠っている人に、みずから親しむな。犀の角のようにただ独り歩め。
学識ゆたかで真理をわきまえ、高邁(こうまい)・明敏(めいびん)な友と交(まじ)われ。いろいろと為になることがらを知り、疑惑を除き去って、犀の角のようにただ独り歩め。
世の中の遊戯や娯楽(ごらく)や快楽に、満足を感ずることなく、心ひかれることなく、身の装飾を離れて、真実を語り、犀の角のようにただ独り歩め。
妻子も、父母も、財宝も穀物(こくもつ)も、親族やそのほかあらゆる欲望までも、すべて捨てて、犀の角のようにただ独り歩め。
「これは執著(しゅうじゃく)である。ここには楽しみは少く、快い味わいも少くて、苦しみが多い。これは魚を釣る釣り針である」と知って、賢者は、犀の角のようにただ独り歩め。
水の中の魚が網(あみ)を破るように、また火がすでに焼いたところに戻ってこないように、諸々の(煩悩(ぼんのう)の)結び目を破り去って、犀の角のようにただ独り歩め。
俯(ふ)して視(み)、とめどなくうろつくことなく、諸々の感官を防いで守り、こころを護(まも)り(慎しみ)、(煩悩の)流れ出ることなく、(煩悩の火に)焼かれることもなく、犀の角のようにただ独り歩め。
葉の落ちたパーリチャッタ樹のように、在家者の諸々のしるしを除(のぞ)き去って、出家して袈裟(けさ)の衣をまとい、犀の角のようにただ独り歩め。
諸々の味を貪(むさぼ)ることなく、えり好みすることなく、他人を養うことなく、戸ごとに食を乞(こ)い、家々に心をつなぐことなく、犀の角のようにただ独り歩め。
こころの五つの覆(おお)いを断(た)ち切って、すべて付随して起る悪しき悩み(随煩悩(ずいぼんのう))を除き去り、なにものかにたよることなく、愛念の過(あやま)ちを絶(た)ち切って、犀の角のようにただ独り歩め。
以前に経験した楽しみと苦しみとを擲(なげう)ち、また快(こころよ)さと憂(うれ)いとを擲って、清らかな平静と安(やす)らいとを得て、犀の角のようにただ独り歩め。
最高の目的を達成するために努力策励(さくれい)し、こころが怯(ひる)むことなく、行いに怠(おこた)ることなく、堅固な活動をなし、体力と智力とを具(そな)え、犀の角のようにただ独り歩め。
独坐(どくざ)と禅定(ぜんじょう)を捨てることなく、諸々のことがらについて常に理法に従って行い、諸々の生存には患(うれ)いのあることを確かに知って、犀の角のようにただ独り歩め。
妄執の消滅を求めて、怠らず、明敏であって、学ぶこと深く、こころをとどめ、理法を明らかに知り、自制し、努力して、犀の角のようにただ独り歩め。
音声に驚かない獅子(しし)のように、網にとらえられない風のように、水に汚(けが)されない蓮(はす)のように、犀の角のようにただ独り歩め。
歯牙(しが)強く獣どもの王である獅子が他の獣にうち勝ち制圧してふるまうように、辺地の坐臥(ざが)に親しめ。犀の角のようにただ独り歩め。
慈(いつく)しみと平静とあわれみと解脱(げだつ)と喜びとを時に応じて修め、世間すべてに背(そむ)くことなく、犀の角のようにただ独り歩め。
貪欲(とんよく)と嫌悪(けんお)と迷妄(めいもう)とを捨て、結(むす)び目を破り、命(いのち)を失うのを恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
今のひとびとは自分の利益のために交(まじ)わりを結び、また他人に奉仕する。今日、利益をめざさない友は、得がたい。自分の利益のみを知る人間は、きたならしい。犀の角のようにただ独り歩め。
これはスッタニパータといって数ある仏典の中でも最も古い経典の中の一節で、ここに書かれているものはブッダその人が実際に教えたことにかなり近いと考えていいだろう。
僕はたくさんある原始仏典の言葉の中でも、この一節が好きで、とくにこの韻を踏むようにかかれている「犀(さい)の角のように一人歩め」ということばに明確な理由はないのだが強く惹かれる。
この言葉を思い浮かべるとき、クローズアップされた犀の角が左右に揺られながらもゆっくりと前へ進んでいくビジョンがはっきりと脳裏に浮かぶ。おそらく、いや必ずブッダその人も実際にそういう犀の角を見て、ご自分の人生と重ね合わせるものがあったに違いない。
ここにかかれていることは、いかにもブッダの説いた仏教の本質の一端をあらわしていて、最初期の仏教徒の修行の厳しさというものが察せられる。
今現在の仏教徒でこれほどの厳しい環境で修行をしている人々がどれほどいるだろう。この「命を失うのを恐れることなく」という言葉通り、修行の途中で命を失う修行者も実際にいたことだろう。
今でもたまに見るかごを持って路傍にたって托鉢しているお坊さんの修行なども、この最初期の仏教徒の修行を彷彿とさせるし、それを思い起こすためにやっているのかもしれない。
僕も実は最近、ある非常に難しい人柄の人物とのかかわりの中で苦しんでいて、そんな今の心境でみるとこの、
『音声に驚かない獅子(しし)のように、網にとらえられない風のように、水に汚(けが)されない蓮(はす)のように、犀の角のようにただ独り歩め。』
という言葉がとくに強い力を持って浮き上がって見えてくる。
この全文をあらためて読んでみると、仏教というもの(特にブッダの説いた原始仏教)の核、原理的な本質となる部分をある程度は理解していないと、かなり誤解を受けるだろうと思う。何と反社会的な教えなんだろうというふうに(笑)
僧侶が仏典(とくにブッダの説いた教え)の教えを人々に説くこともなく、また、その僧侶自身も世俗の中にどっぷりとつかっている人々が多くなってしまっている今では、それはある程度はしかたがないのかもしれない。
すべての苦悩の根源とは何か?という疑問を若き日に抱き、その探求のために将来は王となる地位を惜しげもなく捨て去って命がけの修行の道に入っていったブッダ(釈迦)のたどり着いた答えは、確かに今の価値観から見れば「反社会的」に見える。しかし、この世俗社会というものの本質的なありようそのものの中に『人間の苦悩の根源』が内包されている以上、この覚醒者(ブッダ)がそこからの離脱を人々に説くことになったのは当然の帰結であろう。
孤独であることが悪とされる社会の中で生きている場合、こんな生き方をすれば自分は孤立するのではないか、でも、自分の正しいと信じるところに従えば孤立せざるを得ないというような状況の中であえいでいる時、これらブッダの「肉声」は強い指針と勇気を与えてくれる。