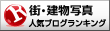ようやく確定申告が終わった。まるで締め切りに追われる作家のように追い詰められながらぎりぎりで終わるというパターンを毎年繰り返している。
今年、いや、毎ねんそうなのだが、申告会場で相談に乗ってくれる税務署の職員さんたちの親切さ、優しさはほんとうにありがたい。たぶんだが、日本ほど公共サービス(公的も、民間も含めて)の質のいい国はないのではないかと思う。
海外に住んだ人であればわかると思うが、海外では民間の会社であってもサービスを与える側と受ける側の立場はほぼ対等だ。できないことはできないといってはっきり断る。例えば日本であればたとえ自分が知らないことであっても自社のことであれば、かならずお客を待たせて同僚や上司に聞き客にこたえるのがふつうである。最近のとくにネットのチャットサポートではそうしないでただできませんで済ませる人もいるが、普通の窓口ではちゃんと確認をしてから答えるだろう。
欧米、といっても僕が住んだことのある国だけではあるが、ではたとえ自分の会社のことを聞かれていても、自分が知らなければ知らない、あそこにあるパンフレットを見てください、と平気で言う。あくまで自分がまかせられている業務のことにしか対応しない人が多い。これは彼らが不親切であるからではなく、そういう文化的な思考をする国なんだなと僕は解釈していた。
一度、空港で飛行機を乗り継ぎしたときに、次の便が大幅に遅れていて、いつ動くのかたぶん詰問調に聞いていた客がいたのだが、そのたぶんフランス人と思われる航空会社の職員は、「知りません、遅れたのは私の責任ではありません」とのうのうといっていたのをおぼえている。
ようは、あくまで「自分」と「会社」とは別なのである、彼らにとっては。自分は自分の責任の範囲のことだけに責任を負うのであって、同じ会社のことであっても他人がやった事には責任は負えないし、負う必要はない、という思考なのだ。もちろん会社の上層部に行けば行くほどそういう応対をする人は減っていくだろう、でもそれはその地位がもたらす責任の範囲が広がるからそうなるのであって、「基本的な思考」はこの末端の職員的な思考をしているはずである。
そう、これらはかれらの個人主義的な価値観から生まれているのだと僕は思う。
これがいいか悪いかというのは短絡的には言えない。視点を社会全体、あるいは歴史全体に拡げてみれば正と負の両面が見えてくるし、多くの場合視点を高いところにあげれば上げるほど、僕には彼らの個人主義というものが社会や国家、そして文化にまで多くの実益を与え続けてきていることが見えてくる。だから、どちらがいいか悪いかというよりも、あくまでも文化的な「違い」と僕は受け止めている。
ただし視点をあくまで利用者、サービスを受ける側に限定すれば、やはり日本のサービスはありがたいと思う。

さて、そんなこんなでやっと自由の身になれたので、この週末は休日を満喫させてもらった。もっとも僕のためというよりは僕のペットのためではあるが。ずっと家に閉じ込めっきりになっていて、散歩もほんのちょっとしかできていなかったので、その償いとして2日間の有休をこの子のために使った。昨日は鎌倉にいき砂浜を歩かせようと思ったのだが、あいにく風が強く砂嵐のようになっていたので、散歩は断念した。ただし、強風で大きくゆれる波に太陽の光が反射して、白くうねるようにうごめく水面はえもいわれぬ美しさだった!
そして昨日は箱根へ。例によって箱根湯本からバスに乗って芦ノ湖湖畔まで行き、湖畔を少し歩いた。こちらも期待していた富士山は見えなかった。
コロナの影響で外国人観光客もいなくて、おまけに平日だったので閑散としたものだった。実は僕はここで外国人観光客とふれあうことが好きである。というのも、欧米人(特に英米人)は見ず知らずの人でも人によっては目配せをしたり、軽く挨拶をする人がいるからだ。とにかく、本質的に旅好きな僕はこの小さな二つの小旅行を十分満喫できた。ありがたかった。
話題は変わって、今年僕の信仰する組織で信者証というものを信者全員に発行しているのだが、それが新しくなるというので新しいものをいただいた。入信してからもう12年になる…入信しても当初の真剣味を失い形だけの信仰になったり、信仰そのものを捨てていく人々もいる中で、僕は今でもほぼ入信当時のままの想いでいる。12年という歳月を振り返ってみるとこれはほんとうにありがたいことだと思う。
この両者を分けるものは何なのだろう…おそらくだがそれは信仰を持つに至った動機、理由、というものと深い関係があるのではないかと思う。
だれか親しい友達や家族から誘われたから、入るとなんかいいことがありそうだから、あるといわれたから、といった動機で入る人々は…おそらく熱意を失うのも早いだろうと思う。
あるいは、なんらかの社会的、経済的、人間関係的な問題に苦しみ、それの解決を求めて入信してきた人々もまた、同じようにそれらの問題が解決するとおそらく熱意を失っていくのではないだろうか。(もちろんそれらの動機で入信することが悪いといっているわけではない)
それにたいして入信に至るまでの間に、なんらかの個人的な悲劇、大きな罪の意識、道義的な葛藤(善と悪の問題、とくに自らのうちに潜む善悪の問題)というものにさいなまれどこにも出口が見いだせないで苦悶していて、信仰に救いを見出そうとして入信した人々はその信仰を捨てることは少ないのではないか(その信仰がその人の抱える問題に相互的に答えてくれるものである限り)。
このような問題を抱えている人々にとって、キリスト教や僕の信仰のように絶対的な善とそれによる受容というものを中心に置いている信仰は、いちどそれにいだかれればそれを捨てることはまずありえない。そのような人々にとっては、信仰すればなにか目の前にある具象的な問題が一気に解決するとか、大きな物理的、社会的利益があるとかは、ほとんどどうでもいいことである。
自分の存在、存在している意味、価値、それそのものが崩壊していく危機の中で、すべてを知りながら受容しそこに存在する意味、価値を与え、その過程の中で自分の問題そのものを根本的に変質させてくれるもの、そのような信仰の対象である限りそれを捨てることなどはあり得ない。
いいかえると、善を希求する意識、意志、がその人の存在の本質を決定ずけるほどの意味を持っている人であればあるほど、一度得た信仰を捨てることはあり得ない。なぜならそれは自己を完全否定することと同じだからだ。どの信仰であれ信仰というものを核心までつきつめていけば、最後はそこに突き当たるのではないか。
今、「親鸞」という本を読んでいるのだが、親鸞が法然の教えを暗闇の中でまさぐるように求めたその Cause 動機はそこにあったのではないかと思うようになっている。
ただ、残念なことに彼の教えを求めて集まってくる人々の中の大多数は、それよりもむしろ、死後の浄土、往生だけを求めていた……そこに親鸞の根源的な孤独があった…と僕は思うようになっている。それがどれほどの孤独であったかは想像するに余りある、しかし、かれはそれでもよい、それでもよい、この現世の苦悩にさいなまれている人々に希望を与えることができるならと考えたに違いない。
この孤独はおそらく、キリストも、ブッダも、あるいはあの孔子も抱いていた孤独であろう。と同時に、彼らは知っていた、そのような大衆の中にも、善悪の崖の底で苦悶している人々がいることを、あるいは未来にはそのような人々が生まれることを。そのような人々にもよりそい、そっと肩に手を置いてあげたかった。だからこそ彼らは『その孤独』に耐えることができたのだと思う。
電車の中で「親鸞」を読みながらそんなことを考えていた。