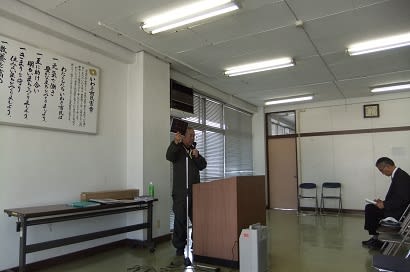
熊澤 幹夫先生の講演の姿です。
片寄平蔵石炭発見の道
5人目の講師は
熊澤 幹夫先生・・・いわきヘリテージ・ツーリズム事務局長
先生は
いわきの近代遺産のガイドをされているそうです。
1)江戸末期の藩領
幕領・平藩・泉藩・湯長谷藩・棚倉藩・笠間藩・多古藩・の7つ。
岩城家→鳥居家→井上家→内藤家→安藤家の5つの歴史。
2)片寄平蔵の石炭発見について
明石屋14代の影響(廻船問屋・材木商)・・・塩がメーン。
明石家屋と平蔵の関係→石炭発見へ。
明石屋の存在がなければ
平蔵は石炭を発見できなかったのではないか?
3)江戸までの運搬経路・・・販売するには江戸に運ばなければならなかった。
弥勒沢→中の作港→江戸
いわきの各港→那珂湊港→川船・涸沼の海老沢河岸→陸路・吉影→小舟・串引
→高瀬舟・北浦を通り→利根川を遡り→関宿→江戸へ。
※銚子沖は荒れていたのでこのような経路で運ばれた。
4)明治初期の採炭の状況・・・中央財界参入前
日本抗法施工前後の採炭場所等
西南の役で九州からの石炭が入らず常磐の石炭で儲けた。
5)中央財界の石炭経営に進出
①山崎藤太郎のお話・・・小野田炭鉱を設立
②浅野総一郎のお話・・・磐城炭鉱社を設立
③採炭夫の変化・・・中央資本の導入前・・・主に地元・
中央資本導入後・・・・飯場制度による友子(とのこ)制度が主。
④友子制度:鉱山鉱員を集め飯場に泊め専門性を帯びた技術者を導入した。
3年3か月以後6年6か月働けば披露して名札をもらえた。
名札はどこでも使えることができた。
健康保険制度がない時代・互助会制度も行われた。
⑤山元から港までの運搬の変化のお話
馬車軌道の活用(明治20年)・・・小野田から港まで
加納作平の挫折・・・旧来の採炭業から脱せられなかった。
⑥運搬経路・・・銚子沖を通り東京湾に入るコース(事故の発生が多い)
・・・海難事故が・・・保険がない時代(浅野は保険業も始めた)
運搬船の座礁、沈没等→運搬コストのUP
茨城・神永喜八も海難事故で失意のうちに亡くなる。
鉄道の必要性が高まる!!
常磐線 平~水戸間開通・・・明治30年2月5日
参考文献:
☆いわき市史・・・・・・市史編纂委員会
☆内郷市史・・・・・・・市史編纂委員会
☆片寄平蔵実傳・・・・・執筆者 本多徳次
☆加納家と石炭・加納邦武を偲ぶ・・・猪狩勝巳
☆常磐炭田史・・・・・・清宮一郎著
☆ハワイアンセンター物語・・・執筆者 猪狩勝巳
☆福島人物の歴史 第10巻 白井遠平・・・執筆者 高萩精玄
☆いわき地域學會図書 新しいいわきの歴史・・・編集 編集委員会
ヘリテージツーリズムとは:
観光人口を増やそうということで、
ガイドを中心にやられる目標で設立され
現在は炭鉱や施設の案内・解説をされています。
熊澤先生
ガイドの仕事を通した
いわきの近代産業の歴史のお話
ありがとうございました。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます