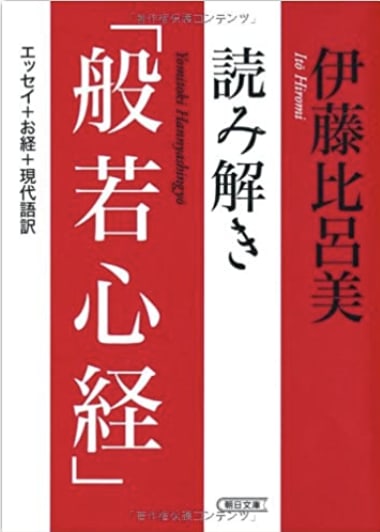@身内が病人となり、延命しない人生を看取るまでの姿を綴った本書、お経とともに描いた思いは身に沁みる。菩薩、如来など「般若心経」「観音経」、ブッダ、釈迦の「法句経」、特に「法句経」はむしろ人生訓、箴言集、自己啓発書という。「無常偈」にある「常なるものは何もない。生きて滅びる定めである。生き抜いて、滅び果て生きるも、滅ぶもないところに 落ち着く」は心に残る。
『般若心経』伊藤比呂美
「概要」死にゆく母、残される父の孤独、看取る娘の孤独。
苦しみにみちた日々の生活から、向かい合うお経。
・読み解き「懺悔文」 女がひとり、海千山千になるまで
「我昔より作りし所の諸々の悪行は、皆無始の貪瞋痴に由る。 身と語と意より生ずるところなり、一切を我今皆懺悔して奉る」
貪瞋痴:貪る心・思いのままにならぬ怒る心、知ろうとしない愚かな心
・読み解き「香偈」「四奉請」 おはいりください
・読み解き「般若心経」 負うた子に教えられ
・新訳「般若心経」
生老病死・愛別離苦・怨憎会苦(人間が切っても切れない四苦八苦)
・読み解き「発願文」忘れること忘れないこと
人は昔の確執、諍いを思い出す(忘れたという思いが思い出す)
・読み解き「大地の歌」浄土をさがして
・読み解き「ひじりたちのことば」いぬの話
延命治療をしないという意味「口から食べられなくなった老人をそのままにしておくのは、医療従事者としても家族としても大変辛いものだんですよ、生きながらミイラになるのを見ているわけですから」
・読み解き「白骨」ほらほらこれがぼくの骨だ
「骨拾い」で「もっとダディーに教えてもらいたいことがあった」と泣きながら・・・
・読み解き「観音経」あなたにはかんのんがいる
・読み解き「地蔵和讃」母が死んで、父が残った
・読み解き「七仏通戒偈」「無常偈」いつか死ぬ、それまで生きる
「諸悪莫作 諸善奉行 自浄其意 是諸仏教」(悪い事をするな 良い事をしなさい 清い心を持ちなさい これが仏の教えだ)
・読み解き「四弘誓願」ぼんのうはつきません。あとがきにかえて
・無常偈「諸行無常 是生滅法 生滅滅己 寂滅為楽」(常なるものは何もない。生きて滅びる定めである。生き抜いて、滅び果て生きるも、滅ぶもないところに 落ち着くのだ』