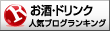平成26酒造年度(今年の秋から)の季節雇用の蔵人を募集します。
募集人員 1名
期間 平成26年10月中旬頃~平成27年3月下旬頃(季節雇用)
資格 特にないが、健康で身体が頑強な人
年齢 20歳以上~概ね50歳くらいまで
経験 全く経験がなくても可能ですが、その場合は苦労すると思います。経験者(即戦力)歓迎します。
その他 志太泉は能登杜氏ですが、経験者の場合は杜氏集団は問いません。原則蔵に泊り込みの作業となります。(地元で通勤を希望する場合は応相談)。喫煙者でも可能ですが、採用において、応募者の他の条件がほぼ同じの場合非喫煙者を優先します。
その他 清酒退職金共済については応相談となります。
その他、詳細は、お電話でお問い合わせください。電話054-639-0010(担当 望月雄二郎)
今年は、過去最高に苦労する年です。
正確に書くと、「今年は、過去最高に製造計画に苦労する年です。」
酒は、米と水から造るもの、だから製造計画はというのは、「精米歩合××%の〇〇という米を×××KG使ったこういうお酒(本醸造とか純米酒とかという種別です)を何本造る計画」というものを集計したものです。
という事は、志太泉酒造で〇〇というお米が全部で玄米で何キロ入荷するのか?それがわからけば計画が立てようがありません。
この入荷数量が、今年は、何度も何度も何度も変更になってます。
そのたびごとに、製造計画変更です。杜氏も私もほとほと疲れました。
でも、普通の製造業としてに考えれば、必要な数量注文すればいいんじゃないという事になります。でもお米(酒造好適米)というのは、そうはいかないのです。なんで、そうはいかないかはまた気分しだいで書きます。
今年ももうすぐ酒造りです。
今年の清酒製造設備は、大きな変化はないです。
ひとつ変わるのは、冷水製造装置が新しくなります。
冷水業界というのに、一般の人はあまり一生関わることはないでしょうが
食品・飲料系で、特に日本酒業界ではだいたいの人が知っている「第一工業」http://www.firstline.jp/index.html
の「ファーストブラインチラー」が導入(更新)されます。
ファースト=第一
ブライン=冷媒(不凍液)
チラー=冷却器
です。
これで、何がよくなるかというと、低温仕込水が安定供給できるという事です。
仕込中に冷たい水がたくさん出来ていると心が豊かになります。
今年の秋からの酒造りの蔵人を引き続き募集中です。
http://shidaizumi.com/brewing/touji/touji.htm
志太泉で酒造りをする
メリットとしては
①初年度から、酛屋か釜屋か船頭かいずれかの担当として責任をもちます。
これは、経験がなくても同じです。
②豪華ではないが食事が美味しいと思います。
③(20~40代の人にとっては)スタッフの世代が近い。
デメリット
①朝が早くから作業がはじまり、忙しい。
気持ち次第で、酒造りの技能は学べる環境です。
平成25酒造年度(今年の秋から)の季節雇用の蔵人を募集します。
募集人員 1名
期間 平成25年10月中旬頃~平成26年3月下旬頃(季節雇用)
資格 特にないが、健康で身体が頑強な人
年齢 20歳以上~概ね50歳くらいまで
経験 全く経験がなくても可能ですが、その場合は苦労すると思います。経験者(即戦力)歓迎します。
その他 志太泉は能登杜氏ですが、経験者の場合は杜氏集団は問いません。原則蔵に泊り込みの作業となります。(地元で通勤を希望する場合は応相談)。喫煙者でも可能ですが、採用において、応募者の他の条件がほぼ同じの場合非喫煙者を優先します。
その他、詳細は、お電話でお問い合わせください。電話054-639-0010(担当 望月雄二郎)

平成24酒造年度の酒造りも終わりに近づきました。
最後の作業は火入れとなります。
通常釜はお米を蒸す為に使われますが、最後だけは火入れに使われます。
写真の右側のホースから冷たい酒が入っていきます。
釜の中には、蛇管と呼ばれる、らせん状の管があり、釜の内部の湯に浸かっています。
(湯が管を温め、管が通過する酒を温めるので酒とお湯が混じる事はありません)
左側のホースは出口につながっているいます。
その手前に温度計がありますが、ここでの温度は摂氏60度第後半です。
出口のホースから密閉タンクに熱酒が送られます。
密閉タンクが満了すると、タンクの外側に水をかけて急冷していきます。
火入れの作業中は、少しカラメルっぽいお酒の香りがします。
子供のころは、冬はまったく酒蔵の中には入りませんでしたが
志太泉は蔵の外(入口)に釜があるので火入れの作業だけは香りとともに記憶があります。
現状でも、この工程は、かなりの部分が違う方法に置き換えられております。
将来的には、この作業は、いつかなくなる作業かなと思います。
少しさみしい気持ちもします。
以前もいつかとりあげた事はあるかもしれないが
蔵元あるいは杜氏さんの人格とその酒質が似てくるのではないかという日本酒の世界の大いなる問いがある。
厳格な蔵元さんはシャープな酒を造るとか。やさしい杜氏さんはまるい酒を造るとか。
いちばん極端に言えば、良い人は良い酒を造るとか。
これについて、私は以前より『酒質と人格は別物』であると大いに主張してきた。
これに関しては、今も全く変わっていない。
『最悪の人間が最高の酒を造ることもある。』
そうでなきゃつまんないだろう。
但し、昨年頃から一点大きな譲歩をしようかと思っている。
『酒質と人格は別物』であるが、その蔵元のすべてのスペックの酒を『同一方向にもっていこうとする』か、スペックごと『酒の中に多様性を求める』のかは、性格によるものだろう。
※人格も酒質も嗜好品のため、本来問い自体が間違っています。
今期は、設備としては変更はないです。
ただし、薮田式自動醪搾機(酒造業界ではやぶたと呼ばれる)の部品を交換しました。
薮田式自動醪搾機とは、こういうものです。
http://www.zjkk.or.jp/entry/ybt/ybt-moromi/ybt-moromi.htm
日本酒業界の自動で醪を搾る機械の市場で正確な数字はわかりませんが、圧倒的なシェアがあります。
部品とはいえ、ポンプとこのアコーディオン状のろ過板の一部を交換したため、200万近い出費となります。
日本酒用の機械は、量産されていないためとても高いです。
12月から3月はじめまでだいたい毎年午前中から酒飲んでます。
正確にいうと、その日にしぼった酒の味見をしています。
ほとんどの場合、飲み込むことはないです。
でも、急に電話がなったりするとごっくんと飲む事もあります。
それでもひとくち以上飲むことはないです。
一応これは仕事です。
基本杜氏と、色、香り、味について評価と要因とこれからどうするかの話とします。
評価について杜氏と意見がわれるということはほとんどないです。
これは、その前段階のもろみを見ている以上、もろみの印象による酒のイメージがある程度、相互に固まってるからです。
自分のところの酒でなくても、評価がわれることはあまりないです。
ある酒を蔵元が10点満点で9点というの杜氏が8点という事はあっても、蔵元が5点というのを杜氏が9点ということはないと思われます。(各酒を10秒で100点以上の酒を評価すればそういうこともあるかもしれん)
まあ、蔵元も杜氏も完全な味覚のシンクロから同じ理想の酒への道すじというストーリーが美しいかもしれませんが、そういう美談に対しては個人的には懐疑的であるべきだと思います。
蔵元も杜氏も志太泉を飲んでるのが、いちばん多く、似たような食べ物を食べてるので、味覚のガラパゴス化が進行してるかもしれません。
あー、評価については『2つのものさし』という大したことない話がありますが、それはまた今度気が向いたら書きます。
ここ数日は寒いです。
寒さというのは、蔵元にとっては基本うれしい事です。
寒くなるとやっぱり酒(日本酒)も売れます。
志太泉も蔵全体を空調しているわけではないので、外気温が寒ければ、蔵も冷え、外気温が暖かければ、蔵の室温も上がります。
当然もろみの低温管理は寒いほうがやりやすいです。
ぜいたくをいうと安定的した寒さが続いてほしいです。
それが無理なら逆にずっと暖冬のほうがよいです。
いちばん難しいのは、日替わりで、暖かくなったり、寒くなったり、雨になったり、乾燥したりすることです。
もちろん、それぞれの気象に応じて対応はしますが、ニュースの天気予報も蔵で予想する天気もはずれることもあります。
寒くて逆に不利になるのは蒸しです。あと寒さが続くと疲れもたまります。
それでも、寒い日は、良い事がたくさん。悪いことが少しです。