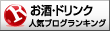世の中には、大人でも子供でも取れる資格もありますが、これは大人の資格それもとてもマイナーな資格のお話です。
今年の夏「清酒専門評価者」という資格を取得しました。
正確さを欠いてイメージだけ表現すると「清酒の鑑定士」みたいな資格です。
ゆえに、子供は「清酒専門評価者」にはなれません。
詳細はこちらです。
http://www.nrib.go.jp/kou/h26ssh.htm
資格を取る前に、その講習を受けなければならないというのは資格業界ではわりとある事ですがなんと(東京で)平日4日間連続の講習を受けなければならない。というのは、かなりハードルが高いです。
しかも、まず
(1) 大学(短期大学を含む)の農学・食品・生物系学科卒業以上
(2) 職業能力促進法に基づく酒造技能士2級以上
(3) 「酒類醸造講習(清酒上級コース)」又は「清酒製造技術講習」(当研究所及び日本酒造組合中央会の共催)の修了
(4) 「実践きき酒セミナー」((公財)日本醸造協会主催)の全部門の合格
のどれががないと、講習を受けられないのです。
私は、農学系でも、食品系でも、生物系でもないので昔とった(4) が受講資格となります。
それで、以下の内容の講習を受けました。
1 基本味及びにおいの識別 基本味及び金属味の識別試験
Open Essenceによるにおいの同定能力試験
2 酸味及び甘味の差異の検出 3点識別法による試験
①清酒に酸を添加した識別試験
②清酒に甘味を添加した識別試験
3 香味強度の順位付け 順位法による試験
①アルコール、②甘味、③酸味、④酢酸イソアミル、⑤カプロン酸エチル、⑥イソバレルアルデヒド
4 においと味の記述及びその由来 標準見本を用いたにおいと味の確認及びその由来に関する講義及び訓練
試験:標準試料のうち任意の5種類×2のにおい試料について特性を回答するとともにその由来について回答する。
5 有機酸の味の識別 マッチング法による訓練
○有機酸(酢酸、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸)水溶液
6 熟度の識別 1:2点識別法による訓練
統計処理(仮説検定)に関する講義
○火入れ酒及び生酒の貯蔵後
7 記述的試験法 記述的試験法(プロファイル法)及び尺度評価の訓練
統計処理(分散分析)に関する講義
①純米酒(特徴に差があるもの6点)
②吟醸酒(特徴に差があるもの6点)
試験:記述的試験法による試験
①純米酒(特徴に差があるもの3点)
②吟醸酒(特徴に差があるもの3点)
8 同一製造者製品の識別及び香味の記述 マッチング法による識別及び記述的試験法の訓練
○同一製造者製品6点
吟醸、純米吟醸、純米、本醸造、特撰、上撰等
4日もあると内容多い。
このうち、1.2.3.4.7に対して試験があります。
これは、全科目一括合格でなくても、部分合格なら不合格科目だけを再受験すればよい仕組みです。
(次回に続く)