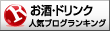昨夜の静岡県東部地震で蔵に被害はございませんでした。
お問合せ等をたくさん頂き誠にありがとうございました。
3月23日の静岡県清酒鑑評会一般公開の会場にて震災に被災された方に対して義援金を募集いたします。
これは、静岡県酒造組合静酉会が主催し
静岡県酒造組合を通して被災者の方に責任をもって届けさせて頂きます。
こんな情況の中で一般公開にご参加頂けるだけでもありがたいことでございますが
ご賛同頂ける方は、何卒ご協力よろしくお願い申しあげます。
地震に大変な事態となっているようです。
様々な形で多くの方が被災されたおられるようです。
少しでもそれぞれの方の事態が好転することを祈念いたします。
本日、静岡県清酒鑑評会が開催されました。
吟醸酒、純米吟醸部門とも入賞しました。
首位は、吟醸部門が正雪。純米吟醸部門が磯自慢です。(敬称略)
例年であれば、詳細順位も午後4時30分ごろにはわかりますが、今年は静岡県酒造組合からもまだまったく連絡がありません。東名高速も通行止めのようです。
改めて、地震で被災された方の被害が軽い事を願っております。
18日は静岡県清酒鑑評会一般公開でした。
http://www.shizuoka-sake.jp/prize/h21_report.html
(以下敬称略)
吟醸酒部門では、首位の開運が抜群の出来栄えでした。
静岡型の香りでありながら、香りに華やかさがあり
味も透明感がありつつ適度な味幅もかね揃えた美酒でした。
上位の中では、正雪がいかにも正雪らしい香りのバランスと
ソフトで欠点のない酒で印象に残りました。
純米酒部門は、鑑評会的な基準で
全般的に差が少ない年ではないかと推察します。
2008年12月6日にSBS学苑パルシェにて開催された
第三回静岡県純米酒鑑評会にて
志太泉 純米酒が首位となりました。
http://sake.eshizuoka.jp/e215235.html
消費者の方の審査でご支持を頂けるのは
全国鑑評会等の審査員が国税庁鑑定官や県の技術者や蔵元代表といった
業界に中のエキスパートによる審査で好成績を修めるとは
また違った意義があると思いうれしく思います。
第2回静岡県本醸造鑑評会の結果が発表されました。
http://www.marukawaya.com/koza/kanpyoykai/honjo2008.html
静岡県清酒鑑評会吟醸の部と比較すると
(①静岡県本醸造鑑評会 ②静岡県清酒鑑評会吟醸の部として)
■審査酒
①本醸造市販酒 28酒
②大吟醸斗瓶取り
■審査酒の準備方法
①酒販店からの買取
②蔵元が搬入
■審査方法
①実際に飲みながら、食べながら(ブラインド)
おつまみもあり今回は「豆腐」「キュウリの漬け物」「トマト」「カツオの鉛節」
②口に含んで審査後吐き出す(ブラインド)
■審査基準
①各自の好み
②酢酸イソアミルの香り>カプロン酸エチル香り
■審査員
①一般消費者
②沼津工業技術支援センター 国税庁鑑定官 酒類評論家 東京農業大学 蔵元・杜氏代表他
本醸造鑑評会は、実際の飲酒に近い形であることがよくわかります。
こちらで、今年の志太泉の市販酒(特別本醸造)は2位となりました。
通常の公式の鑑評会とは全く土俵の異なるものですが
それぞれが当然意味のあるものであり
上位にランクされた事は大変光栄です。
「メロンのようなフルーティーさがやさしくふくらみ、さわやかに
切れるので、美味しい。」
というご意見を頂いたと伺いました。
個人的には、この本醸造は派手さはなく透明感のある酒質だと思います。
力強い酒の中でその魅力をご評価頂いた事は大変うれしく感じます。
今年より、表彰は行なわず評価のみ行なうということになり
志太泉の純米も成績が良好と認められました。
25日の静岡県の鑑評会と全く異なりほとんど香り高い酒でした。
特にM県のコーナーは、格別の香りの高さでした。
審査で高い評価を得た酒は、香りが高く低酸で味がソフトで官能的に甘いものが多く
次いで香りが高く、比較的味があり酸や旨みがバランスよい酒が多かったです。
香りがあまり高くない酒は、ほぼ評価されなかったです。
25日の結果と好対照ですが、どちらも審査における評価基準が審査員に徹底されていたように感じます。
これは、非常に良い事だと思われます。
今年は、カプロン酸エチル系(強い林檎様の香り)が強い酒は、ほぼありませんでした。
(例年ですと、もう少し出品されていました。)
吟醸の首位、喜久酔さんの酒は、上立ち香も含み香も上品で香り高く味はきれいで丸く全く完璧でした。私が酒を利いた約10年の間では、数年前の忠正さんの首位賞の酒とこの酒の二つが静岡に出品された酒の中で最も優れていると個人的に思います。
全般的に、米のせいか、気候のせいかレベル近年では高かったです。
純米部門は、ずばぬけて印象に残る酒はありませんでしたが、上位の酒はいずれも各蔵の個性が発揮された銘酒ぞろいでした。
静岡県清酒鑑評会で入賞する酒は、ほぼ全国新酒鑑評会で金賞はとれません。
全国新酒鑑評会で金賞をとる酒は、ほぼ静岡県清酒鑑評会で入賞しません。
ここが出品酒選びを難しくしている理由ですが
その件はまたの機会に書くとして
吟醸部門は2点、純米部門は2点までの出品となります。
純米部門は3点まで選びましたが、後の2点はどうするか田中杜氏に一任しました。
なかなか3点ともかなり似たタイプで決定は難しかったです。
吟醸は、2点はっきり違いのある酒を出品します。
ちょっとブログをさぼっていました。
ブログを含むネットへの方向性をちょっと迷っていた面もありますが
迷っていてもしかたないので再開します。
7月7日に第1回静岡県本醸造鑑評会が静岡の丸河屋さんの主催で開催されました。
詳細はこちらです。http://www.marukawaya.com/koza/kanpyoykai/h01_2007007kekka.html
この鑑評会では、極めて公平な審査が行われております。
私は、個人的にこのような試みがいろいろな形で行われ
ネットを通じて発信されていく事はとてもよい事ではないかと思っております。
今回は、本醸造というそんなに値段の高くない酒の市販酒で行われた点
は非常に意義のあることだと思います。
お酒の評価は極めて多面性をもつものですから
たとえばとびきり燗で美味しい酒とか燗ざましがうまい酒とか
真夏の快晴の日に一日野外に出しておいてへたらない酒とか
いちばん最中にあう酒とかなんでもありではないでしょうか。
仮にそんなのがあったとしても笑ってあげる余裕は必要ではないでしょうか?
ただし、ネットで発信されている情報を個人としてどう取捨選択していくか
ネットリテラシーの能力がお酒に限らずより必要とされていくでしょう。
今年は、南部杜氏協会の優等賞累計15回の十五回賞も頂きました。
表彰式は岩手県ですのでさすがに例年どおり出席出来ず
出席した田中杜氏より本日賞状が届きました。
志太泉は、戦後直後を除きほぼ一貫して南部杜氏です。
積み上げてなんとか15回重ねる事が出来ました。
二十回賞が頂けたらぜひ岩手の表彰式に行こうと思います。
盛岡で冷麺を食べた後花巻温泉も行ければ行きたいです。
①全国新酒鑑評会への出品者数は
1065者(平成14年)⇒1049者(平成15年)⇒1019者(平成16年)です。
②製造業者数の推移(すべての製造免許を持つ蔵の数)は
1904者(平成14年)⇒1836者(平成15年)⇒1782者(平成16年)です。
①/②の出品率は
56%(平成14年)⇒57%(平成15年)⇒57%(平成16年)です。
実際に酒造りをしている蔵の数のデータは、完全にはわからなかったのですが
製成数量別の企業数の推移というデータの中の専業割合50%以上の蔵の数字は
かなり近いと思われます。
③この数字は
1462者(平成14年)⇒1407者(平成15年)⇒1367者(平成16年)です。
①/③の出品率は
73%(平成14年)⇒75%(平成15年)⇒75%(平成16年)です。
この3年度を比較する限りは
ほぼ出品数の減少は、蔵の数の減少に比例したものです。
皆様から多数のご祝辞を頂きありがとうございます。
せっかく読んで下さる方の対してなので
私の全国鑑評会に対する一つの見方を提示します。
もちろんこんな事は当たり前に考慮してる人も多くいるでしょう。
全国鑑評会は、常識的には精米歩合35-40%の大吟醸仕込みから出品されます。
どんな蔵でも仕込みが成功する事も失敗する事もあるでしょう。
でもこのスペックの仕込みを何本仕込んでいるかは蔵によって
全く異なります。
小規模の蔵では1本の事が多いため、これが失敗に終われば
金賞はほぼ絶望的になります。
仮に10本仕込んでいればその10本の中からベストを選ぶ事が出来ます。
だから金賞の受賞率においては、単年度の大吟醸もろみの仕込み本数が
通産回数においては連続的な酒造年度における平均
大吟醸もろみ仕込み本数が重要なファクターの一つになります。
だからおそらく仕込み本数の少ない蔵の金賞はさらに価値がある事だし
また通産回数の多い蔵というのは、その蔵がコンスタントに
大吟醸もろみの本数を仕込める実力がある蔵だなと推測したりします。
もちろんこれは極めて多くのファクターの一つにすぎません。
さて全国新酒鑑評会の発表は21日という事ですが
平成18年度出品状況が公開されました。
出品点数は981点です。
平成14酒造年度から毎年平成18酒造年度まで並べると
1065(14)⇒1049(15)⇒1019(16)⇒997(17)⇒981(18)
と出品点数は着実な減少傾向にあります。
まあ蔵の数も減った影響なのか、鑑評会ばなれが進んでいるのかは
わかりません。
実際にその年度の酒造りをした蔵の中での出品率がその判断材料に
なるかもしれませんから今度調べてみようと思います。
全国鑑評会は原料米が山田錦部門(山田錦使用率50%以上 Ⅱ部)
とその他部門(その他の米使用率50%以上 I部)に分かれています。
I部の出品数を平成14酒造年度から毎年平成18酒造年度まで並べると
84(14)⇒71(15)⇒98(16)⇒98(17)⇒118(18)
とこちらはほぼ着実に増え、出品酒における酒造米の多様化は
蔵元で進んでいるようです。
また、その他の米の使用している蔵の多い地域は
仙台、関東信越、広島の国税局の管轄地域でやはり
その土地の酒米をもつ地域です。
5PPM未満のグループ(280点)Aグループ(香りが低いグループ)
5-7PPMのグル―プ(494点)Bグループ(香りが中位のグループ)
8PPM以上(245点)Cグループ(香りが高いグループ)
の金賞率がAグループ20% Bグループ30% Cグループ23%と言う事で
金賞率にはあまり違いがないという事です。
ところが入賞率には歴然とした違いがあります。
グループ別の入賞率は
Aグループ45% Bグループ53% Cグループ58%
明らかに香りが高い酒の方が入賞率が高くなっています。
この事実から何を読み取ればいいのでしょうか。
実はこの後、香りの高低による特徴という部分で以下のように
記述されています。
香りが高い区分のものは、香り不調和の傾向がある。
一方、香りが低い区分のものは、渋みの指摘が少なく、
酢酸エチル臭及び濾過臭の指摘が多い。また高い区分の
ものに比べ、木香様臭の指摘が多い傾向がある。
私なり解釈すると
香りが高い酒は、酢酸エチル、生老ね、つわり香等
マイナス評価される部分をすべて覆い隠す化粧のような効果
があるのでとりあえずなにがなんでも入賞したいときは
とにかく香りの高い酒を出す戦略が有効。
(注 酢酸エチル濃度に関しては、統計的にカプロン酸エチル
と逆相関はあるが、個人的に、根拠はないがお化粧効果の方が
大きいような気がしている。)
反面厚化粧がすぎるとカプロンばなれとか
香味不調和となる危険性もある。
ただし、蔵元や杜氏にとっては金賞と入賞では雲泥の差なので
やっぱり香りはカプロン酸は6PPMぐらいのいい感じかなあ。
志太泉を含めほとんどの蔵では、社内でカプロン酸エチル濃度
は測定できません。だから感で計るしかないです。