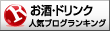もしも来年の101回以降も同じように全国鑑評会を続けていても、いつまでも日本酒業界内の中でのコンテストとなるんではないかと思う。
それは、それで価値のあることである。
ひとつ実現可能なことは、現在と全く同じ審査をして金賞を従来通り発表するのに加えて、評価の1位を発表するというのではどうだろうか?
あるいは、10位までを発表して、その10位までのお酒を現在池袋でやってる一般公開の時に審査委員が結審するあるいは(ブラインドで)一般投票して1位をきめるのをテレビ中継してもらうとか。
結局全国で約250の蔵が金賞という幸福を横並びで分け合ってるのは、平和で波風は立たないが、ニュースとしてのインパクトは薄いのだと思われる。
参加蔵数が減少傾向にあるとはいえ、この全国鑑評会は日本酒最大のコンテストであることは間違いない。だから、そこで1位を取る蔵には、「今年の日本酒NO1の○□■△蔵に決まりました」と、メディアに最大限露出するように、日本酒造組合中央会がそれなりの仕掛けをしてあげればいいんだと思う。やっぱり一位というのはニュースとして価値があるから、少なくともいまより注目されると思う。
ただし、おそらく100%近く、これは実現しないだろう。
理由は次回。
今日は、静岡松坂屋にいきます。よろしくお願いします。
配達をしてから行きますのでお昼頃からとなります。
昨日は、日本酒業界の様々な方々から、お祝いの言葉を頂き、感謝しております。
本当にありがたいことです。
昨日の夕方からは、めずらしく藤枝法人会というところの会に参加しました。
(サラリーマンの方だと、イメージしにくいですが、地方のある程度商売を続けている自営業者というのは、商工会議所、法人会、青年会議所等の組織に加入している場合も多い。)
当然のように、全国新酒鑑評会の事は誰も知りませんでした。
今日の静岡新聞を見ましたが、どこにも、全国新酒鑑評会のニュースは載っていませんでした。
YAHOOのトピックスにも園山真希絵さんは載ってましたが、全国新酒鑑評会のニュースは載っていませんでした。
つまり、全国新酒鑑評会は日本酒業界では、昨日一番の話題であるが、
藤枝のローカルコミュニティでも、全静岡県的な報道でも、全日本のネット上でもほとんど知られてないという事です。
そりゃあAKB総選挙じゃないので、知られなくても当然といえば当然です。
ただ、少し寂しいなという気持ちはしました。
100回目の記念となる全国新酒鑑評会で金賞を受賞することができました。
今までも受賞できた年もできなかった年もありましたが、今年を合わせて16回目の金賞受賞となりました。
これも、多くの方々のご支援のおかげです。
ブログという媒体を借りて、厚く御礼申し上げます。
静岡県では、三和酒造様、磯自慢酒造様、土井酒造場様、当蔵の4蔵が金賞を受賞されました。
昨年は土井酒造場様のみ金賞受賞でしたので、今年はよい結果となりました。
但し、昭和61年度の10蔵金賞受賞や平成2年度の12蔵金賞受賞に比較すれば、単純に数字は減っています。これをどう捉えるべきは、非常に難しい問題であり、言及する事はできません。
以下、受賞蔵のリストを見た印象です。
http://www.nrib.go.jp/kan/h23by/pdf/h23by_moku.pdf
・今年も東高西低の結果で、仙台局の成績が昨年に引き続き突出していた。
・地域的な入賞率は近年とあまり変わらない印象がある。
・福島県の受賞数が22、山形県16、秋田県16などが目立っている。昨年特に目立った宮城県は減少したがそれでも10受賞している。
・出品数は減少を続けてきたが、今年は876、昨年は875とわずかに増加した。100回記念だったらだろうか?
3月26日は
静岡県清酒鑑評会の一般公開、酒造会社対象の利き酒研究会、鑑評会表彰式に行ってきました。
一般公開は、月曜日のお昼という時間帯にも関わらず、多くのお客様にお越し頂き誠にありがとうございました。この一般公開が静岡県の酒を介在としたコミュニケーションの場として機能はしていると思います。
吟醸部門、純米吟醸部門の県知事賞のお酒をはじめ、多くのお酒が短時間になくなり関心の高さが伺えました。
酒造会社対象の利き酒研究会では、各社の出品酒を利き酒させていただきました。
吟醸部門では、今年は、光栄なことに結審まで選考されました。
《審査の流れ 1審(上位得点の酒が2審へ)→2審(上位得点の酒が2審へ)→3審(最高得点の酒が知事賞、最高得点が複数あるときは結審へ)→結審》
(以下敬称略)
《吟醸部門の印象》
知事賞(1位)の正雪の酒は、非常になめらかで上質の甘さがあり、その点で2位の志太泉より優れておりました。また例年のように静岡県らしい酢酸イソアミルの香りが爽やかでした。
また3位の磯自慢のお酒も、きれいな酒質と、やはり酢酸イソアミルを核としながらも磯自慢らしい特徴のある香りの素晴らしい酒でした。
この素晴らしいお酒の間にある2位の志太泉の酒でしたが、味の奥行きと香りのバランスが評価されたのではと考えております。
《純米吟醸部門の印象》
知事賞(1位)の開運の酒は、お酒がやわらかで香りも調和がとれておりました。
2位以下の酒は、それぞれのお酒の良さがありました。
志太泉(6位)の酒は、香りでは、蔵としての独自の香気バランス、味ではやわらかさやまるみはよかった点かと思います。
《全体の印象》
昨年の鑑評会と比較すると、全般的に味が甘く丸く感じました。
全国新酒鑑評会の要項が届きました。
日程
3月25日 申し込み締め切り
4月1日 出品酒搬入期限
4月20~22日 予審
5月10~11日 結審
5月24日 東広島 酒類総合研究所講演会
5月25日 東広島 製造技術研究会(酒造業界関係者の利き酒会)
6月15日 池袋 公開利き酒会
昨年からの変更点
山田錦の使用割合による出品酒区分の廃止
(山田錦使用部門とその他の米使用部門の一本化)
特に気づいた点
池袋の公開利き酒会では、原料米品種と純米酒かどうかが表示される。
ここ数年は池袋の公開利き酒会に行っており、東広島には、ずいぶん行っていません。
毎年行きたいなと思いつつ、やはり広島は遠いなあと断念しています。
普通にYAHOOの路線検索だと
藤枝~東広島で新幹線とJRで片道4時間半ぐらいと16120円かかります。
最近静岡から大阪に夜行バスが運行されるようになったので
夜中静岡を出発すると朝新大阪に着きます。6500円です。
この後、新大阪から東広島に新幹線を使うと9940円でちっとも安くなりません。
朝から普通列車のみなら5250円でお昼に西条に到着できますが
苦労の割にやすくならないなあという感じがします。
多分名古屋まで行ってそれから広島まで夜行高速バス(多分6000円ぐらい)で行くのが一番安そうです。
調べたけどいけるかどうかいまだにわかりません。
静岡県の杜氏組合主催の杜氏研究会が開催されました。
静岡県清酒鑑評会と同様に吟醸部門と純米吟醸部門の審査が行われました。
この審査では、静岡県清酒鑑評会と同様の評価基準で静岡県の現役杜氏
名古屋国税局鑑定官室、酒販店代表、卸代表、静岡県沼津工業技術支援センターの諸氏
が審査されます。
吟醸部門、純米吟醸部門ともまずまずの評価を得ることができました。
一般公開に時間帯に利き酒してきました。
今年の志太泉出品酒は、例年の指摘事項である渋みが少ないことが評価につながったように感じます。
◆名古屋国税局の総評◆
全般に酢酸イソアミルを主体にした佳酒がそろっていた。一部に吟醸部門では、酢酸エチル、純米吟醸部門では、ろ過ぐせがある酒が散見された。
西原杜氏が能登杜氏の若手による自主的な利き酒会トラディションに出席してきました。
トラディションは、各蔵の大吟醸新酒を持ち寄り、造り手が互いにブラインドで審査しあう会です。
志太泉の大吟醸の評価は、まずまずよかったです。
特徴としては、志太泉の大吟醸(明利酵母使用)でも香りがかなり高い部類に属する。
全国的には、能登杜氏の(全国鑑評会用の)酒は、カプロン酸エチルという尺度では、抑え目であるのではないかということです。
なかなか、現在非常に全国鑑評会で成績の良い仙台国税局管内の酒に比べると、香りが抑え目なため、欠点を指摘しやすいのではないかと言う事などを杜氏と話しました。
3月14日(水) 沼津工業技術センターにおいて、以下重要事項抜粋。
出品規定
H23BY製造酒
清酒の製法品質表示基準等に定められた区分により、吟醸酒部門と純米吟醸酒部門を設ける。
(両部門とも原酒で、酸度の制限無し)
審査方法
吟醸酒は、アンバーグラス、純米吟醸酒は蛇の目きき猪口により実施。
審査方針
静岡県清酒鑑評会としてふさわしいものは、調和のとれた香り(酢酸イソアミルとカプロン酸エチルのバランスがよく、酢酸イソアミル>カプロン酸エチル)で味はきれいで丸い酒である。
審査は3点法。
一般公開
3月26日(月) 正午~午後2時
場所 JR静岡駅前アオイタワー GRANDAIR(ブケ・トウカイ)
車で来てはいけません。
名古屋国税局酒類鑑評会製造技術研究会という極めて大仰な名前の会ですが、ようするに出品酒の利き酒会です。
以下は個人的な感想です。(敬称略)
伝統酵母吟醸部門は、静岡県の各蔵に加え醴泉、四海王、蓬莱泉も素晴らしいお酒を出品されていました。
一般吟醸部門では、正直言って、カプロン酸エチルが変化した酒もあり、春の方が、全体として美味しく感じました。その中で、女城主にやわらかな旨み、考の司に力強い味幅があり、ほしいずみ、ねのひは香り高い酒としてのきれいなバランスに優れていた感じました。
純米酒部門(45℃で審査)では、開運のバランスが絶妙で、白隠正宗も非常に良かったです。
本醸造部門(45℃審査)では、翁鷺(若竹)が濃度酒(アルコール度やや高め)の良さがお燗により引き出されていたと感じました。
一点だけ違和感を感じたのは、45℃の御燗審査とはいえ、純米酒部門では、複数の老ねた酒が入賞していたことです。
肯定的に捉えれば、従来の日本酒の審査法は、減点法であり、酒の短所を探す審査であり、それ自体が弊害である。それを酒の良さを見出す加点法に改めたという評価もできるのかもしれません。
「平成23年 名古屋国税局酒類鑑評会 吟醸酒伝統酵母部門」入賞しました。
こちらが、鑑評会概要です。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/60/index.htm
こちらが、入賞名簿です。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/60/meibo.htm
この、鑑評会の特徴は、吟醸部門が、伝統型酵母部門とそれ以外の酵母部門に分かれている事です。(名古屋国税局酒類鑑評会とは、わかりやすくいえば、国税庁主催東海4県日本酒コンテストです)
伝統型酵母とは、酢酸イソアミルを主体にしたおだやかな香りをもつ吟醸酒で、具体的には原則としてカプロン産エチルの含有量が、酢酸イソアミルの含有量を超えないことと出品要項に定められています。
伝統酵母の種類も定めれており、きょうかい6号から1501号酵母、岐阜G酵母、静岡県酵母のほとんど、愛知酵母FIA1、FIA2、三重酵母MK-1となっております。
静岡県の蔵元が、久しぶりに数多く吟醸部門で入賞しましたが、これは伝統型酵母部門への出品、入賞とも多かったのが理由です。
対照的に、岐阜、三重、愛知各県では、伝統型酵母への出品自体が、ほとんどなく、東海4県でも、静岡県とそれ以外の酵母に対する方針があらためてくっきり分かれました。
純米酒大賞制定委員会が主催する第3回の「純米酒大賞2011」の精米歩合70%以上部門において、「純米原酒 開龍」が金賞を受賞しました。
http://fullnet.co.jp/junmaisyu_taisho/2011/index.html
昨年も、準グランプリ(部門2位)を受賞しておりますが、今年も金賞(部門3位)を受賞しました。
「開龍」は地元藤枝市朝比奈産の山田錦を精米歩合70%精米にて仕込んだ純米原酒です。精米歩合70%ですが、仕込み方法自体は、ほとんど純米吟醸クラスと同じです。低温長期のもろみにて、旨みはありますが、きれいに仕上げています。
今年は全国新酒鑑評会は残念な結果に終わりました。
審査は相対的なものなので他の御蔵の出品酒と比較しないとなんとも言えません。
結果表(成績表のようなもの)が醸造研究所から来ましたら分析します。
静岡県では、開運さんが金賞を受賞されました。
土井専務の結婚に金賞受賞が花を添えました。
おめでとうございます。
3月23日の静岡県鑑評会の一般公開の報告です。
(敬称略)
今年は、静岡県のみならず全国を代表する南部杜氏である多田杜氏(磯自慢)と山影杜氏(正雪)のお酒が吟醸、純米吟醸部門とも1位2位を独占しました。(吟醸部門1位磯自慢 純米吟醸部門1位正雪)。
両部門の1位2位のお酒4種類はどれも素晴らしい出来で甲乙つけ難いですが、両部門とも1位はお酒としての華のある酒でした。2位の酒のほうがややまだ蕾を想起させるものでありました。
どちらが良いかと言えば、これは嗜好の問題と思います。ただ審査としては、蕾の酒より華のある酒を採るのは妥当だと思います。
志太泉の吟醸酒はやはり最後は精米歩合の差(志太泉の出品酒は精米歩合50%)が酒質の差となったかと思います。精米歩合40%の酒の質と精米歩合50%の酒の質には、厳然とした壁がありますが、挑戦し続けたいと考えます。