「道灌の山吹伝説」は、道灌は鷹狩りにでかけて俄雨にあってしまい、みすぼらしい家にかけこみ、「急な雨にあってしまった。蓑を貸してもらえぬか。」と声をかけると、
思いもよらず年端もいかぬ少女が出て、黙ってさしだしたのは、蓑ではなく山吹の花一輪。
花の意味がわからぬ道灌は「花が欲しいのではない。」と怒り、雨の中を帰って行った。
道灌がこのことを語ると、近臣の一人が進み出て、「後拾遺集に醍醐天皇の皇子・中務卿兼明親王が詠まれたものに「七重八重花は咲けども山吹の(実)みのひとつだになきぞかなしき」
という歌があり、その娘は蓑ひとつなき貧しさを山吹に例えたのではないでしょうか。」といった。道灌は己の不明を恥じ、この日を境にして歌道に精進すると云う伝説。
山吹伝説は越生の他にも各地に残り、豊島区高田、荒川区町屋、神奈川県横浜市六浦など。落語の「道灌」としても広く知られています。
高田の説には続きがあり蓑を
求められた家の少女、「紅皿」を後に江戸城に呼んで和歌の友としたという話や道灌が亡くなった後、紅皿は新宿区大久保に庵を建てて尼となったという。
道灌の父・道真(資清1411~1488)は扇谷上杉家・家宰として馬上に打ち物取っては並ぶものなき武将で、そのうえ連歌の達者としても知られていたのですが、
ある事件をきっかけに家督を道灌に譲ります。道灌23才、道真は44才でした。その後、道灌は江戸城、道真は河越城で活躍しましたが、道灌の背後には
つねにすぐれた師・道真がいたのです。また道灌自信も鎌倉の建長寺や足利学校に学び、幼少からずばぬけた秀才だったのだとも言われている。
父・道真は、越生の龍穏寺近くに「さんしあん」と呼ばれる砦を築き、ここは秩父往還の要衝に位置する山上にあり、後に小杉周辺の「自得軒」と呼ばれる屋敷に移っている。
1480年 、秩父から長尾景春が越生に出撃して太田道真を襲うが破れる、という事件があり、越生近在には多くの武者達が居住していたようである。
太田軍の主力は身分の低い傭兵(野武士)が主だったようで、このことから足軽戦法ともよばれている。江戸時代に書かれたこの山吹伝説がもし本当にあった話なら、
やはり道灌が父に会いに往く途中に俄雨にあって立ち寄ったのは越生の近在、道真配下の者の家で(道真・配下の者なら和歌をたしなんでいても不思議はない。)
蓑のないのを恥じて娘に山吹の花を持たせた・・。山吹伝説。・・資料より
道灌山から見た下町

「室町時代中期・道灌と日暮里」は、JR西日暮里駅脇の小高くなった台地が道灌山、諏訪台とも呼ばれている。
この台地にある諏方神社の「諏訪大明神略記」には、室町時代中期の1455年、荒川区を含む武蔵豊島郡を支配していた豊島氏と激しく争っていた太田道灌が諏方神社に
祈願し社領を寄進した旨が記されている。
道灌山は大河隅田川、東京湾に近接し水運利用には格好の場所であり、豊島氏の本城が石神井城にあったことなど考えると軍事戦略に秀でた
太田道灌が
ここに出城を築いたのは当然であるという。
日暮里の諏訪大社に戦勝祈願し練馬方面と兵を向けた。
1476年に関東管領山内上杉家の家宰を二代続けて出した白井長尾家の長尾景春が顕定に叛き、豊島氏の当主泰経は景春に加担して石神井城、練馬城で挙兵。
弟の泰明も平塚城で挙兵している。これにより、江戸城と河越城の連絡が絶たれて太田道灌は危機に陥るが、1477年の江古田・沼袋原の戦いで泰経は道灌に大敗を喫し
、泰明は戦死し、石神井城も落とされてしまうのである。
1478年に泰経は平塚城で再挙するが、道灌の攻撃を受けて落城。小机城に逃れるが、ここも落とされ、泰経は行方知れずとなり豊島氏本宗家は滅亡したという。
1478年には、「江戸名所図絵」には道灌がこの地に砦を築いた際に諏方神社を鎮守とした図が残されている。
道灌は、1486年、に主君の関東管領上杉定正に謀殺され関東南部は再び戦乱の地になる。
1524年、北条氏綱が上杉氏を破り江戸城に入り後北条氏の時代を迎えるが、僅か約30年後には徳川家康が江戸城に入城し江戸時代を迎え、近代史へと歩みを進める。
この辺りの台地は“道灌山”と呼ばれ江戸時代には景勝地として知られていた場所。

道灌の名声が主家の扇谷上杉定正を上回るようになってくると、定正もしだいにも自分の懐刀である道灌の存在を恐れるようになる。
利用したのが、分家の台頭を面白く思わない上杉家の本家、山内上杉顕定だった。顕定は定正に道灌暗殺をそそのかし、定正はその気にする。
「謀 殺」1486年 道灌は上杉定正の召しにより、相模国糟谷の上杉定正邸を訪れ、このときすでに定正と本家の顕定との間に道灌暗殺の密約ができていることなど、
道灌には思いもよらぬことであった。
上杉邸に入った道灌は、道中の疲れをいやすようにと風呂に案内された。やがて、入浴を終えた道灌が、風呂の小口を出ようとして首を出したところ、
定正の家来、曽我兵庫がとび出して斬りつけた。 道灌はひと声「当方滅亡」と叫んで、そのまま息絶えたという。道灌55歳であった。
当方滅亡とは、当家滅亡。つまり、これほど忠誠を尽くしてきた自分を殺すという上杉家は滅亡するに違いない、という意味である。そして実際に上杉両家はこの後、
衰退の途をたどることになる。
道灌山に建つ開成中・高校 道灌坂


道灌の一首に、
「 きのふまで まくまうざうを 入れおきし へんなしぶくろ 今破りけり 」
戦国初期、まだ下克上は一般的なことではなかった。道灌は潔癖な人間であり、道灌自身も上杉家を乗っ取ろうとか滅ぼそうというような考えはまったく持っていなかったようだ。
道灌は、上杉家のためによく働いた。しかし、主君のほうは下克上の影におびえたようである、道灌と同世代の人間に北条早雲がいる。早雲は小田原を手に入れ、
関東の覇者になった。もし、道灌が存命し上杉家をまとめていたら、その後の勢力図がどうなっていたか、興味深いところである。
現在の西日暮里公園 駅沿いの山の手



道灌は30数回の合戦を戦い抜き、ほとんど独力で上杉家の危機を救った。
「太田道灌状」で「山内家が武・上の両国を支配できるのは、私の功である」と自ら述べている。
道灌山の桜並木


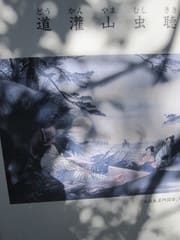
「諏方神社」は、1202年 豊島左衛門尉経泰が信州諏訪神社より勧請して創建したという。
江戸期には日暮里(新堀)村・谷中町の総鎮守として崇敬を集め、また慶安2年には社領5石の朱印状を拝領していたほか、日暮の里として江戸有数の景勝地として有名。
太田道灌が戦勝祈願した諏訪神社



次回は上野浅草羽子板市へ














































































































