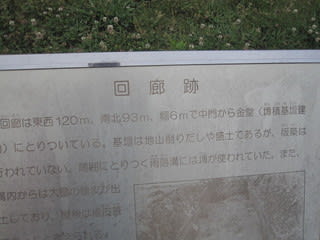「大垣城」
駅南約700mに「大垣城」がある。
関ケ原の戦い(1600年)で西軍「石田三成」の本拠地とした。東軍の攻撃で落城した。1635年以降は、戸田氏の居城で、国宝の天守閣と艮櫓が残っていたが、1945年・昭和20年戦災で消失、59年復元した。城跡・大垣公園・博物館などがある。
芝一面の大垣公園 (公園面積30.200m2)

「戸田氏鉄公」は、治山治水を進め、開墾・山には植林・伐採を止めた。入封16年目の大洪水「慶安寅年の大水」洪水史上大被害だったと云う。
このような水害を守るため、美濃特有の堤塘に包まれた「輪中」が発達している。(輪中・村落の周囲を土手で囲った)
「公園」は、城郭内・本丸・二の丸跡に出来た。面積30.200m2・大垣城は、別名「巨鹿城」と呼ばれ木々の緑・桜で知られ、天守閣からの眺めも素晴らしい。天守閣は、4階が展望台で、地域の気象通報所の役目をしていると云う。赤「城から赤玉がでたぞ、台風がくるぞ」白旗は「晴天」水色が「曇」
初代藩主戸田氏鉄の像 1535年宮川吉左衛門尉安定が築城と明応9年竹腰氏説もある

城は、1535年「宮川安定」が築城・「竹腰尚網説もある」で、水門川を外堀に利用した小さい城であったと云う。
その後、増築増築で、天守閣が 1595年「伊藤祐盛」が造営。1620年「松平・久松氏」4重4階ごめ様式優美な城で名高く、歴史上にも剰余な役割をしている。現在は、昭和34年完成している。
大垣城天守閣 木曽川など永年水との戦いに明け暮れた

戸田大垣藩藩祖「戸田一西」公。
戸田一西公は 大垣藩の藩祖. 三河国・田原城主 戸田宗光の第六世で 徳川広忠・家康に仕えて戦に従い 勇名を馳せた,天正18年戦功により武蔵国鯨井城主となり 次いで近江国 大津城を経て 同国膳所城に転じた。 戸田氏鉄公は一西公の子で 膳所城主より尼が埼城主に移り、1635年・大垣十万石の城主となった。常葉明神の神号を受けている。
戸田藩祖戸田一西公

「関ケ原の合戦」
1600年、石田三成ら豊臣方の西軍は、徳川家康を打つため美濃の国の入る。ときの大垣城主、「伊藤盛宗」は、豊臣家の家臣で、西軍に属していた。
三成は、大垣城に入城して西軍の本拠とし、南宮山にかけ諸将に陣を張らせた。
東軍の進出が早く、美濃の緒城を攻略して、大垣城西北の赤坂岡山を中心に布陣していた。西軍の動揺大。
「島左近」(勝猛)西軍は、1計を案じ東軍を誘い、南一色の地に配置し伏兵と呼応し笠縫・笠木で勝利を得た。これを「杭瀬川の戦い」。
西軍はここまでで、東軍徳川方の作戦におびき出され、大垣城に兵7500人残し、関ケ原に移動し、一大決戦となった。
最後に、ここ大垣城の攻防戦で、西軍よく戦っている。「7騎多門」・「おあむ物語」が伝わる。
寛永12年・1635年江戸幕府は、「戸田左門 氏鉄」10万で入城、明治元年、10代続く。氏鉄は1637年「島原の乱」に出兵。
明治時代の大垣城

「戸田大垣藩誕生」
江戸時代1601年「石川康通」が5万石で城主に任命された。1635年「戸田氏鉄」が摂州尼崎より入封するまで35年間あるが、江戸幕府の人事異動が激しく、石川氏3代・松平2代・岡部2代、、変わっていたのは、大阪冬・夏の陣である。
戸田氏大垣藩は、235年太平の世を続けた。
城内



城門 一部石垣 関ヶ原の戦い



「石田三成」 1560-1600 徳川軍と天下分け目の合戦を。
五奉行の一人、「佐和山城主」、正継の子として近江国で誕生している。幼名佐吉。豊臣秀吉に見出されて近侍し、豊臣政権の吏僚として活躍する。
秀吉没後に、家康打倒を画策、「関ヶ原の戦い」敗れて処刑された説と、処刑されず佐竹義宣に匿われて71才まで長生したとも云われている。
処刑に向かう途中で、三成は、喉の渇きを覚えて湯を求め、警固の士が、「これで我慢せよ」と干し柿を与えると、三成「これは痰の毒なり、食すまじ」
と返したと云う。警固達が「今から処刑される人間が毒忌するとは、、」笑ったと云う。
これに対し三成は、「大義を思う者は、首を斬られる瞬間まで命を大切にし、本意を遂げようとするものだ、、、」と返したと云う。
関ヶ原の戦い


「佐和山城跡」
彦根駅の北側、佐和山・232.5mにある城跡。
不破の関があった関ケ原に近く、交通の要衝でした。
近江守護佐々木氏によって築城され、1590年 石田三成が、佐和山城主となってから、5層の天守を構え、鳥居本を大手とする立派な城だったという。
三成が関ケ原の戦いで破れた後、徳川家老・井伊直政が新しい城主に、1606年、彦根城築城にともない廃城に。
関ヶ原の戦い


石田軍は、東軍の攻撃を防いだ、小西・宇喜多の敗走の後、三成は「伊吹山」に逃走した。天下分け目の戦いも東軍勝利で終わる。
西軍本隊が関ケ原へ移動後、大垣城は、三成の妹婿「福原長尭」らが 7500の兵で守り、関ヶ原の戦い後も戦っている。
この時、二の丸多門は、大垣の土沼波・松井氏等「七騎が防戦」その名が残り「七騎多門」と称した。
1600年9月15日午前8時火蓋が切られ、大垣城は、9月23日開城している。
1600年三成ら豊臣西軍は、徳川家康を討つため美濃に入る、時の大垣城主「伊藤盛宗(3万4千石)」は、豊臣家家臣



1616年 2万石加増を受け摂津国尼崎に移封された「戸田氏鉄」が1635年 「大垣城」に移封、10万石を封与された。
氏鉄は、新田開発・治山治水事業と文教復興につくし、藩政の基礎を築いた。
戸田氏は、235年間、明治「版籍奉還」の世が続いた。
天守閣から



徳川軍の陣地
「桃配山」は、国道21号線を挟んで中山道の松並木のほぼ向かい、「桃配山」は二大戦の陣跡と言われている。
家康は関ケ原合戦早朝に、赤坂から桃配山に兵を移動し、桃配山の中腹に陣を敷き、この山は、関ケ原合戦以前の壬申の乱にて、勝者である
「大海人皇子」が野上行宮より出陣し陣を敷いたという言い伝えがある。
家康は縁起を担ぎこの場所に陣を置いたといわれている。
戸田氏鉄人物像 江戸時代の鉄砲



壬申の乱の時、大海人皇子に村人より山桃が献上され、大海人皇子は、その山桃が非常に美味であったので、兵士の士気を上げようと大量に購入。
その故事により「桃配山」と名づけられた。
山桃は今も桃配山で見ることができる。
城内


次回は、美濃国分寺へ。