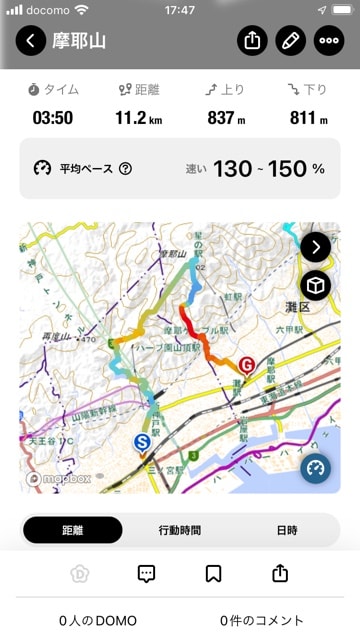三浦半島はその全域を丘陵に覆われ、平坦な場所は横須賀の海岸部と南端の三崎に限られます。その付け根の鎌倉に当時の政権が誕生したのはこの三浦半島の位置に重要な意味があったと言われています。その意味は、三浦半島最高峰の大楠山に登ればわかるのだとか。




山頂からの西方面。相模湾を挟んで伊豆半島が見えます。雲の向こうには富士山があります。

南西方向。右に伊豆半島南端と左に伊豆大島。

南は三浦半島南端の三崎。

東は房総半島。

北東には横浜と関東平野。

大楠山山頂には広場と休憩所がありますが、展望台は老朽化のため登れません。少し秋谷側に戻ると国交省レーダー雨量観測所と展望台があります。360度のビューはここからがオススメです。その後、ゴルフ場の横を通り、湘南国際村に入ります。国際村からは舗装された遊歩道が整備されて、最後に階段の急登はありますがのんびり海を見ながらの散策が楽しめます。

湘南国際村はバブル期に計画され、1994年にオープンしました。国際交流や人材育成を目的として、各種研究機関や研修施設を誘致した住宅街併設の大規模開発地区です。天気が良ければ相模湾の向こうに伊豆半島と富士山が見える、風光明媚な場所です。その後、研究機関の誘致は進まず、研修の開催も期待通りには進まず、今はどちらかといえば観光や自然に触れる場所として訪れる人が多いような感じです。開発された場所も一部は元の雑木林に戻すべく植林が行われています。この一帯のお話は、別の機会に改めてしてみたいと思います。

大楠山は、三浦半島西海岸の秋谷と横須賀の間にある、標高は241mほどの低山です。今日はいつもの逗子渚橋交差点から国道134号線を秋谷まで南下します。葉山、長者ヶ崎、久留和と続く冬の相模湾は夏の喧騒とは打って変わり、静かで海の色もオフショアのお陰で澄んでいます。前田橋の交差点から山側に入り、住宅街をしばらく進むとすぐに三浦半島の背骨をなす丘陵にとりつきます。

三浦半島はほとんど山で、しかも海岸から急坂に取り付く場所が多いです。義経の鵯越の逆落とし、は有名ですが三浦の武士たちはこの辺りの急坂を登り降りしていたので、さほどのことではなかったのだ、という説もあるとか。

かつてはこの山道を越えて、三浦の東西を行き来していたのでしょう。

山頂からの西方面。相模湾を挟んで伊豆半島が見えます。雲の向こうには富士山があります。

南西方向。右に伊豆半島南端と左に伊豆大島。

南は三浦半島南端の三崎。

東は房総半島。

北東には横浜と関東平野。
三浦半島は伊豆半島と房総半島の中間に位置し、安房、武蔵、伊豆という広大な土地と武力の中心に位置していた事が分かります。確かに、介殿は伊豆で蜂起、敗れた後、三浦の勢力と共に海を渡って房総に上陸、そこで再起して鎌倉に入ったとされます。大楠山に登るとこの事がビジュアルにわかると言う事なのでしょう。大河ドラマに影響されて、改めて地元の歴史を学びました。

大楠山山頂には広場と休憩所がありますが、展望台は老朽化のため登れません。少し秋谷側に戻ると国交省レーダー雨量観測所と展望台があります。360度のビューはここからがオススメです。その後、ゴルフ場の横を通り、湘南国際村に入ります。国際村からは舗装された遊歩道が整備されて、最後に階段の急登はありますがのんびり海を見ながらの散策が楽しめます。

湘南国際村はバブル期に計画され、1994年にオープンしました。国際交流や人材育成を目的として、各種研究機関や研修施設を誘致した住宅街併設の大規模開発地区です。天気が良ければ相模湾の向こうに伊豆半島と富士山が見える、風光明媚な場所です。その後、研究機関の誘致は進まず、研修の開催も期待通りには進まず、今はどちらかといえば観光や自然に触れる場所として訪れる人が多いような感じです。開発された場所も一部は元の雑木林に戻すべく植林が行われています。この一帯のお話は、別の機会に改めてしてみたいと思います。